この本のタイトルには「医療・介護スタッフ必修」とありますが、いつどこで誰が自分の目の前で倒れるかは分からないので、一般常識として多くの人におすすめしたい本です。
窒息、過換気症候群、頭部外傷、急性心筋梗塞、骨折、出血、火傷、アナフィラキシーショック、熱中症など、様々な状況に応じた対処法が載っています。
いざという時は気が動転してオロオロしてしまいがちだけれど、とっさの処置が出来るか出来ないかで、誰かの生死やその後の後遺症の程度にも影響しますから、しっかり頭に入れておきたいです。
まずは、「救急のABCD」を頭に入れておきたいです。
Aは気道確保(エアウェイ)、Bは呼吸(ブリージング。人工呼吸)、Cは循環(サーキュレーション。心臓マッサージや止血)、Dは電気的除細動(デフィブリレーション。よく目にするAEDはAutomated External Defibrillatorの略)。
わたしは身近な人たちが頭部外傷で亡くなったり頚椎損傷で障害を負ったりしていますので、特にP36〜37に載っている対処法をしっかり頭に叩き込み、いざという時はバイタルサインの確認や頚椎の保護をして救急車を呼びたいです。
熱中症について、「熱中症になると、筋肉の細胞が壊れてコーヒー色をした尿(ミオグロビン尿)が出ることがあります。ミオグロビンが尿細管に詰まると腎臓がダメージを受けます。肝臓などほかの重要臓器も障害を受ける危険性があります。症状が進むと、集中治療を行わざるをえません」(P78から抜粋)と書かれていて、改めて熱中症の恐ろしさにゾッとしました。
熱中症にならないための対策を徹底したいです。
この本の最後のページには、「救急処置がうまくいったときには達成感が得られます。しかし、うまくいかなかったとき、自責の念にかられます。時には悪い記憶がよみがえるのかもしれません。また、傷病者のその後の経過がわからないとイライラもたまります」(P102から抜粋)と救急救命にあたる人への心のケアや、二次災害・ケガ・感染から自分を守ることの重要性についても触れられています。
こう言ったら不謹慎なのかもしれませんが、救える命もあれば救えない命もあるというのが現実。
誰かを救おうとして結果的に救えなかったとしても、自分を責めないで欲しいです。
そういうのは見殺しにしたのとは違いますから。
窒息、過換気症候群、頭部外傷、急性心筋梗塞、骨折、出血、火傷、アナフィラキシーショック、熱中症など、様々な状況に応じた対処法が載っています。
いざという時は気が動転してオロオロしてしまいがちだけれど、とっさの処置が出来るか出来ないかで、誰かの生死やその後の後遺症の程度にも影響しますから、しっかり頭に入れておきたいです。
まずは、「救急のABCD」を頭に入れておきたいです。
Aは気道確保(エアウェイ)、Bは呼吸(ブリージング。人工呼吸)、Cは循環(サーキュレーション。心臓マッサージや止血)、Dは電気的除細動(デフィブリレーション。よく目にするAEDはAutomated External Defibrillatorの略)。
わたしは身近な人たちが頭部外傷で亡くなったり頚椎損傷で障害を負ったりしていますので、特にP36〜37に載っている対処法をしっかり頭に叩き込み、いざという時はバイタルサインの確認や頚椎の保護をして救急車を呼びたいです。
熱中症について、「熱中症になると、筋肉の細胞が壊れてコーヒー色をした尿(ミオグロビン尿)が出ることがあります。ミオグロビンが尿細管に詰まると腎臓がダメージを受けます。肝臓などほかの重要臓器も障害を受ける危険性があります。症状が進むと、集中治療を行わざるをえません」(P78から抜粋)と書かれていて、改めて熱中症の恐ろしさにゾッとしました。
熱中症にならないための対策を徹底したいです。
この本の最後のページには、「救急処置がうまくいったときには達成感が得られます。しかし、うまくいかなかったとき、自責の念にかられます。時には悪い記憶がよみがえるのかもしれません。また、傷病者のその後の経過がわからないとイライラもたまります」(P102から抜粋)と救急救命にあたる人への心のケアや、二次災害・ケガ・感染から自分を守ることの重要性についても触れられています。
こう言ったら不謹慎なのかもしれませんが、救える命もあれば救えない命もあるというのが現実。
誰かを救おうとして結果的に救えなかったとしても、自分を責めないで欲しいです。
そういうのは見殺しにしたのとは違いますから。
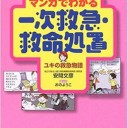

コメント