著…山崎陽子『きものが着たくなったなら』
2020年4月4日 おすすめの本一覧 コメント (2)
「時々しか着ないと、もう着ること自体が面倒になり、そのうち着方も忘れてしまいます。だから、できるだけふだん着的な紬や小紋でスタートするといいと思うのです」
(P14から抜粋)
という著者の考え方にわたしは共感しました。
こういう軽やかな考え方の人が増えてくれれば良いなぁと心の底から思います。
せっかく「着物を着てみたいな」と思ってまずはカジュアルな着物で街へ出かけてみた人が居ても、いわゆる「着物警察」と呼ばれる人たちが頼んでもいないのにどこからともなく寄って来て、「訪問着じゃないとどうたらこうたら」「正絹じゃないとどうたらこうたら」とネチネチお説教をしてくることって、多いんです。
「着物警察」に悪気は無く、むしろ着物の伝統を「正しく」「上品に」継承させたいそうなのですが、赤の他人からお説教をされる側はたまったものではありません。
「嫌な思いをさせられた。着物なんて着るんじゃなかった」と若い芽を潰すだけ。
わたしも木綿の着物を着てお茶のお稽古に向かっていたら赤の他人の「着物警察」に不当逮捕されて「あなたその着物いくら?安そう。正絹の訪問着を買えないの?」と着物をベタベタ触られて嫌な思いことをしたことがあります。
今からお稽古でお抹茶が付くかもしれないのに、いちいち正絹の訪問着なんて着ていられるかっ!というか他人の着ているものを勝手に触るとかあり得ん!!と内心思いながら、「失礼ですがどちら様でしょうか? 貴方さまのことを存じ上げないのですが。急いでおりますので失礼いたします」とわたしは返事をして着物警察をスルーしてやりましたが。
(着物警察は「せっかく教えてあげたのに!これだから今時の人は」と憤慨していましたが。昔の人でもあなたのような人は嫌だと思いますよ、と言ってやれば良かったなと今では思いますが余計怒られそうだから止めて正解ですね)
着物を「特別なもの」とか「高尚なもの」だと捉えると、こうした「着物警察」みたいな凝り固まった考えになってしまうのだと思います。
けれど、着物って昔の日本人は日常的に着ていたはずですよね?
だから、普段着として気軽に楽しみましょう!
「お出かけする日だけでなく、家で過ごす日も積極的に身につける。そうやって、できれば週に1回、3時間着るようにすると、きものが体に寄り添ってくるし、体がきものに慣れてきます。それまで敬語で話していたきものが、友達言葉でしゃべりかけてくるようになるのです」
(P14から抜粋)
著者のこういう考え方、良いなぁ。
わたしも着物を着る機会をどんどん増やしていこうと思います。
高いものは買えないので、安いものや、リサイクル品をうまく組み合わせて、着物を楽しく着たいです。
着物は着たくなった時が着るタイミングです!
(P14から抜粋)
という著者の考え方にわたしは共感しました。
こういう軽やかな考え方の人が増えてくれれば良いなぁと心の底から思います。
せっかく「着物を着てみたいな」と思ってまずはカジュアルな着物で街へ出かけてみた人が居ても、いわゆる「着物警察」と呼ばれる人たちが頼んでもいないのにどこからともなく寄って来て、「訪問着じゃないとどうたらこうたら」「正絹じゃないとどうたらこうたら」とネチネチお説教をしてくることって、多いんです。
「着物警察」に悪気は無く、むしろ着物の伝統を「正しく」「上品に」継承させたいそうなのですが、赤の他人からお説教をされる側はたまったものではありません。
「嫌な思いをさせられた。着物なんて着るんじゃなかった」と若い芽を潰すだけ。
わたしも木綿の着物を着てお茶のお稽古に向かっていたら赤の他人の「着物警察」に不当逮捕されて「あなたその着物いくら?安そう。正絹の訪問着を買えないの?」と着物をベタベタ触られて嫌な思いことをしたことがあります。
今からお稽古でお抹茶が付くかもしれないのに、いちいち正絹の訪問着なんて着ていられるかっ!というか他人の着ているものを勝手に触るとかあり得ん!!と内心思いながら、「失礼ですがどちら様でしょうか? 貴方さまのことを存じ上げないのですが。急いでおりますので失礼いたします」とわたしは返事をして着物警察をスルーしてやりましたが。
(着物警察は「せっかく教えてあげたのに!これだから今時の人は」と憤慨していましたが。昔の人でもあなたのような人は嫌だと思いますよ、と言ってやれば良かったなと今では思いますが余計怒られそうだから止めて正解ですね)
着物を「特別なもの」とか「高尚なもの」だと捉えると、こうした「着物警察」みたいな凝り固まった考えになってしまうのだと思います。
けれど、着物って昔の日本人は日常的に着ていたはずですよね?
だから、普段着として気軽に楽しみましょう!
「お出かけする日だけでなく、家で過ごす日も積極的に身につける。そうやって、できれば週に1回、3時間着るようにすると、きものが体に寄り添ってくるし、体がきものに慣れてきます。それまで敬語で話していたきものが、友達言葉でしゃべりかけてくるようになるのです」
(P14から抜粋)
著者のこういう考え方、良いなぁ。
わたしも着物を着る機会をどんどん増やしていこうと思います。
高いものは買えないので、安いものや、リサイクル品をうまく組み合わせて、着物を楽しく着たいです。
着物は着たくなった時が着るタイミングです!
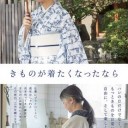

コメント
あまり大きな声で言えないですが、(そういう人が生きてるから)着物文化を廃れさせた人は着物で儲けてる古い体質の人たちです。着る、という点でいえば着ないとどんどん廃れていくので着ないといけないのですが、古い人たちは適当な物を来てると自分は洋服着てるのに文句を言うのです(汗) 特に女性の着物にはそういうのが顕著に出ていると思います。 私も恥ずかしながらユザワヤで買った生地で(木綿)自分用の着物を仕立てた(作った)人間ですが、男子の場合、木綿のを着ていてもさほど文句を言われないですね。(女子の着物って特別?) うちのは半襟も帯もアレンジしてきてますけど(お太鼓なんてほとんどしない)「古い」人から見たら異形の姿なんだと思いますね。 そうですね、着物警察ってのはいい表現です。 某着付け教室(無料)には沢山いそうです(金づるになるから) また、着物(和装)の事を書いてください! 突然横槍失礼ました。
本当にその通りですよね。
そういった人たちが着物文化を廃れさせているのだと思います。
自分用に着物を仕立てるのって素敵ですね!
少なくともわたしがこれまでに出会った「着物警察」はみんな女性でしたから、男性にはお説教しにくいのかもしれません。
半襟も帯も、アレンジして自分好みに着こなした方が楽しいですよね。
着付け教室は、何百万円もする着物を買わないと外へ出してもらえないなど、色々怖い話を耳にします…。
そうやって押し売りされた着物が愛されるはずもないのに。
着物を売る側に着物への愛が無いというのはとても残念ですよね…。
ありがとうございます。
また着物について書きたいと思います。