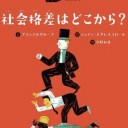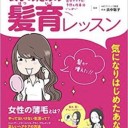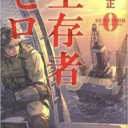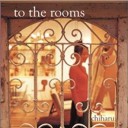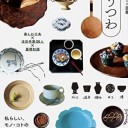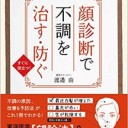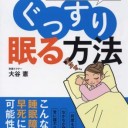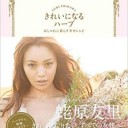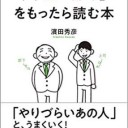災害への備えと美しさを兼ね備えたインテリアの本。
モダニズム。
ミッドセンチュリー。
北欧。
シャビー・シック。
ナチュラル。
エスニック。
和モダン。
そしてこれらをミックスしたテイスト。
こうした様々な好みに合わせて、不要な収納や破損しやすい照明を見直し、避難経路の確保や、彩度や明度などによって印象が変わる「色」の仕組みも意識しながら、自分らしいインテリアを作り上げる方法が紹介されています。
「大掛かりなリフォームや家具の買い替えは出来ないけれどお洒落に暮らしたい!」という方には第7章『心地よい空間のためのディスプレイ』がおすすめ。
小物をセンス良く配置するだけで、同じ小物でも印象がガラリと変わります。
モダニズム。
ミッドセンチュリー。
北欧。
シャビー・シック。
ナチュラル。
エスニック。
和モダン。
そしてこれらをミックスしたテイスト。
こうした様々な好みに合わせて、不要な収納や破損しやすい照明を見直し、避難経路の確保や、彩度や明度などによって印象が変わる「色」の仕組みも意識しながら、自分らしいインテリアを作り上げる方法が紹介されています。
「大掛かりなリフォームや家具の買い替えは出来ないけれどお洒落に暮らしたい!」という方には第7章『心地よい空間のためのディスプレイ』がおすすめ。
小物をセンス良く配置するだけで、同じ小物でも印象がガラリと変わります。
チコちゃんが旅に出ました!
埼玉県大里郡寄居町の波久礼駅にやって来たチコちゃんはこう言いました、
「チコはひとりだけど、はぐれたわけじゃないんだけどね!」
と。
えっ、そのギャグを言うためにわざわざその駅へ!?
チコちゃんが駅員さんにニカッと笑って切符を渡す姿が、なんとも言えず愛らしいです。
今時の5歳はPASMOやSuicaなどのICカードに慣れているだろうに、ちゃんと切符を渡せて偉いなあ!
他にもチコちゃんは、埼玉県秩父郡長瀞町で焼き立てのおせんべいを買ったり、寳登山神社にお参りして御朱印を頂いたり、鮎飯を食べたりと、なかなか渋い旅を楽しんだようです。
この調子でチコちゃんが全国を旅してくれたら楽しいだろうなあ。
チコちゃんならではの視点でその地域の魅力を紹介してくれそう。
埼玉県大里郡寄居町の波久礼駅にやって来たチコちゃんはこう言いました、
「チコはひとりだけど、はぐれたわけじゃないんだけどね!」
と。
えっ、そのギャグを言うためにわざわざその駅へ!?
チコちゃんが駅員さんにニカッと笑って切符を渡す姿が、なんとも言えず愛らしいです。
今時の5歳はPASMOやSuicaなどのICカードに慣れているだろうに、ちゃんと切符を渡せて偉いなあ!
他にもチコちゃんは、埼玉県秩父郡長瀞町で焼き立てのおせんべいを買ったり、寳登山神社にお参りして御朱印を頂いたり、鮎飯を食べたりと、なかなか渋い旅を楽しんだようです。
この調子でチコちゃんが全国を旅してくれたら楽しいだろうなあ。
チコちゃんならではの視点でその地域の魅力を紹介してくれそう。
「金持ちの子は、うまれたときから金持ちで、びんぼうな人の子は、うまれたときからびんぼうだ」
という残酷な真実。
上流階級・中産階級・労働者階級の違い。
上流階級はますます豊かになって自分の分け前を減らすまいとし、中産階級は貧しくなり、労働者階級は仕事を見つけられなくなっている。
これは、こうした格差の広がりについて子どもに教える絵本です。
単に現状を教えるだけではなく、
「いまの日本に社会格差はあると思う?」
「なぜ社会格差があるのだろう?」
「いちばん幸せなのはどの階級だと思う?」
「社会格差がなかったら、みんな公平にくらすことができるだろうか?」
「社会格差は、どうしたらちぢまるだろう?」
と自分で考えたり、友達や家族と考えるきっかけをくれる絵本でもあります。
という残酷な真実。
上流階級・中産階級・労働者階級の違い。
上流階級はますます豊かになって自分の分け前を減らすまいとし、中産階級は貧しくなり、労働者階級は仕事を見つけられなくなっている。
これは、こうした格差の広がりについて子どもに教える絵本です。
単に現状を教えるだけではなく、
「いまの日本に社会格差はあると思う?」
「なぜ社会格差があるのだろう?」
「いちばん幸せなのはどの階級だと思う?」
「社会格差がなかったら、みんな公平にくらすことができるだろうか?」
「社会格差は、どうしたらちぢまるだろう?」
と自分で考えたり、友達や家族と考えるきっかけをくれる絵本でもあります。
日本全国の和菓子、郷土菓子、ケーキ、焼き菓子、ジュレ、ジャム、調味料、飲料といったお土産のパッケージデザインを紹介する本。
わたしはまずP16〜19掲載の「三角だるま最中」に目を奪われました。
この、口髭を生やしたひょうきんなおじさんが「およ?」「おや?」「あら?」と、とぼけたみたいな顔が堪りません!
もしわたしがこの最中を入手したら、すぐには食べずに、しばらく飾っておきたいです。
赤いおじさん。
青いおじさん。
いや〜、可愛い!
おじさんを育てる箱庭ゲームアプリにハマっている友達が我が家へ遊びに来た時に、このおじさんたちをテーブルにちょこんと置いておきたいです。
友達のリアクションを見たい!
でも、何だかおじさんに情が移ってしまって、食べるタイミングを逃してしまいそう…。
パッケージを取ったら、最中そのものもおじさんの姿をしていて可愛いし…。
もしわたしや友達がおじさんを食べた場合、『進撃の巨人』の捕食シーンみたいになりそう…。
かと言って、おじさんは最中なのだから、食べられてナンボのさだめ…。
うーん。
わたしはまずP16〜19掲載の「三角だるま最中」に目を奪われました。
この、口髭を生やしたひょうきんなおじさんが「およ?」「おや?」「あら?」と、とぼけたみたいな顔が堪りません!
もしわたしがこの最中を入手したら、すぐには食べずに、しばらく飾っておきたいです。
赤いおじさん。
青いおじさん。
いや〜、可愛い!
おじさんを育てる箱庭ゲームアプリにハマっている友達が我が家へ遊びに来た時に、このおじさんたちをテーブルにちょこんと置いておきたいです。
友達のリアクションを見たい!
でも、何だかおじさんに情が移ってしまって、食べるタイミングを逃してしまいそう…。
パッケージを取ったら、最中そのものもおじさんの姿をしていて可愛いし…。
もしわたしや友達がおじさんを食べた場合、『進撃の巨人』の捕食シーンみたいになりそう…。
かと言って、おじさんは最中なのだから、食べられてナンボのさだめ…。
うーん。
・生命維持に直接関係のない髪に栄養が送られる優先順位は低いので、髪まで栄養がいくよう、日頃からバランスの良い食事をする。
・髪の成長に欠かせない成長ホルモンの分泌量を維持するため、質の良い睡眠を十分にとる。
・髪に栄養を運ぶのは血液なので、適度な運動と体重管理を行い、体全体の血流を良くする。
といった3つのポイントが載っている本。
特に、P46掲載の正しいシャンプーの仕方とすすぎ方や、P56〜57掲載の正しいドライテクニックが参考になります。
意外にも、日頃ちゃんと頭皮を洗えていない人は多いもの。
シャンプーの泡をつけただけで「洗ったつもり」になって、耳のまわり、側頭部、生え際といったところに汚れが残っていたり、シャンプー・トリートメント類のすすぎ残しがあって肌荒れしている人は多いそうなので、正しいケア方法を覚えたいです。
・髪の成長に欠かせない成長ホルモンの分泌量を維持するため、質の良い睡眠を十分にとる。
・髪に栄養を運ぶのは血液なので、適度な運動と体重管理を行い、体全体の血流を良くする。
といった3つのポイントが載っている本。
特に、P46掲載の正しいシャンプーの仕方とすすぎ方や、P56〜57掲載の正しいドライテクニックが参考になります。
意外にも、日頃ちゃんと頭皮を洗えていない人は多いもの。
シャンプーの泡をつけただけで「洗ったつもり」になって、耳のまわり、側頭部、生え際といったところに汚れが残っていたり、シャンプー・トリートメント類のすすぎ残しがあって肌荒れしている人は多いそうなので、正しいケア方法を覚えたいです。
著…安生正『生存者ゼロ』
2020年1月31日 おすすめの本一覧
未知の感染症に立ち向かう人々を描いた小説。
それまで普通に暮らしていた人間がみるみるうちに無残な遺体へと変わり、その原因も治療法も不明、あっという間にパンデミック発生…という絶望的な状況においても諦めない登場人物たち。
奇しくも、新型肺炎ウイルスの患者数増加によって、今まさに日本を含む世界各国が戸惑いと恐怖を感じているところなので、わたしは登場人物たちの苦しみが他人事とは思えません。
この小説における感染症の原因は割とすぐに判明するため、パニックエンターテインメントを期待して読むと盛り上がりに欠けるため期待外れかもしれませんが、読んでいてイライラするほど愚鈍な政治家たちの姿が描かれているので、現実に警鐘を鳴らす小説として読むと読み応えがあります。
特に、感染症学者が首相から「細菌とウイルスの違いはなんだ」と問われる描写が印象的。
細菌とウイルスが違うものだということさえ分からない人が国の代表として感染症対策の舵を握っている…、ゾッとします。
それを受けて、感染症学者は、
「所詮、政治家とはその程度だ。ずぶの素人が、パンデミックの議論をしようとしているのか。彼らが背負っているのは国家の危機ではなく面子だ」
(P54から抜粋)
と考えます。
そう。単なる素人ならまだしも、面子を気にして初動対応が遅れるから、政治家は厄介です。
そういう政治家を国民が投票で選んだのだから仕方が無いのかもしれませんが…。
また、この小説の中では、中国をはじめとする各国やWHOが日本の感染症対応に不信感を抱く様子が描かれます。
この小説の中で起きていることと、今まさに現実で起きていることは異なっており、現実では日本を含む世界各国が、12月の時点で発症者が出ていたのに隠そうとしていた中国にも、緊急事態宣言を見送って中国に忖度したであろうWHOにも、特に初動対応に関して不信感を抱いているのですが、国同士が「面子」を守ろうとしている間にも罪なき命が失われていく点は小説も現実も共通しています。
くれぐれも、この小説のP465のような出来事が日本で起きないことを祈ります。
P465には、ある母親がその「感染症」によって死にかけながらも、我が子だけはなんとか助けようと、必死で我が子を生物研修者へ差し出すというシーンが描かれているからです。
そんな思いは誰にもさせてはいけません。
それまで普通に暮らしていた人間がみるみるうちに無残な遺体へと変わり、その原因も治療法も不明、あっという間にパンデミック発生…という絶望的な状況においても諦めない登場人物たち。
奇しくも、新型肺炎ウイルスの患者数増加によって、今まさに日本を含む世界各国が戸惑いと恐怖を感じているところなので、わたしは登場人物たちの苦しみが他人事とは思えません。
この小説における感染症の原因は割とすぐに判明するため、パニックエンターテインメントを期待して読むと盛り上がりに欠けるため期待外れかもしれませんが、読んでいてイライラするほど愚鈍な政治家たちの姿が描かれているので、現実に警鐘を鳴らす小説として読むと読み応えがあります。
特に、感染症学者が首相から「細菌とウイルスの違いはなんだ」と問われる描写が印象的。
細菌とウイルスが違うものだということさえ分からない人が国の代表として感染症対策の舵を握っている…、ゾッとします。
それを受けて、感染症学者は、
「所詮、政治家とはその程度だ。ずぶの素人が、パンデミックの議論をしようとしているのか。彼らが背負っているのは国家の危機ではなく面子だ」
(P54から抜粋)
と考えます。
そう。単なる素人ならまだしも、面子を気にして初動対応が遅れるから、政治家は厄介です。
そういう政治家を国民が投票で選んだのだから仕方が無いのかもしれませんが…。
また、この小説の中では、中国をはじめとする各国やWHOが日本の感染症対応に不信感を抱く様子が描かれます。
この小説の中で起きていることと、今まさに現実で起きていることは異なっており、現実では日本を含む世界各国が、12月の時点で発症者が出ていたのに隠そうとしていた中国にも、緊急事態宣言を見送って中国に忖度したであろうWHOにも、特に初動対応に関して不信感を抱いているのですが、国同士が「面子」を守ろうとしている間にも罪なき命が失われていく点は小説も現実も共通しています。
くれぐれも、この小説のP465のような出来事が日本で起きないことを祈ります。
P465には、ある母親がその「感染症」によって死にかけながらも、我が子だけはなんとか助けようと、必死で我が子を生物研修者へ差し出すというシーンが描かれているからです。
そんな思いは誰にもさせてはいけません。
この世には膨大な種類のウイルスが存在し、宿主に「寄生」または「共生」しながら生きています。
この本は、「インフルエンザウイルス」「エボラウイルス」「HIV(ヒト免疫不全ウイルス)」「デングウイルス」「ジカウイルス」「SARSコロナウイルス」「MERSコロナウイルス」「ポリオウイルス」「日本脳炎ウイルス」「狂犬病ウイルス」「麻疹ウイルス」「風疹ウイルス」といった、人体に有害なウイルスが引き起こす感染症・ワクチン・治療方法・感染対策などについてまとめた本です。
ウイルスがヒト・鳥・豚といった「種の壁」を越えてどう感染し、どう変異していくか想像するだけで、パンデミックが非常に恐ろしくなります。
現在、新型コロナウイルスによる肺炎が中国で多発しており、死者も出ていますが、ウイルス感染者が世界各国を訪れてしまい、感染被害が世界規模で拡大しています。
春節と時期が重なってしまったことが災いしたのもありますが、ウイルスがいかに危険なのかよく知らないことや、「予定をキャンセルするとキャンセル料が勿体ない」とか、「解熱剤を飲めば大丈夫だろう」という誤った判断をして出かけてしまうことが大きな要因となっているのだとわたしは思います。
なかには「ウイルスを理由に旅行を取りやめろと言うのは人権侵害だ」と怒る人も居るかもしれませんが、「人権」も勿論大切なのですが何よりも「人命」を最優先にしていただきたいです。
自分に悪気が無くても、他人に感染させてしまったら、それはもはやバイオテロ。
「あれっ」と体調に違和感を覚えたら、いくらせっかくの連休であろうとも出歩かず、自分の国できちんと治療を受けるのが一番です。
これ以上被害が拡大しないように、感染しない・感染させない知識と危機感を持つべきです。
この本は、「インフルエンザウイルス」「エボラウイルス」「HIV(ヒト免疫不全ウイルス)」「デングウイルス」「ジカウイルス」「SARSコロナウイルス」「MERSコロナウイルス」「ポリオウイルス」「日本脳炎ウイルス」「狂犬病ウイルス」「麻疹ウイルス」「風疹ウイルス」といった、人体に有害なウイルスが引き起こす感染症・ワクチン・治療方法・感染対策などについてまとめた本です。
ウイルスがヒト・鳥・豚といった「種の壁」を越えてどう感染し、どう変異していくか想像するだけで、パンデミックが非常に恐ろしくなります。
現在、新型コロナウイルスによる肺炎が中国で多発しており、死者も出ていますが、ウイルス感染者が世界各国を訪れてしまい、感染被害が世界規模で拡大しています。
春節と時期が重なってしまったことが災いしたのもありますが、ウイルスがいかに危険なのかよく知らないことや、「予定をキャンセルするとキャンセル料が勿体ない」とか、「解熱剤を飲めば大丈夫だろう」という誤った判断をして出かけてしまうことが大きな要因となっているのだとわたしは思います。
なかには「ウイルスを理由に旅行を取りやめろと言うのは人権侵害だ」と怒る人も居るかもしれませんが、「人権」も勿論大切なのですが何よりも「人命」を最優先にしていただきたいです。
自分に悪気が無くても、他人に感染させてしまったら、それはもはやバイオテロ。
「あれっ」と体調に違和感を覚えたら、いくらせっかくの連休であろうとも出歩かず、自分の国できちんと治療を受けるのが一番です。
これ以上被害が拡大しないように、感染しない・感染させない知識と危機感を持つべきです。
「立ちっぱなしでも疲れない靴が欲しい」
「おしゃれな靴は痛いものだと思って我慢して履いている」
「子どもができて、ハイヒールを履く機会が減った」
「走れるパンプスが欲しい」
といった女性たちの様々な要望や悩みにぴったりな靴について教えてくれる本。
文章だけでなく、イラストやコミックが豊富に使われているので、楽しく読めます。
「合わない靴を履いている人を見つけると威嚇する猫」というキャラクターも出てきて面白いです。
猫って、威嚇してくる姿さえも可愛いですね。
さて、この本には、自分の足長(そくちょう)・足囲(そくい)の測り方、つま先の形に合う靴の選び方、インソールの使い方、靴のメンテナンス方法が紹介されています。
ブーツ、サンダル、ローファー、ひも靴といった靴の種類によって確認すべきフィットポイントが違うので、わたしもしっかり覚えたいです。
また、この本の場合、単にサイズを合わせることだけを意識するのではなく、美脚に見える靴と服のコーディネート方法も紹介されているので、コーディネートを考える時の参考にもなります。
…以下は、直接この本とは関係の無い余談なので、興味のない方は読み飛ばしてください。
わたしは最近、捨て寸(足の指が自由に動ける、つま先10mm程度の余裕)を考慮するのをうっかり忘れて、ネットでぴったりし過ぎるパンプスを買ってしまいました。
「履いているうちに伸びるでしょ」と能天気に考えていたら、爪が痛いのなんの!
ちょっと歩いたら立ち止まって休憩、またちょっと歩いたら立ち止まって休憩、を繰り返してしまい、もはや「ひとりダルマさんが転んだ」状態!
ひとりでやるもんじゃないぞ!
あまりにも寂しいぞそれは。
しかも、「爪が痛いよう」と半ベソをかきながら帰宅したら、足の指のジェルネイルが剥がれていて、色んな意味でガックリきました。
でも、パンプスに罪はありません。
はい、全てわたしが悪いです!
せっかく買ったから、なんとか履けるようにしたいです。
しかし、自分の足よりも大きい靴はインソールを入れることである程度調整出来ますが、自分の足よりも小さい靴を調整するのは困難。
特別な道具が無くても今すぐ少しでもマシにする方法としては、「厚手の靴下を履いてからパンプスを履いたり、パンプスの着脱を繰り返す」という方法や、「パンプスに靴下などを詰めてドライヤーで温める」などの方法がありますが、パンプスの素材によっては痛みますし、効果が無いことも。
結局、わたしが購入失敗したそのパンプスは、上記の方法を試したら少しはマシになったのですが、靴のお直しのプロでも「横幅ならともかく縦幅を直すのは難しい」とおっしゃるくらいなので、誤差程度にしかマシにならず、やっぱり「ひとりダルマさんが転んだ」状態になるので、「もう買い物を失敗しないように」という教訓として、敢えて捨てずに、わたしの靴箱に置いたままにしてあります。
知人に譲ろうかとも思ったのですが、わたしの足のサイズは21.5cmなので、これを履ける大人はわたしの知人の中に誰一人として居ませんし、低めとは言えヒールがあるので知人の子どもにあげることも不可能!
が、このまま放置していても、せっかくのパンプスがかわいそうなので、横幅だけでなく縦幅も広げられるタイプのシューストレッチャーを近々購入する予定です。
わたしが買い物をミスしていなければ、シューストレッチャーを買うという余計な出費は無かったのに…!
悔しい!
わたしのようなアホはそう居ないでしょうし、まともな人はいくらネットで購入したと言っても「サイズが合わない」と気づいた時点で返品するはずですが、皆さま、靴を購入する際はくれぐれもお気をつけください。
「おしゃれな靴は痛いものだと思って我慢して履いている」
「子どもができて、ハイヒールを履く機会が減った」
「走れるパンプスが欲しい」
といった女性たちの様々な要望や悩みにぴったりな靴について教えてくれる本。
文章だけでなく、イラストやコミックが豊富に使われているので、楽しく読めます。
「合わない靴を履いている人を見つけると威嚇する猫」というキャラクターも出てきて面白いです。
猫って、威嚇してくる姿さえも可愛いですね。
さて、この本には、自分の足長(そくちょう)・足囲(そくい)の測り方、つま先の形に合う靴の選び方、インソールの使い方、靴のメンテナンス方法が紹介されています。
ブーツ、サンダル、ローファー、ひも靴といった靴の種類によって確認すべきフィットポイントが違うので、わたしもしっかり覚えたいです。
また、この本の場合、単にサイズを合わせることだけを意識するのではなく、美脚に見える靴と服のコーディネート方法も紹介されているので、コーディネートを考える時の参考にもなります。
…以下は、直接この本とは関係の無い余談なので、興味のない方は読み飛ばしてください。
わたしは最近、捨て寸(足の指が自由に動ける、つま先10mm程度の余裕)を考慮するのをうっかり忘れて、ネットでぴったりし過ぎるパンプスを買ってしまいました。
「履いているうちに伸びるでしょ」と能天気に考えていたら、爪が痛いのなんの!
ちょっと歩いたら立ち止まって休憩、またちょっと歩いたら立ち止まって休憩、を繰り返してしまい、もはや「ひとりダルマさんが転んだ」状態!
ひとりでやるもんじゃないぞ!
あまりにも寂しいぞそれは。
しかも、「爪が痛いよう」と半ベソをかきながら帰宅したら、足の指のジェルネイルが剥がれていて、色んな意味でガックリきました。
でも、パンプスに罪はありません。
はい、全てわたしが悪いです!
せっかく買ったから、なんとか履けるようにしたいです。
しかし、自分の足よりも大きい靴はインソールを入れることである程度調整出来ますが、自分の足よりも小さい靴を調整するのは困難。
特別な道具が無くても今すぐ少しでもマシにする方法としては、「厚手の靴下を履いてからパンプスを履いたり、パンプスの着脱を繰り返す」という方法や、「パンプスに靴下などを詰めてドライヤーで温める」などの方法がありますが、パンプスの素材によっては痛みますし、効果が無いことも。
結局、わたしが購入失敗したそのパンプスは、上記の方法を試したら少しはマシになったのですが、靴のお直しのプロでも「横幅ならともかく縦幅を直すのは難しい」とおっしゃるくらいなので、誤差程度にしかマシにならず、やっぱり「ひとりダルマさんが転んだ」状態になるので、「もう買い物を失敗しないように」という教訓として、敢えて捨てずに、わたしの靴箱に置いたままにしてあります。
知人に譲ろうかとも思ったのですが、わたしの足のサイズは21.5cmなので、これを履ける大人はわたしの知人の中に誰一人として居ませんし、低めとは言えヒールがあるので知人の子どもにあげることも不可能!
が、このまま放置していても、せっかくのパンプスがかわいそうなので、横幅だけでなく縦幅も広げられるタイプのシューストレッチャーを近々購入する予定です。
わたしが買い物をミスしていなければ、シューストレッチャーを買うという余計な出費は無かったのに…!
悔しい!
わたしのようなアホはそう居ないでしょうし、まともな人はいくらネットで購入したと言っても「サイズが合わない」と気づいた時点で返品するはずですが、皆さま、靴を購入する際はくれぐれもお気をつけください。
著…chiharu『to the rooms』
2019年12月8日 おすすめの本一覧 コメント (2)
アンティーク調のインテリア本。
わざと古びた感じにした小物と本物のアンティーク家具を組み合わせたり、ランプやシャンデリアによって繊細な光の加減を楽しめる空間を作ったり、わざとムラが出来るように壁の色を塗り重ねて表情を出す、などの方法を学べます。
この本を読んでいると、特に照明によって部屋の雰囲気がガラリと変わることに気づかされます。
わたしは来年の春に引っ越しをするので、出来れば引っ越し先でシャンデリアを使いたいなと考えています。
しかし、「大きな地震が起きたらシャンデリアは危ないのでは…」という不安もあります。
美しさも地震対策も兼ね備えた照明が無いか探してみます。
わざと古びた感じにした小物と本物のアンティーク家具を組み合わせたり、ランプやシャンデリアによって繊細な光の加減を楽しめる空間を作ったり、わざとムラが出来るように壁の色を塗り重ねて表情を出す、などの方法を学べます。
この本を読んでいると、特に照明によって部屋の雰囲気がガラリと変わることに気づかされます。
わたしは来年の春に引っ越しをするので、出来れば引っ越し先でシャンデリアを使いたいなと考えています。
しかし、「大きな地震が起きたらシャンデリアは危ないのでは…」という不安もあります。
美しさも地震対策も兼ね備えた照明が無いか探してみます。
著…信田さよ子『さよなら、お母さん 墓守娘が決断する時』
2019年11月25日 おすすめの本一覧 コメント (2)
過干渉タイプの毒親がいる方におすすめの本。
この本で紹介されているエピソードを通して、「自分の親がいかに異常か」を客観的に見るきっかけになります。
わたしはすぐにこのエピソードに釘付けになりました。
ノリコ(母親)がカオリ(娘)の自立を妨げるために発した、
「反対するのはね、カオリのためなの、すべてはカオリのためなんだから。〜(中略)カオリはママの宝物なのよ、どうして、どうしてなの……わかった、カオリはママを捨てる気なのね」
(P58から抜粋)
という言葉に、「わたしもこれ母親から言われたなぁ…」と、共感というか懐かしいというか苦笑いするしかない気持ちになりました。
このエピソードの場合、ノリコがべっとりと娘に粘着したり、年頃になってメイクに興味を持つというごく自然な成長を見せたことにノリコが「いやらしい」と言い放つなどしたために、カオリはノリコのことを「おかしい」と気づき、ノリコを避けるようになりました。
ノリコはアポ無しでカオリ宅を訪問して、ドアにメモを挟んで行ったり、自分を避けるカオリのことを「誰かに操られている」と思い込んでいたそうです。
わたしも同じ体験をしました。
まるで、溺れている母親にしがみつかれて、自分まで溺れかけているような、あの感覚といったら!
溺れている場合、普通の母親ならば「自分はいいから娘だけでも助かって欲しい」と願うでしょう。
ところが、「自分と娘は固い絆で結ばれているから一緒に溺れるのが当然」と思い込んでいる母親もこの世には存在します。
自分の母親が後者のタイプだと気づいた時の、あのとてつもない生き苦しさといったら!
また、カオリが「私、結婚したい人がいるの。会ってくれない?」と言うと、ノリコが「カオリが結婚するなんて嘘に違いない、そんなことが起きるはずもない」と〝確信〟した…というエピソード、わたしも体験しました。
わたしの場合、毒親あるあるなのですが、30歳を過ぎた社会人であるわたしが「結婚したい人がいるので会って欲しい」と伝えたところ、母親から「せっかく痛い思いをして産んであげたのに、わたしの言うことをきかない。産まなきゃ良かった」「あんたが嫁にいったら親の老後はどうなるの? 親を捨てるんだね。捨てなさい! わたしもあんたを捨てるから!」「〝結婚したら子どもが欲しい〟だなんて、そんないやらしいこと言わないで! 甥っ子と姪っ子が可愛くないの?」「どうしても結婚したいなら、実家と同じ市町村在住で親同士が知っている人でないとダメ」「そんなに結婚がしたいなら、両親を看取ってからでいいでしょ。あと30年後、あんたが60歳くらいになったら2人とも死ぬだろうから。60歳でも結婚する人は居るんだし」「近所の〇〇さんは40過ぎて独身だけど実家で親を介護しながら暮らしてて偉いわ。それなのにあんたは…」「取り柄のないあんたを好きになる人が居るはずない。あんたは騙されている。あんたを嫁に欲しいなんて相手の親もおかしいに違いない」「あんたを殺してわたしも死にたい。でも孫に迷惑がかかる。完全犯罪の方法が知りたい」とマシンガンのように口撃されて、「わたしが悪いのか…。わたしが親不孝なのか…」と自分を責めて悩み苦しみました。
カオリも「自分は人間ではないのか…。鬼ではないのか…」と苦しんだようです。
これって毒親の常套手段なんですよね。
あくまでも「親は被害者」「子どもは加害者」であるかのように子どもを洗脳し、「わたしはあなたのことを愛しているから、あなたのために言っているのよ」というテイで、正常にひとり立ちをしようとする子どもを阻もうとするのって。
カオリはノリコと一線を引く強さを持っているのが素晴らしいです。
カオリが相当な緊張状態の中で必死の努力をして実家に帰省しても、ノリコがまたべっとりと粘着しようとして、カオリに拒絶されたようですが、当たり前ですよね。
ノリコにとって、カオリは「自立して社会生活を送っている大人」ではないのですから。
たぶん一生、「カオリはわたしの可愛い可愛い、わたしの〝一部〟」という認識のままなのですから。
そして、カオリにとって、実家は気の休まるところではなく、ノリコのそばに居ると苦痛なのですから。
それにしても、カオリがノリコに流されずしっかりと自分を奮い立たせていて、その夫にも理解があるのが、本当に良かった。
また、カオリは夫の両親に初めて会った時、夫の両親が良い意味で普通の人たちだったので「いつもあんな風なの?」と心底驚いたそうです。
わたしも彼氏の両親に初めて会った時、そのあまりのまともさに「うちの親と全然違う!」と心底驚いたので、わたしはカオリに様々な点で非常に共感します。
ノリコは、その後、カオリに超長ったらしい手紙を書いたり、「カオリを黒木(カオリの夫)に拉致された」「黒木の親もグル」と妄想を募らせていたそうです。
わたしの母親はノリコにどっぷりと共感するだろうなぁ…。
わたしの母親もノリコみたいに手紙攻撃をしてくるし。
カオリには新しい家庭で幸せになって欲しいし、わたし自身も幸せにならねば、という気持ちで、わたしはこの本を読み終えました。
産んで育ててもらったという点では親に感謝してもし尽くせないけれど、だからといって、たった一度しかない人生を親のために棒に振るなんてナンセンスですよね。
親の希望通りに生きていたら、娘の人生めちゃくちゃ。
この本で紹介されているエピソードを通して、「自分の親がいかに異常か」を客観的に見るきっかけになります。
わたしはすぐにこのエピソードに釘付けになりました。
ノリコ(母親)がカオリ(娘)の自立を妨げるために発した、
「反対するのはね、カオリのためなの、すべてはカオリのためなんだから。〜(中略)カオリはママの宝物なのよ、どうして、どうしてなの……わかった、カオリはママを捨てる気なのね」
(P58から抜粋)
という言葉に、「わたしもこれ母親から言われたなぁ…」と、共感というか懐かしいというか苦笑いするしかない気持ちになりました。
このエピソードの場合、ノリコがべっとりと娘に粘着したり、年頃になってメイクに興味を持つというごく自然な成長を見せたことにノリコが「いやらしい」と言い放つなどしたために、カオリはノリコのことを「おかしい」と気づき、ノリコを避けるようになりました。
ノリコはアポ無しでカオリ宅を訪問して、ドアにメモを挟んで行ったり、自分を避けるカオリのことを「誰かに操られている」と思い込んでいたそうです。
わたしも同じ体験をしました。
まるで、溺れている母親にしがみつかれて、自分まで溺れかけているような、あの感覚といったら!
溺れている場合、普通の母親ならば「自分はいいから娘だけでも助かって欲しい」と願うでしょう。
ところが、「自分と娘は固い絆で結ばれているから一緒に溺れるのが当然」と思い込んでいる母親もこの世には存在します。
自分の母親が後者のタイプだと気づいた時の、あのとてつもない生き苦しさといったら!
また、カオリが「私、結婚したい人がいるの。会ってくれない?」と言うと、ノリコが「カオリが結婚するなんて嘘に違いない、そんなことが起きるはずもない」と〝確信〟した…というエピソード、わたしも体験しました。
わたしの場合、毒親あるあるなのですが、30歳を過ぎた社会人であるわたしが「結婚したい人がいるので会って欲しい」と伝えたところ、母親から「せっかく痛い思いをして産んであげたのに、わたしの言うことをきかない。産まなきゃ良かった」「あんたが嫁にいったら親の老後はどうなるの? 親を捨てるんだね。捨てなさい! わたしもあんたを捨てるから!」「〝結婚したら子どもが欲しい〟だなんて、そんないやらしいこと言わないで! 甥っ子と姪っ子が可愛くないの?」「どうしても結婚したいなら、実家と同じ市町村在住で親同士が知っている人でないとダメ」「そんなに結婚がしたいなら、両親を看取ってからでいいでしょ。あと30年後、あんたが60歳くらいになったら2人とも死ぬだろうから。60歳でも結婚する人は居るんだし」「近所の〇〇さんは40過ぎて独身だけど実家で親を介護しながら暮らしてて偉いわ。それなのにあんたは…」「取り柄のないあんたを好きになる人が居るはずない。あんたは騙されている。あんたを嫁に欲しいなんて相手の親もおかしいに違いない」「あんたを殺してわたしも死にたい。でも孫に迷惑がかかる。完全犯罪の方法が知りたい」とマシンガンのように口撃されて、「わたしが悪いのか…。わたしが親不孝なのか…」と自分を責めて悩み苦しみました。
カオリも「自分は人間ではないのか…。鬼ではないのか…」と苦しんだようです。
これって毒親の常套手段なんですよね。
あくまでも「親は被害者」「子どもは加害者」であるかのように子どもを洗脳し、「わたしはあなたのことを愛しているから、あなたのために言っているのよ」というテイで、正常にひとり立ちをしようとする子どもを阻もうとするのって。
カオリはノリコと一線を引く強さを持っているのが素晴らしいです。
カオリが相当な緊張状態の中で必死の努力をして実家に帰省しても、ノリコがまたべっとりと粘着しようとして、カオリに拒絶されたようですが、当たり前ですよね。
ノリコにとって、カオリは「自立して社会生活を送っている大人」ではないのですから。
たぶん一生、「カオリはわたしの可愛い可愛い、わたしの〝一部〟」という認識のままなのですから。
そして、カオリにとって、実家は気の休まるところではなく、ノリコのそばに居ると苦痛なのですから。
それにしても、カオリがノリコに流されずしっかりと自分を奮い立たせていて、その夫にも理解があるのが、本当に良かった。
また、カオリは夫の両親に初めて会った時、夫の両親が良い意味で普通の人たちだったので「いつもあんな風なの?」と心底驚いたそうです。
わたしも彼氏の両親に初めて会った時、そのあまりのまともさに「うちの親と全然違う!」と心底驚いたので、わたしはカオリに様々な点で非常に共感します。
ノリコは、その後、カオリに超長ったらしい手紙を書いたり、「カオリを黒木(カオリの夫)に拉致された」「黒木の親もグル」と妄想を募らせていたそうです。
わたしの母親はノリコにどっぷりと共感するだろうなぁ…。
わたしの母親もノリコみたいに手紙攻撃をしてくるし。
カオリには新しい家庭で幸せになって欲しいし、わたし自身も幸せにならねば、という気持ちで、わたしはこの本を読み終えました。
産んで育ててもらったという点では親に感謝してもし尽くせないけれど、だからといって、たった一度しかない人生を親のために棒に振るなんてナンセンスですよね。
親の希望通りに生きていたら、娘の人生めちゃくちゃ。
編著…暮らしの図鑑編集部『うつわ 楽しむ工夫×注目作家55人×基礎知識』
2019年11月15日 おすすめの本一覧
フルカラー写真を非常に多く使った贅沢な本。
可愛いうつわも、渋いうつわも、綺麗なうつわも、豊富に紹介されています。
ページを捲っているだけでも楽しいし、好みのうつわが見つかります。
特に、うつわを洋服に例えて説明してくれるのが、とても分かりやすいです。
無地のうつわは、無地の洋服。
染付や色絵のうつわは、柄物の洋服。
うつわに磁器・陶器・ガラス・木・漆といった様々な素材があるように、洋服にも麻・コットン・シルク・ウールといった様々な素材があります。
洋服をコーディネートする時TPOや季節感を考えて組み合わせるのと同じように、うつわもまた、料理との相性や季節感を踏まえてコーディネート出来たら楽しいんだな、と気づかせてもらいました。
可愛いうつわも、渋いうつわも、綺麗なうつわも、豊富に紹介されています。
ページを捲っているだけでも楽しいし、好みのうつわが見つかります。
特に、うつわを洋服に例えて説明してくれるのが、とても分かりやすいです。
無地のうつわは、無地の洋服。
染付や色絵のうつわは、柄物の洋服。
うつわに磁器・陶器・ガラス・木・漆といった様々な素材があるように、洋服にも麻・コットン・シルク・ウールといった様々な素材があります。
洋服をコーディネートする時TPOや季節感を考えて組み合わせるのと同じように、うつわもまた、料理との相性や季節感を踏まえてコーディネート出来たら楽しいんだな、と気づかせてもらいました。
普段は特に意識していなくても、法はわたしたちの生活に深く根差しています。
例えば、コンビニでおにぎりを買う時「売買契約」が結ばれます。
買主(客)にはおにぎりを手に入れる権利とお金を払う義務が発生し、売主(店)にはお金を貰う権利とおにぎりを渡す義務が発生します。
もし法が無ければ、誰もが法によって自由を制限されることは無くなりますが、法によって守られることも無くなるので、治安は最悪になるでしょう。
この本は、様々な「法」が果たしている役割を、13歳の読者へ向けて分かりやすく教えてくれる本です。
「〝付き合う〟と〝結婚〟って何が違うの?」「〝いじめ〟って犯罪なの?」「インスタにウソの投稿をしたらどうなるの?」「バイト中の悪ふざけをネットにアップしたらどうなるの?」といった想像しやすいエピソードを使って教えてくれるので、子どもだけでなく大人にもおすすめ。
例えば、コンビニでおにぎりを買う時「売買契約」が結ばれます。
買主(客)にはおにぎりを手に入れる権利とお金を払う義務が発生し、売主(店)にはお金を貰う権利とおにぎりを渡す義務が発生します。
もし法が無ければ、誰もが法によって自由を制限されることは無くなりますが、法によって守られることも無くなるので、治安は最悪になるでしょう。
この本は、様々な「法」が果たしている役割を、13歳の読者へ向けて分かりやすく教えてくれる本です。
「〝付き合う〟と〝結婚〟って何が違うの?」「〝いじめ〟って犯罪なの?」「インスタにウソの投稿をしたらどうなるの?」「バイト中の悪ふざけをネットにアップしたらどうなるの?」といった想像しやすいエピソードを使って教えてくれるので、子どもだけでなく大人にもおすすめ。
監修…遠藤隆夫『ラグビー・ゲーム&プレー』
2019年11月2日 おすすめの本一覧
「ラグビーワールドカップ2019」開催中、わたしはテレビの前で、この本を片手に「走れー!走れ走れ走れー!」と叫んで選手たちを応援していました。
「スクラム」「キックオフ」「ラインアウト」といったプレー用語、ルール、審判のジェスチャーの意味、「プロップ」「フッカー」「スクラムハーフ」といったポジションごとの役割など、ラグビーの基礎知識を学べる本です。
2009年に発行されたこの本には、
「ワールドカップ初の日本開催も遠い未来のことではなさそうだ」
(P114から抜粋)
と書かれています。
その10年後に、日本でワールドカップが開催され、日本もベスト8まで勝ち進んだことを、2009年にこの本の発行に携わった人たちに、タイムマシンで教えに行きたいです。
また、P31に掲載されている「ノーサイド」の解説が特に分かりやすかったです。
今年のワールドカップの決勝でも、日本の解説者が試合終了後に「ノーサイドー!」と叫んでいたのが非常に印象的でした。
試合が終了したら敵味方の味方は無くなり、ラガーマンとして皆が一つになる。
かっこいい言葉ですね!
「スクラム」「キックオフ」「ラインアウト」といったプレー用語、ルール、審判のジェスチャーの意味、「プロップ」「フッカー」「スクラムハーフ」といったポジションごとの役割など、ラグビーの基礎知識を学べる本です。
2009年に発行されたこの本には、
「ワールドカップ初の日本開催も遠い未来のことではなさそうだ」
(P114から抜粋)
と書かれています。
その10年後に、日本でワールドカップが開催され、日本もベスト8まで勝ち進んだことを、2009年にこの本の発行に携わった人たちに、タイムマシンで教えに行きたいです。
また、P31に掲載されている「ノーサイド」の解説が特に分かりやすかったです。
今年のワールドカップの決勝でも、日本の解説者が試合終了後に「ノーサイドー!」と叫んでいたのが非常に印象的でした。
試合が終了したら敵味方の味方は無くなり、ラガーマンとして皆が一つになる。
かっこいい言葉ですね!
監修…徳田竜之介『どんな災害でもネコといっしょ』
2019年10月29日 おすすめの本一覧
被災して、飼い主とペットが離れ離れになると、お互いに辛い思いをすることになります。
しかし、ペットに対して良い感情を持っていない人や、アレルギーを持つ人も居るため、同じ避難所で受け入れてもらうのはなかなか難しい現状があります。
この本は、災害時に飼い主とペット両方が安心して避難生活を送るため、飼い主が普段から「もしも」に備えて行っておくべきことをまとめた本です。
犬の飼い主向けに書かれた別の本もあるようですが、これは猫の飼い主向けに書かれた本。
実際に東日本大震災や熊本地震で猫と一緒に被災した方々の体験談も載っているので、実践的なアイディアを学べます。
例えば、主なアイディアは、
・猫が迷子になっても必ず再会出来るように、身元が分かる物を猫に身につけさせておき、探しやすくなるように猫の写真も用意しておく
・単なる移動手段としてだけではなく、避難場所としても使えるように、日頃から猫をキャリーバッグに慣らしておく
・最低でも3日分の、普段から慣れているキャットフード、薬、飲料水、猫砂、猫用食器などを非常持ち出し袋に入れておく
・猫にワクチンの接種、ノミ・ダニの予防、定期的な健康診断を受けさせておく
・猫にトイレのしつけをしておく
・ペット同行可の避難訓練に猫と一緒に参加して、いざという時のシミュレーションを行う
・猫が出血や骨折などをした際の応急処置について飼い主が学んでおく
・猫が避難所でパニックにならないように、飼い主以外の人間や他の生き物に慣れさせておく
といったもの。
こうしたアイディアを紹介する中で、特に強調されているのは、「飼い主が無事でなければ猫の命を守ることは出来ないので、自分の身の安全を確保することを忘れないこと」。
意外と、これが盲点になりがちですよね。
自分のことより猫のことを最優先に考えてしまいがちですから。
それについてはわたしも身近な事例を知っています。
わたしの友人は熊本地震の際に、「猫が他の人間や生き物を怖がるから」「他人に頼るのは嫌」と言って、避難所へ行くことも、わたしを含めた友人たちの家や親族の家へ一時避難することも嫌がり、猫と一緒に軽自動車の中で車中泊を何日も続けた結果、エコノミー症候群になりかけましたし、猫もいつもと違う環境がストレスとなり持病が悪化しかけました。
「猫のために」と思って行ったはずのことが、飼い主にとっても猫にとっても良くない事態を招きました。
ただ、友人が悪いとは言い切れません。
友人の場合は「避難所に行ったら女性は性被害にあう」という不安も感じていたため避難所に行きたくても行けない事情もあったからです。
もし友人が日頃から猫を飼い主以外の人や生き物に慣れさせていたら少しは違う結果になったのかもしれませんし、「他人に頼るのは嫌だ」と意地を張らずに避難して他の人に頼るということも選択肢の1つに入れておくべきだったのでしょうし、そもそも「避難所は安全だ」と言い切れる安心感があれば良かったのに…と思います。
同じようなことを繰り返さないために、日頃から人間・ペット両方のためになる災害対策を行っていきたいです。
しかし、ペットに対して良い感情を持っていない人や、アレルギーを持つ人も居るため、同じ避難所で受け入れてもらうのはなかなか難しい現状があります。
この本は、災害時に飼い主とペット両方が安心して避難生活を送るため、飼い主が普段から「もしも」に備えて行っておくべきことをまとめた本です。
犬の飼い主向けに書かれた別の本もあるようですが、これは猫の飼い主向けに書かれた本。
実際に東日本大震災や熊本地震で猫と一緒に被災した方々の体験談も載っているので、実践的なアイディアを学べます。
例えば、主なアイディアは、
・猫が迷子になっても必ず再会出来るように、身元が分かる物を猫に身につけさせておき、探しやすくなるように猫の写真も用意しておく
・単なる移動手段としてだけではなく、避難場所としても使えるように、日頃から猫をキャリーバッグに慣らしておく
・最低でも3日分の、普段から慣れているキャットフード、薬、飲料水、猫砂、猫用食器などを非常持ち出し袋に入れておく
・猫にワクチンの接種、ノミ・ダニの予防、定期的な健康診断を受けさせておく
・猫にトイレのしつけをしておく
・ペット同行可の避難訓練に猫と一緒に参加して、いざという時のシミュレーションを行う
・猫が出血や骨折などをした際の応急処置について飼い主が学んでおく
・猫が避難所でパニックにならないように、飼い主以外の人間や他の生き物に慣れさせておく
といったもの。
こうしたアイディアを紹介する中で、特に強調されているのは、「飼い主が無事でなければ猫の命を守ることは出来ないので、自分の身の安全を確保することを忘れないこと」。
意外と、これが盲点になりがちですよね。
自分のことより猫のことを最優先に考えてしまいがちですから。
それについてはわたしも身近な事例を知っています。
わたしの友人は熊本地震の際に、「猫が他の人間や生き物を怖がるから」「他人に頼るのは嫌」と言って、避難所へ行くことも、わたしを含めた友人たちの家や親族の家へ一時避難することも嫌がり、猫と一緒に軽自動車の中で車中泊を何日も続けた結果、エコノミー症候群になりかけましたし、猫もいつもと違う環境がストレスとなり持病が悪化しかけました。
「猫のために」と思って行ったはずのことが、飼い主にとっても猫にとっても良くない事態を招きました。
ただ、友人が悪いとは言い切れません。
友人の場合は「避難所に行ったら女性は性被害にあう」という不安も感じていたため避難所に行きたくても行けない事情もあったからです。
もし友人が日頃から猫を飼い主以外の人や生き物に慣れさせていたら少しは違う結果になったのかもしれませんし、「他人に頼るのは嫌だ」と意地を張らずに避難して他の人に頼るということも選択肢の1つに入れておくべきだったのでしょうし、そもそも「避難所は安全だ」と言い切れる安心感があれば良かったのに…と思います。
同じようなことを繰り返さないために、日頃から人間・ペット両方のためになる災害対策を行っていきたいです。
著…渡邉由『顔診断で不調を治す・防ぐ』
2019年10月13日 おすすめの本一覧
吹出物もホクロもシミも、意味なく出てくるわけではないので、顔の状態を見れば体のどこが弱っているか分かる、という本。
例えば、目の下のクマ。
東洋医学において「青」の病変は肝の不調と捉えられており、青っぽいクマが出ている時は肝臓や胆のうが弱っている時だそうです。
また、「黒」の病変は腎の不調と捉えられており、黒っぽいクマが出ている時は腎臓が弱っているのだそう。
目の下の皮膚は薄いので、血液がどんな状態なのか読み取りやすいそうです。
あくまでも「目安」であって、精密検査をするわけではないので、「体の〜が〜の状態だから〜の病気だ」と断言することは出来ません。
しかし、それでも、「目安」となる知識があれば、自分自身の体調を把握出来るだけでなく、周りの人の体調不良にいち早く気づけると思いますので、わたしもこうした知識を身につけていきたいです。
例えば、目の下のクマ。
東洋医学において「青」の病変は肝の不調と捉えられており、青っぽいクマが出ている時は肝臓や胆のうが弱っている時だそうです。
また、「黒」の病変は腎の不調と捉えられており、黒っぽいクマが出ている時は腎臓が弱っているのだそう。
目の下の皮膚は薄いので、血液がどんな状態なのか読み取りやすいそうです。
あくまでも「目安」であって、精密検査をするわけではないので、「体の〜が〜の状態だから〜の病気だ」と断言することは出来ません。
しかし、それでも、「目安」となる知識があれば、自分自身の体調を把握出来るだけでなく、周りの人の体調不良にいち早く気づけると思いますので、わたしもこうした知識を身につけていきたいです。
著…大谷憲『薬を使わずにぐっすり眠る方法』
2019年10月6日 おすすめの本一覧 コメント (2)
ぐっすり眠る方法や、すっきり起きる方法について、イラストを豊富に使って分かりやすくまとめた本。
一言で「睡眠障害」と言っても、「中途覚醒タイプ」「入眠障害タイプ」「熟眠障害タイプ」「早朝覚醒タイプ」など様々なものがあり、それぞれ症状も要因も異なるので、むやみに睡眠薬に頼らず、生活習慣などを見直すことが大切だと気付かされます。
すっきり起きるためのアイディアとして、
「寝室のカーテンを閉め切らずに10センチだけ開けて眠ることで、朝日が室内に差し込んできて、自然なかたちで明るくなり、目覚めを促してくれる」
「就寝前は暖色系の照明で過ごす」
「平日、休日に関わらず、同じ時刻に起きるようにする」
といったものが紹介されています。
わたしもこの三つについてはここ数年間実践しており、確かに目覚めが良くなったのでおすすめです。
一言で「睡眠障害」と言っても、「中途覚醒タイプ」「入眠障害タイプ」「熟眠障害タイプ」「早朝覚醒タイプ」など様々なものがあり、それぞれ症状も要因も異なるので、むやみに睡眠薬に頼らず、生活習慣などを見直すことが大切だと気付かされます。
すっきり起きるためのアイディアとして、
「寝室のカーテンを閉め切らずに10センチだけ開けて眠ることで、朝日が室内に差し込んできて、自然なかたちで明るくなり、目覚めを促してくれる」
「就寝前は暖色系の照明で過ごす」
「平日、休日に関わらず、同じ時刻に起きるようにする」
といったものが紹介されています。
わたしもこの三つについてはここ数年間実践しており、確かに目覚めが良くなったのでおすすめです。
著…中山和彦、小野和哉『図解 よくわかる思春期の発達障害』
2019年8月20日 おすすめの本一覧
発達障害があることが周りの人に理解されず、適切なサポートを受けられないまま思春期を迎えてしまうと、「変わっている」「扱いにくい」と孤立しがち。
非難されたり叱責されて傷つき、発達障害だけでなく、うつ病などの心の病も重なってしまう…。
そんなことにならないように、この本は、発達障害と他の障害との違い、治療方法、思春期に陥りがちな状況別の対応方法を紹介しています。
発達障害の有無や、年齢や性別も関係なく、何だか生き辛い、という方にもおすすめです。
この本で紹介されている、「友だちの輪に入れない」「努力しても成績が上がらない」「いじめがひどくなって学校に行くのが怖い」といった悩みは、発達障害がある子だけでなく、多かれ少なかれ誰もが抱えている悩みだから。
苦しんでいるのは自分だけじゃない、一人で抱え込まなくていいんだ、と思えてきます。
非難されたり叱責されて傷つき、発達障害だけでなく、うつ病などの心の病も重なってしまう…。
そんなことにならないように、この本は、発達障害と他の障害との違い、治療方法、思春期に陥りがちな状況別の対応方法を紹介しています。
発達障害の有無や、年齢や性別も関係なく、何だか生き辛い、という方にもおすすめです。
この本で紹介されている、「友だちの輪に入れない」「努力しても成績が上がらない」「いじめがひどくなって学校に行くのが怖い」といった悩みは、発達障害がある子だけでなく、多かれ少なかれ誰もが抱えている悩みだから。
苦しんでいるのは自分だけじゃない、一人で抱え込まなくていいんだ、と思えてきます。
著…蛯原友里『きれいになるハーブ おしゃれに暮らす幸せレシピ』
2019年7月22日 おすすめの本一覧
お花が描かれたティーカップ&ソーサー、キラキラ輝くガラスのグラス、アンティーク風の砂時計、ヨーロッパ調のトレイ。
水を飲むだけでも優雅な気持ちになれそうなアイテムを使い、色とりどりのハーブを濾して、色や香りを楽しみながらゆっくり味わう…。
そんな贅沢な時間を過ごしたい人におすすめの本。
どのページを開いても「可愛い!」と思われるよう、写真も文字も色もこだわり抜いて作られた本ですが、
「デトックスをしたいなら」「白い肌を目指したい」「心を穏やかに鎮めたいとき」「ぐっすりと質のよい睡眠を」「風邪気味かな…と感じたら」といった、目的別の茶葉の組み合わせと分量、
ハーブを使ったサラダ、スープ、メインディッシュ、デザート、カクテルといったレシピも紹介されているので、
可愛いだけではなく実用的な本です。
水を飲むだけでも優雅な気持ちになれそうなアイテムを使い、色とりどりのハーブを濾して、色や香りを楽しみながらゆっくり味わう…。
そんな贅沢な時間を過ごしたい人におすすめの本。
どのページを開いても「可愛い!」と思われるよう、写真も文字も色もこだわり抜いて作られた本ですが、
「デトックスをしたいなら」「白い肌を目指したい」「心を穏やかに鎮めたいとき」「ぐっすりと質のよい睡眠を」「風邪気味かな…と感じたら」といった、目的別の茶葉の組み合わせと分量、
ハーブを使ったサラダ、スープ、メインディッシュ、デザート、カクテルといったレシピも紹介されているので、
可愛いだけではなく実用的な本です。
著…濱田秀彦『「年上の部下」をもったら読む本』
2019年7月16日 おすすめの本一覧
「定年退職後はのんびりと年金生活をしながら趣味を楽しみますよ」なんて言えたのはもはや過去の話。
消費税は上がるし、年金制度がどうなるか分からないので、よほど蓄えがある人でない限り、年齢に関係なく働き続けざるを得ないのが今の世の中。
これまでとは違う職場へ行く年配の方や、今までと同じ職場には居るけれど役職を退いて一般社員に戻る年配の方も多いです。
だから、「自分より年上の部下が出来た」と悩む人や、逆に「自分より年下の上司のもとで働くことになった」と悩む人はこの先どんどん増えていきそう。
仕事の場なんだから年齢に関係なく上司は部下を堂々と指導すればいい、と思いがちですが、なかなかそうも割り切れないのが人の心。
「自分の親と同じ、いや、下手したら自分の親より上の世代の人を指導出来るのか?」と悩んでいる人に、この本はおすすめです。
年上の部下のプライドに配慮しつつ仕事をきちんとしてもらうための、指示の出し方、やる気の引き出し方、職場に溶け込ませる方法、注意の仕方、スキルや経験の活かし方が書かれています。
わたし自身も年上の部下たちと仕事をしており、悩むことが多いので、参考になりました。
特に、年上の部下の居場所を作るには飲み会を開くことよりも遠慮せずにどんどん仕事を与えることだ、そうすれば職場に溶け込む、という記述に共感。
消費税は上がるし、年金制度がどうなるか分からないので、よほど蓄えがある人でない限り、年齢に関係なく働き続けざるを得ないのが今の世の中。
これまでとは違う職場へ行く年配の方や、今までと同じ職場には居るけれど役職を退いて一般社員に戻る年配の方も多いです。
だから、「自分より年上の部下が出来た」と悩む人や、逆に「自分より年下の上司のもとで働くことになった」と悩む人はこの先どんどん増えていきそう。
仕事の場なんだから年齢に関係なく上司は部下を堂々と指導すればいい、と思いがちですが、なかなかそうも割り切れないのが人の心。
「自分の親と同じ、いや、下手したら自分の親より上の世代の人を指導出来るのか?」と悩んでいる人に、この本はおすすめです。
年上の部下のプライドに配慮しつつ仕事をきちんとしてもらうための、指示の出し方、やる気の引き出し方、職場に溶け込ませる方法、注意の仕方、スキルや経験の活かし方が書かれています。
わたし自身も年上の部下たちと仕事をしており、悩むことが多いので、参考になりました。
特に、年上の部下の居場所を作るには飲み会を開くことよりも遠慮せずにどんどん仕事を与えることだ、そうすれば職場に溶け込む、という記述に共感。
著…地曳いく子『服を買うなら、捨てなさい』
2019年7月13日 おすすめの本一覧
おしゃれな人=沢山の服を持っていたり、高価な服を持っている人、ではない。
おしゃれな人=自分を美しく見せる服を自分で管理出来る量だけ持っている人。自分が何にときめくか知っている人。自分のスタイルがある人。
という内容の本。
「流行は繰り返す」というけれど、次に流行る時は素材やシルエットが昔のものとは微妙に違っているので、昔流行った服を着ても古臭くて「今」にフィットしない、
何となく服を「買い足す」より、少数精鋭のお気に入りを「買い替え」しましょう、
ということも書かれているので、わたしも早速タンスの中身を整理しました。
おしゃれな人=自分を美しく見せる服を自分で管理出来る量だけ持っている人。自分が何にときめくか知っている人。自分のスタイルがある人。
という内容の本。
「流行は繰り返す」というけれど、次に流行る時は素材やシルエットが昔のものとは微妙に違っているので、昔流行った服を着ても古臭くて「今」にフィットしない、
何となく服を「買い足す」より、少数精鋭のお気に入りを「買い替え」しましょう、
ということも書かれているので、わたしも早速タンスの中身を整理しました。