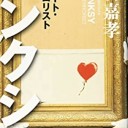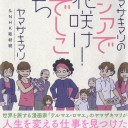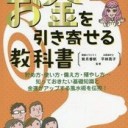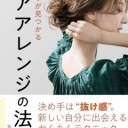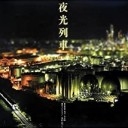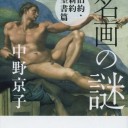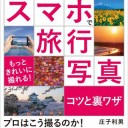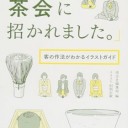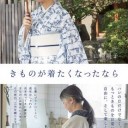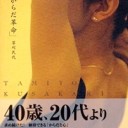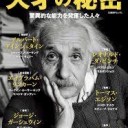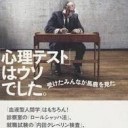著…藤田孝典『コロナ貧困 絶望的格差社会の襲来』
2021年8月16日 おすすめの本一覧
社会福祉士として働く著者がコロナ禍で貧困に苦しむ方たちの事例を紹介する本。
誰がいつ貧困に陥ってもおかしくないのだ、ということを気付かせてくれます。
コロナ禍以前から貧困問題は誰にとっても他人事ではなかったのですが、「自己責任」とされることが多かったように思います。
ところが、これまでギリギリのラインで生活を持ちこたえていた方がコロナ禍を機にとうとう限界に達したり、ごく普通に暮らしていた方がコロナ禍で初めて我が身のこととして貧困を経験するようになりましたよね…。
本当に未曾有の危機…。
コロナそのもので命を落とさなくても、経済的理由から自殺を考える人、残念ながら実際に命を絶ってしまった方たちも多いですよね…。
世の中には、お金に困っている方や生活保護受給者を馬鹿にする方もいまだにいますが…、そういう方にこういった本を読んでいただき、明日は我が身、個人的努力ではどうにもならない事態が誰にでも突然起こり得ること、不正受給者が悪いのであって生活保護そのものは悪くないこと、貧困は社会全体の問題だと知っていただきたいです。
誰がいつ貧困に陥ってもおかしくないのだ、ということを気付かせてくれます。
コロナ禍以前から貧困問題は誰にとっても他人事ではなかったのですが、「自己責任」とされることが多かったように思います。
ところが、これまでギリギリのラインで生活を持ちこたえていた方がコロナ禍を機にとうとう限界に達したり、ごく普通に暮らしていた方がコロナ禍で初めて我が身のこととして貧困を経験するようになりましたよね…。
本当に未曾有の危機…。
コロナそのもので命を落とさなくても、経済的理由から自殺を考える人、残念ながら実際に命を絶ってしまった方たちも多いですよね…。
世の中には、お金に困っている方や生活保護受給者を馬鹿にする方もいまだにいますが…、そういう方にこういった本を読んでいただき、明日は我が身、個人的努力ではどうにもならない事態が誰にでも突然起こり得ること、不正受給者が悪いのであって生活保護そのものは悪くないこと、貧困は社会全体の問題だと知っていただきたいです。
著…毛利嘉孝『バンクシー アート・テロリスト』
2020年9月15日 おすすめの本一覧
ステンシルの手法、各作品についての解説、サザビーズでのシュレッダー事件、ミュージアムでの無断展示事件、バンクシーの正体ではないか?と噂されている人たちのことなど、バンクシーにまつわる様々なことが書かれている本。
特に、バンクシーがやっていることは落書きなのか? アートなのか? という点について考えさせられます。
アートならば犯罪ではないのか?
表現の自由はどこまで許されるのか?
また、バンクシー風の落書きが日本国内で次々と見つかり、「これは本物のバンクシーなのか」「本物なら消したらまずいのだろうか」「本物だったらいくらくらいするのだろうか」と人々がざわついたことについてもこの本は触れています。
悩ましい問題ですよね。
わたしは、反戦、パレスチナ問題、難民問題、反資本主義といったテーマ性の強いバンクシーの作品が好きなので、「うちの家の壁にもバンクシーが絵を描いてくれないかなぁ」と胸をときめかせることもあります。
しかし、バンクシーのファンではない人なら「よくも落書きしやがって!」と腹が立って即刻消すでしょうし、バンクシーに損害賠償請求をしたくなるでしょうね。
しかしそうやって物議を醸すことこそがバンクシーの狙いなのかもしれません。
単に綺麗なものだけを描く芸術だけでは無く、爆弾や銃や遺体といった生々しい現実を描くことで人々の注目を集め、人々に平和について考えさせようという意図があるのかも。
特に、バンクシーがやっていることは落書きなのか? アートなのか? という点について考えさせられます。
アートならば犯罪ではないのか?
表現の自由はどこまで許されるのか?
また、バンクシー風の落書きが日本国内で次々と見つかり、「これは本物のバンクシーなのか」「本物なら消したらまずいのだろうか」「本物だったらいくらくらいするのだろうか」と人々がざわついたことについてもこの本は触れています。
悩ましい問題ですよね。
わたしは、反戦、パレスチナ問題、難民問題、反資本主義といったテーマ性の強いバンクシーの作品が好きなので、「うちの家の壁にもバンクシーが絵を描いてくれないかなぁ」と胸をときめかせることもあります。
しかし、バンクシーのファンではない人なら「よくも落書きしやがって!」と腹が立って即刻消すでしょうし、バンクシーに損害賠償請求をしたくなるでしょうね。
しかしそうやって物議を醸すことこそがバンクシーの狙いなのかもしれません。
単に綺麗なものだけを描く芸術だけでは無く、爆弾や銃や遺体といった生々しい現実を描くことで人々の注目を集め、人々に平和について考えさせようという意図があるのかも。
著…木谷卓哉『タクシー運転手のご縁を味わう日常 一期一会の物語』
2020年9月14日 おすすめの本一覧 コメント (2)
タクシー内で起きたちょっと心温まるエピソードやハプニングなどを紹介しているKindle本。
お客目線で書かれたものは時々ありますが、タクシー運転手側の目線で書かれたものはなかなか見かけないのでユニークだと思います。
著者が自らを「素人」と言っている通り、確かにプロ作家のように巧みな文章表現が使われているわけではありませんが、その分、嘘偽りない素直な運転手側の心境を読めて好印象。
改めて考えると、タクシーって乗る側にとっても乗せる側にとっても独特の体験だよなあ、とわたしはこの本を読んでいて気づかされました。
沢山あるタクシーの中から、たまたま一台のタクシーにお客が乗りこんで来るのって、まさに一期一会。
どこをいつ通るかあらかじめ決められているバスや電車とは違って、タクシーの行き先はバラバラ。
運転手も人それぞれ。
お客も人それぞれ。
世間話をしたいお客。
観光案内をして欲しいお客。
「この辺り、警察取り締まりしてないから、もっとスピード出せよ!」と無茶な文句を言ってくるお客。
暴れるお客。
「新人の腕章をしてたら絡んでくる人が多いやろうから、外したらいいのに」と心配してくれるお客。
重たい人生相談をしたいお客。
…色んなお客がいるんですね…。
タクシーって密室なので、良くも悪くも自分の素が出ちゃう空間なんでしょうね…。
わたしも少なくとも、筋違いの文句を言ったり暴れるお客にならないように気をつけます。
タクシーに乗せてくれる人がいるからこそタクシーに乗れるわけですし、お互いに気持ち良く利用したいです。
理不尽なクレームをつけたり、暴れるなんて最低。
また、タクシーに限らないことですが「お客様は神様だろう」なんて傲慢な態度をお客の側が取ったらいけませんよね。
神様ではなく人間なのですから。
もしそのお客が人間に見えるけれど実は神様だとしたら、きっと貧乏神か疫病神なのでしょうから、永久に乗車拒否されるべし。
お客目線で書かれたものは時々ありますが、タクシー運転手側の目線で書かれたものはなかなか見かけないのでユニークだと思います。
著者が自らを「素人」と言っている通り、確かにプロ作家のように巧みな文章表現が使われているわけではありませんが、その分、嘘偽りない素直な運転手側の心境を読めて好印象。
改めて考えると、タクシーって乗る側にとっても乗せる側にとっても独特の体験だよなあ、とわたしはこの本を読んでいて気づかされました。
沢山あるタクシーの中から、たまたま一台のタクシーにお客が乗りこんで来るのって、まさに一期一会。
どこをいつ通るかあらかじめ決められているバスや電車とは違って、タクシーの行き先はバラバラ。
運転手も人それぞれ。
お客も人それぞれ。
世間話をしたいお客。
観光案内をして欲しいお客。
「この辺り、警察取り締まりしてないから、もっとスピード出せよ!」と無茶な文句を言ってくるお客。
暴れるお客。
「新人の腕章をしてたら絡んでくる人が多いやろうから、外したらいいのに」と心配してくれるお客。
重たい人生相談をしたいお客。
…色んなお客がいるんですね…。
タクシーって密室なので、良くも悪くも自分の素が出ちゃう空間なんでしょうね…。
わたしも少なくとも、筋違いの文句を言ったり暴れるお客にならないように気をつけます。
タクシーに乗せてくれる人がいるからこそタクシーに乗れるわけですし、お互いに気持ち良く利用したいです。
理不尽なクレームをつけたり、暴れるなんて最低。
また、タクシーに限らないことですが「お客様は神様だろう」なんて傲慢な態度をお客の側が取ったらいけませんよね。
神様ではなく人間なのですから。
もしそのお客が人間に見えるけれど実は神様だとしたら、きっと貧乏神か疫病神なのでしょうから、永久に乗車拒否されるべし。
カンボジアの話が特に印象的です。
ポル・ポト政権が「農業以外のことは不要である」として、農業以外のことに携わる人たちを徹底的に処刑しました。
音楽を奏でたり、歌ったり、踊ったりしただけで、激しい拷問をされたり殺されていたのだそうです。
今の日本なら、音楽は誰もが気軽に楽しめるものですよね。
でも、時代や国によってはそうじゃ無い…。
当たり前だと思い込んでいることって実はとても貴重なことなんだ、と気づかされます。
これはポル・ポト政権が行っていた残虐行為のうちのほんの一部で、ここには書ききれないほど多くの恐ろしいことをやっていたので、興味がある方は調べてください。
この本の主人公は外国で働く日本人女性なのですが、そのポル・ポト政権時代の壮絶な日々を生き抜いたカンボジアの大人たちや、これからの未来を作っていく子どもたちの姿も紹介されていて、希望が伝わってきました。
「音楽は世界の共通のことばです! これを知っていれば世界中の人と仲良くなれるよ」
(P39から抜粋)
と子どもたちに音楽を教える浦田さんという女性の言葉も素敵ですし、
ヤマザキさんが子どもたちと一緒に地面に絵を描いて、
「音楽もだけど、絵も世界の共通言語ですよね」
(P50から抜粋)
と考えているのも素敵!
そう、芸術って世界共通の言語なんですよね。
たとえ言葉が通じなくても、悲しい歌を歌えば悲しい気持ちが伝わるし、楽しそうな絵を描けば楽しい気持ちが伝わります。
芸術を禁止するというのは、人と人との心の通い合いを禁止するということ。
ポル・ポト政権は国民から芸術を奪うことによって国民を恐怖のみによって支配し、意に沿わない国民を殺し尽くそうとしたのでしょうね…。
恐ろしい…。
日本もそういう危険な政治が行われないように国民一人ひとりが気をつけて政治家たちの動きを見ていないといけませんね。
ポル・ポト政権が「農業以外のことは不要である」として、農業以外のことに携わる人たちを徹底的に処刑しました。
音楽を奏でたり、歌ったり、踊ったりしただけで、激しい拷問をされたり殺されていたのだそうです。
今の日本なら、音楽は誰もが気軽に楽しめるものですよね。
でも、時代や国によってはそうじゃ無い…。
当たり前だと思い込んでいることって実はとても貴重なことなんだ、と気づかされます。
これはポル・ポト政権が行っていた残虐行為のうちのほんの一部で、ここには書ききれないほど多くの恐ろしいことをやっていたので、興味がある方は調べてください。
この本の主人公は外国で働く日本人女性なのですが、そのポル・ポト政権時代の壮絶な日々を生き抜いたカンボジアの大人たちや、これからの未来を作っていく子どもたちの姿も紹介されていて、希望が伝わってきました。
「音楽は世界の共通のことばです! これを知っていれば世界中の人と仲良くなれるよ」
(P39から抜粋)
と子どもたちに音楽を教える浦田さんという女性の言葉も素敵ですし、
ヤマザキさんが子どもたちと一緒に地面に絵を描いて、
「音楽もだけど、絵も世界の共通言語ですよね」
(P50から抜粋)
と考えているのも素敵!
そう、芸術って世界共通の言語なんですよね。
たとえ言葉が通じなくても、悲しい歌を歌えば悲しい気持ちが伝わるし、楽しそうな絵を描けば楽しい気持ちが伝わります。
芸術を禁止するというのは、人と人との心の通い合いを禁止するということ。
ポル・ポト政権は国民から芸術を奪うことによって国民を恐怖のみによって支配し、意に沿わない国民を殺し尽くそうとしたのでしょうね…。
恐ろしい…。
日本もそういう危険な政治が行われないように国民一人ひとりが気をつけて政治家たちの動きを見ていないといけませんね。
著…柊木マキ『女王学のススメ 親の愛は汚れている』
2020年7月18日 おすすめの本一覧
親の呪縛から自由になれず苦しい。
かといって親と上手く付き合うことも出来ない。
「どうして自分は親の望むような子どもになれないのか」と自分を責めている。
そんな人におすすめの本。
著者自身の体験をふまえながら、問題のない家庭なんてどこにもないことや、親と自分は違う人格を持った別の人間なので親の言う通りにならなくて良いのだ、ということが書かれています。
たった一度きりの人生を親に振り回されて無駄にするのではなく、自分らしく生きるきっかけとなる本だと思います。
わたし自身、親との関係に大人になってからも苦しんでいるので、この本を読んで気持ちが楽になりました。
かといって親と上手く付き合うことも出来ない。
「どうして自分は親の望むような子どもになれないのか」と自分を責めている。
そんな人におすすめの本。
著者自身の体験をふまえながら、問題のない家庭なんてどこにもないことや、親と自分は違う人格を持った別の人間なので親の言う通りにならなくて良いのだ、ということが書かれています。
たった一度きりの人生を親に振り回されて無駄にするのではなく、自分らしく生きるきっかけとなる本だと思います。
わたし自身、親との関係に大人になってからも苦しんでいるので、この本を読んで気持ちが楽になりました。
監修…紫月香帆、平林亮子『神さまが教える お金を引き寄せる教科書』
2020年5月30日 おすすめの本一覧
・自分の財布にいくら入っているか把握していない
・好きなものは我慢しない
・「余ったら」という成り行きで貯金している
といった感じでお金が貯められない人におすすめの本。
結婚・妊娠・出産・子育て・マイカーやマイホーム購入・老後といった様々なライフイベントごとにかかる金額の相場、家計簿のつけ方、給与明細の見方、税金や年金の仕組みなどについて、イラストや漫画を使って分かりやすく教えてくれます。
なお、P111には、立て続けに同世代が結婚する20〜30代はいつ結婚式が重なってもいいように臨時支出用の特別費を高めに設定しておくと安心、ということが書かれています。
わたしもそういえば若い頃、少ない給料をやりくりして友達の結婚祝いや出産祝いのためにお金を貯めていたなぁ…としみじみ思い出しました。
・好きなものは我慢しない
・「余ったら」という成り行きで貯金している
といった感じでお金が貯められない人におすすめの本。
結婚・妊娠・出産・子育て・マイカーやマイホーム購入・老後といった様々なライフイベントごとにかかる金額の相場、家計簿のつけ方、給与明細の見方、税金や年金の仕組みなどについて、イラストや漫画を使って分かりやすく教えてくれます。
なお、P111には、立て続けに同世代が結婚する20〜30代はいつ結婚式が重なってもいいように臨時支出用の特別費を高めに設定しておくと安心、ということが書かれています。
わたしもそういえば若い頃、少ない給料をやりくりして友達の結婚祝いや出産祝いのためにお金を貯めていたなぁ…としみじみ思い出しました。
著…佐々木拓巳『似合うが見つかるヘアアレンジの法則』
2020年4月26日 おすすめの本一覧
「自分は不器用だからヘアアレンジなんて出来ない」と思っている方にこそおすすめしたい本。
難しいことが出来なくても、どうすればお洒落に見えるかというポイントを理解して、髪をドライヤーで乾かす時やセットをする時などにほんの少しでも意識すれば、印象をかなり変えられます。
ポイントは骨格別の「分け目」「おくれ毛」「前髪」。
トップの髪の毛にボリュームを持たせて、分け目をぼかす。
顔周りの髪にゆるいカールをつけたり、細めの毛束を少しずつ引き出したりして、ニュアンスのあるおくれ毛をつくる。
正面だけではなく斜めや横から見た時のバランスも意識しながら、前髪にも隙間を作ったりカールをつけるなど動きを出す。
こうしたポイントが分かっていれば、一つ結びでも可愛くなります!
この本には、「分け目」「おくれ毛」「前髪」が可愛く出来ているかいないかの比較写真や、スタイリング剤の上手なつけ方、髪の乾かし方などが載っているので、コツが分かりやすいです。
骨格や髪質によっても似合う・似合わないがあるので、まずP42〜43の骨格チェックやP56〜57の髪質チェックを読んでみてください。
難しいことが出来なくても、どうすればお洒落に見えるかというポイントを理解して、髪をドライヤーで乾かす時やセットをする時などにほんの少しでも意識すれば、印象をかなり変えられます。
ポイントは骨格別の「分け目」「おくれ毛」「前髪」。
トップの髪の毛にボリュームを持たせて、分け目をぼかす。
顔周りの髪にゆるいカールをつけたり、細めの毛束を少しずつ引き出したりして、ニュアンスのあるおくれ毛をつくる。
正面だけではなく斜めや横から見た時のバランスも意識しながら、前髪にも隙間を作ったりカールをつけるなど動きを出す。
こうしたポイントが分かっていれば、一つ結びでも可愛くなります!
この本には、「分け目」「おくれ毛」「前髪」が可愛く出来ているかいないかの比較写真や、スタイリング剤の上手なつけ方、髪の乾かし方などが載っているので、コツが分かりやすいです。
骨格や髪質によっても似合う・似合わないがあるので、まずP42〜43の骨格チェックやP56〜57の髪質チェックを読んでみてください。
著…丸々もとお、丸田あつし『夜光列車』
2020年4月22日 おすすめの本一覧
夜にジャズを聴きながら、ゆったりとページを捲りたくなる写真集。
暗闇の中を流れ星のように走る列車の光がとても美しいです。
日常のワンシーンでありながらも、違う世界に入り込んだかのようなロマンがあります。
夜景の一つとして外から眺めるのも味わいがあるし、乗客としてコトンコトン…と揺られながらちょっとセンチメンタルな気分に浸るのも良いものですね。
暗闇の中を流れ星のように走る列車の光がとても美しいです。
日常のワンシーンでありながらも、違う世界に入り込んだかのようなロマンがあります。
夜景の一つとして外から眺めるのも味わいがあるし、乗客としてコトンコトン…と揺られながらちょっとセンチメンタルな気分に浸るのも良いものですね。
著…中野京子『中野京子と読み解く名画の謎 旧約・新約聖書篇』
2020年4月19日 おすすめの本一覧
多くの画家が好んで描いてきた「楽園追放」「カインとアベル」「七つの大罪」といったキリスト教的テーマについて学ぶことで名画をもっと楽しもう、という本。
聖書に関する映画や漫画にも登場する「ヤコブ」「マグダラのマリア」「マタイ」といった人物たちの概要についても説明してくれます。
おかげさまで、ちょっと物知りになった気分になれます。
それにしても、神様の残酷さには驚かされます!
アブラハムを試すために、「息子イサクを殺して神に捧げよ」と言うなんて!
わたしがキリスト教徒ではないから、息子への愛よりも信仰を取るアブラハムの行動がショックなのであって、敬虔なキリスト教徒にとっては当たり前なのかもしれませんが…。
アブラハムは神様を信じ切っていたので、イサクと一緒に祭壇を作り、イサクを縛ってその首を切ろうとしたところ、天使が舞い降りてきて止めてくれたそうです。
天使ありがとう!
レンブラントが描いた『イサクの犠牲』には、今まさに父親に首を切られようとしているのに抵抗もせず横たわるイサクが描かれていて、…哀れ。
わたしに言わせりゃ、我が子を殺めようとするアブラハムもむかつくし、人間を試そうとして無茶振りしてくる神様もむかつきますよ!
確かに神様は世界を作ってくれたかもしれませんが、だからって何をやってもいいんかい!?
わたしはイサクに「我が子を愛さないような親に黙って従うことないよ」と言いたい。
これは、親から虐待されている子どもたち全てに言いたいこと。
子どもは親にどんなに酷いことをされてもやっぱり親を愛してしまいがちだけれど…。
わたしはこの絵の天使のように、止めに入れる人になりたいです。
聖書に関する映画や漫画にも登場する「ヤコブ」「マグダラのマリア」「マタイ」といった人物たちの概要についても説明してくれます。
おかげさまで、ちょっと物知りになった気分になれます。
それにしても、神様の残酷さには驚かされます!
アブラハムを試すために、「息子イサクを殺して神に捧げよ」と言うなんて!
わたしがキリスト教徒ではないから、息子への愛よりも信仰を取るアブラハムの行動がショックなのであって、敬虔なキリスト教徒にとっては当たり前なのかもしれませんが…。
アブラハムは神様を信じ切っていたので、イサクと一緒に祭壇を作り、イサクを縛ってその首を切ろうとしたところ、天使が舞い降りてきて止めてくれたそうです。
天使ありがとう!
レンブラントが描いた『イサクの犠牲』には、今まさに父親に首を切られようとしているのに抵抗もせず横たわるイサクが描かれていて、…哀れ。
わたしに言わせりゃ、我が子を殺めようとするアブラハムもむかつくし、人間を試そうとして無茶振りしてくる神様もむかつきますよ!
確かに神様は世界を作ってくれたかもしれませんが、だからって何をやってもいいんかい!?
わたしはイサクに「我が子を愛さないような親に黙って従うことないよ」と言いたい。
これは、親から虐待されている子どもたち全てに言いたいこと。
子どもは親にどんなに酷いことをされてもやっぱり親を愛してしまいがちだけれど…。
わたしはこの絵の天使のように、止めに入れる人になりたいです。
おしゃれな写真をスマホで撮るテクニックを紹介している本。
「順光」、「前斜光」、「サイド光」、「半逆光」、「逆光」といった光と影の使い分けや、構図の使い分けを分かりやすく学べます。
万能の「三分割構図」。
海と空、山と空のコントラストが美しい「二分割構図」。
風景の奥行きを表現する「三角構図」。
写真にインパクトを与える「逆三角構図」。
被写体を引き立てる「日の丸構図」。
奥行きやリズム感を出す「対角線構図」。
絵画のようにおしゃれな「フレーム構図」。
被写体を模様に見立てる「パターン構図」。
メリハリがついて迫力が出る「遠近構図」。
構図だけでもこんなに沢山あるんですね!
新型コロナウイルスの流行がおさまったら、色んな所へ出かけて色んな写真を撮りたいです。
「順光」、「前斜光」、「サイド光」、「半逆光」、「逆光」といった光と影の使い分けや、構図の使い分けを分かりやすく学べます。
万能の「三分割構図」。
海と空、山と空のコントラストが美しい「二分割構図」。
風景の奥行きを表現する「三角構図」。
写真にインパクトを与える「逆三角構図」。
被写体を引き立てる「日の丸構図」。
奥行きやリズム感を出す「対角線構図」。
絵画のようにおしゃれな「フレーム構図」。
被写体を模様に見立てる「パターン構図」。
メリハリがついて迫力が出る「遠近構図」。
構図だけでもこんなに沢山あるんですね!
新型コロナウイルスの流行がおさまったら、色んな所へ出かけて色んな写真を撮りたいです。
お茶会に行くにあたって用意した方が良い持ち物、相応しい服装と髪型、お客様側の最低限のマナーをゆる〜いイラストと共にまとめた本。
茶室に入る前に腕時計やアクセサリー類を外しましょう、と書いてあるのが、普段お客様をお招きしている側からすると本当に有難いです。
お懐紙やお扇子まで用意せず、手ぶらで来ていただいたとしても、お招きした側としては嬉しいものです。
お客様におもてなしをさせていただくために色々準備をしてきたわけですから。
来てくださってありがとう! わたしたちが頑張るからお客様は頑張らずにゆっくり寛いでいてください! って思います。
お茶の世界を堪能していただくために、とにかく貴金属類を外すことだけを意識してくださると嬉しい!
なぜかと言うと、お茶碗を持った時に指輪や腕時計をお茶碗にカーン!と当ててしまう方や、一礼した時にネックレスがお抹茶の中にちゃっぽんと入ってしまう方、時々いらっしゃるんですよね…。
お客様が「沢山の人たちの前で恥をかいた!」と思ったら、そのお客様はもうお茶会に来てくださらないかもしれません。
そうなると、おもてなしをしたい側のわたしたちにとっても不幸。
お客様が来てくださらなかったら、おもてなしのしようが、無いっ!!
ですからノーモア貴金属!でございます。
そもそもお茶というのは、かつて名だたる戦国武将たちであっても甲冑や武器を茶室に持ち込まず、ゆったりとした心地で楽しんだもののはず。
ですから、現代のお客様たちにもリラックスして美味しいお茶とお菓子を堪能していただきたいです。
茶室に入る前に腕時計やアクセサリー類を外しましょう、と書いてあるのが、普段お客様をお招きしている側からすると本当に有難いです。
お懐紙やお扇子まで用意せず、手ぶらで来ていただいたとしても、お招きした側としては嬉しいものです。
お客様におもてなしをさせていただくために色々準備をしてきたわけですから。
来てくださってありがとう! わたしたちが頑張るからお客様は頑張らずにゆっくり寛いでいてください! って思います。
お茶の世界を堪能していただくために、とにかく貴金属類を外すことだけを意識してくださると嬉しい!
なぜかと言うと、お茶碗を持った時に指輪や腕時計をお茶碗にカーン!と当ててしまう方や、一礼した時にネックレスがお抹茶の中にちゃっぽんと入ってしまう方、時々いらっしゃるんですよね…。
お客様が「沢山の人たちの前で恥をかいた!」と思ったら、そのお客様はもうお茶会に来てくださらないかもしれません。
そうなると、おもてなしをしたい側のわたしたちにとっても不幸。
お客様が来てくださらなかったら、おもてなしのしようが、無いっ!!
ですからノーモア貴金属!でございます。
そもそもお茶というのは、かつて名だたる戦国武将たちであっても甲冑や武器を茶室に持ち込まず、ゆったりとした心地で楽しんだもののはず。
ですから、現代のお客様たちにもリラックスして美味しいお茶とお菓子を堪能していただきたいです。
著…山崎陽子『きものが着たくなったなら』
2020年4月4日 おすすめの本一覧 コメント (2)
「時々しか着ないと、もう着ること自体が面倒になり、そのうち着方も忘れてしまいます。だから、できるだけふだん着的な紬や小紋でスタートするといいと思うのです」
(P14から抜粋)
という著者の考え方にわたしは共感しました。
こういう軽やかな考え方の人が増えてくれれば良いなぁと心の底から思います。
せっかく「着物を着てみたいな」と思ってまずはカジュアルな着物で街へ出かけてみた人が居ても、いわゆる「着物警察」と呼ばれる人たちが頼んでもいないのにどこからともなく寄って来て、「訪問着じゃないとどうたらこうたら」「正絹じゃないとどうたらこうたら」とネチネチお説教をしてくることって、多いんです。
「着物警察」に悪気は無く、むしろ着物の伝統を「正しく」「上品に」継承させたいそうなのですが、赤の他人からお説教をされる側はたまったものではありません。
「嫌な思いをさせられた。着物なんて着るんじゃなかった」と若い芽を潰すだけ。
わたしも木綿の着物を着てお茶のお稽古に向かっていたら赤の他人の「着物警察」に不当逮捕されて「あなたその着物いくら?安そう。正絹の訪問着を買えないの?」と着物をベタベタ触られて嫌な思いことをしたことがあります。
今からお稽古でお抹茶が付くかもしれないのに、いちいち正絹の訪問着なんて着ていられるかっ!というか他人の着ているものを勝手に触るとかあり得ん!!と内心思いながら、「失礼ですがどちら様でしょうか? 貴方さまのことを存じ上げないのですが。急いでおりますので失礼いたします」とわたしは返事をして着物警察をスルーしてやりましたが。
(着物警察は「せっかく教えてあげたのに!これだから今時の人は」と憤慨していましたが。昔の人でもあなたのような人は嫌だと思いますよ、と言ってやれば良かったなと今では思いますが余計怒られそうだから止めて正解ですね)
着物を「特別なもの」とか「高尚なもの」だと捉えると、こうした「着物警察」みたいな凝り固まった考えになってしまうのだと思います。
けれど、着物って昔の日本人は日常的に着ていたはずですよね?
だから、普段着として気軽に楽しみましょう!
「お出かけする日だけでなく、家で過ごす日も積極的に身につける。そうやって、できれば週に1回、3時間着るようにすると、きものが体に寄り添ってくるし、体がきものに慣れてきます。それまで敬語で話していたきものが、友達言葉でしゃべりかけてくるようになるのです」
(P14から抜粋)
著者のこういう考え方、良いなぁ。
わたしも着物を着る機会をどんどん増やしていこうと思います。
高いものは買えないので、安いものや、リサイクル品をうまく組み合わせて、着物を楽しく着たいです。
着物は着たくなった時が着るタイミングです!
(P14から抜粋)
という著者の考え方にわたしは共感しました。
こういう軽やかな考え方の人が増えてくれれば良いなぁと心の底から思います。
せっかく「着物を着てみたいな」と思ってまずはカジュアルな着物で街へ出かけてみた人が居ても、いわゆる「着物警察」と呼ばれる人たちが頼んでもいないのにどこからともなく寄って来て、「訪問着じゃないとどうたらこうたら」「正絹じゃないとどうたらこうたら」とネチネチお説教をしてくることって、多いんです。
「着物警察」に悪気は無く、むしろ着物の伝統を「正しく」「上品に」継承させたいそうなのですが、赤の他人からお説教をされる側はたまったものではありません。
「嫌な思いをさせられた。着物なんて着るんじゃなかった」と若い芽を潰すだけ。
わたしも木綿の着物を着てお茶のお稽古に向かっていたら赤の他人の「着物警察」に不当逮捕されて「あなたその着物いくら?安そう。正絹の訪問着を買えないの?」と着物をベタベタ触られて嫌な思いことをしたことがあります。
今からお稽古でお抹茶が付くかもしれないのに、いちいち正絹の訪問着なんて着ていられるかっ!というか他人の着ているものを勝手に触るとかあり得ん!!と内心思いながら、「失礼ですがどちら様でしょうか? 貴方さまのことを存じ上げないのですが。急いでおりますので失礼いたします」とわたしは返事をして着物警察をスルーしてやりましたが。
(着物警察は「せっかく教えてあげたのに!これだから今時の人は」と憤慨していましたが。昔の人でもあなたのような人は嫌だと思いますよ、と言ってやれば良かったなと今では思いますが余計怒られそうだから止めて正解ですね)
着物を「特別なもの」とか「高尚なもの」だと捉えると、こうした「着物警察」みたいな凝り固まった考えになってしまうのだと思います。
けれど、着物って昔の日本人は日常的に着ていたはずですよね?
だから、普段着として気軽に楽しみましょう!
「お出かけする日だけでなく、家で過ごす日も積極的に身につける。そうやって、できれば週に1回、3時間着るようにすると、きものが体に寄り添ってくるし、体がきものに慣れてきます。それまで敬語で話していたきものが、友達言葉でしゃべりかけてくるようになるのです」
(P14から抜粋)
著者のこういう考え方、良いなぁ。
わたしも着物を着る機会をどんどん増やしていこうと思います。
高いものは買えないので、安いものや、リサイクル品をうまく組み合わせて、着物を楽しく着たいです。
着物は着たくなった時が着るタイミングです!
著…草刈民代『全身「からだ革命」』
2020年3月18日 おすすめの本一覧
「不思議なことに、若いころよりも、無理がきくような感覚さえあるのです」
(P16から抜粋)
と言う草刈さんによる「疲れない身体づくり」の本。
頑張りすぎて心身共に無理をしてしまうと、怪我をしたり、心が不安定になりがちですよね。
特に、草刈さんが昔から活躍しているバレエというものは尋常ではないレベルで全身を酷使するもの。
草刈さんは胃の痛みや怪我に悩まされてきたそうです。
それが、自然食中心の食生活に変えたら、身体が「食べていいもの」「食べたらよくないもの」を判別出来るようになり、市販の栄養ドリンクを一口飲むだけでも違和感を感じるようになるという変化も生まれたとのこと。
草刈さんはPNFメソッドやピラティスといったものにも励んでいるそうですが、やはり食生活って大事なんですね。
わたしはこの本に「なるべく避けたい食材」として載っているものをよく摂取しています。
牛肉、豚肉、魚卵類、魚介類、炭酸飲料水、牛乳、チーズ、ヨーグルト、アイスクリーム、チョコレートなど…。
はっきり言って美味しいものばかりなので、完全に断つのは難しいですが、摂取する量や頻度を控えめにしてみます。
(P16から抜粋)
と言う草刈さんによる「疲れない身体づくり」の本。
頑張りすぎて心身共に無理をしてしまうと、怪我をしたり、心が不安定になりがちですよね。
特に、草刈さんが昔から活躍しているバレエというものは尋常ではないレベルで全身を酷使するもの。
草刈さんは胃の痛みや怪我に悩まされてきたそうです。
それが、自然食中心の食生活に変えたら、身体が「食べていいもの」「食べたらよくないもの」を判別出来るようになり、市販の栄養ドリンクを一口飲むだけでも違和感を感じるようになるという変化も生まれたとのこと。
草刈さんはPNFメソッドやピラティスといったものにも励んでいるそうですが、やはり食生活って大事なんですね。
わたしはこの本に「なるべく避けたい食材」として載っているものをよく摂取しています。
牛肉、豚肉、魚卵類、魚介類、炭酸飲料水、牛乳、チーズ、ヨーグルト、アイスクリーム、チョコレートなど…。
はっきり言って美味しいものばかりなので、完全に断つのは難しいですが、摂取する量や頻度を控えめにしてみます。
ナショナルジオグラフィック『天才の秘密 驚異的な能力を発揮した人々』
2020年3月17日 おすすめの本一覧
「天才」は「平凡」な人々とどう違うのか? を考察する本。
「天才」の定義は無いけれど、敢えて言うなれば、子どもの頃からのIQの高さはさほど重要ではなく、むしろ、
興味を持ったことを途中で投げ出さずに「もっと極めよう」と夢中になれることや、
普通の人が気づかないような細かい違いにとことんこだわり抜けること、
自分のひらめきを周りの人々から否定されたり挫折しても自分を信じ続けること、
そして孤高の天才は意外と多くは無く、周りの人たちとの巡り合わせも重要…、
とわたしはこの本の内容を解釈しました。
モーツァルトのように幼い頃からずば抜けた才能を発揮する早咲きタイプの天才も居れば、ダーウィンのように周囲の人から平凡どころか平均以下だと心配された遅咲きタイプの天才も居るのが興味深いです。
人生のスタートダッシュがうまくいかなくても、何歳からでも花開けるということに励まされます。
また、P56には薄くスライスされたアインシュタインの脳の写真が載っていて、わたしは非常に驚かされました。
組織サンプルとして研究されているのだとか。
「天才」は死後も注目の的なのですね…。
もし死後の世界があるとすれば、アインシュタインの魂はこの脳という名のサナギからとっくに脱皮して別の次元へと旅立っているのだろうな…とわたしは思わずSFめいたことを空想せずにはいられませんでした。
アインシュタインの魂は、今どこを旅しているのでしょう。
いや、「今」という時間の概念さえも飛び越えているのかも。
「天才」の定義は無いけれど、敢えて言うなれば、子どもの頃からのIQの高さはさほど重要ではなく、むしろ、
興味を持ったことを途中で投げ出さずに「もっと極めよう」と夢中になれることや、
普通の人が気づかないような細かい違いにとことんこだわり抜けること、
自分のひらめきを周りの人々から否定されたり挫折しても自分を信じ続けること、
そして孤高の天才は意外と多くは無く、周りの人たちとの巡り合わせも重要…、
とわたしはこの本の内容を解釈しました。
モーツァルトのように幼い頃からずば抜けた才能を発揮する早咲きタイプの天才も居れば、ダーウィンのように周囲の人から平凡どころか平均以下だと心配された遅咲きタイプの天才も居るのが興味深いです。
人生のスタートダッシュがうまくいかなくても、何歳からでも花開けるということに励まされます。
また、P56には薄くスライスされたアインシュタインの脳の写真が載っていて、わたしは非常に驚かされました。
組織サンプルとして研究されているのだとか。
「天才」は死後も注目の的なのですね…。
もし死後の世界があるとすれば、アインシュタインの魂はこの脳という名のサナギからとっくに脱皮して別の次元へと旅立っているのだろうな…とわたしは思わずSFめいたことを空想せずにはいられませんでした。
アインシュタインの魂は、今どこを旅しているのでしょう。
いや、「今」という時間の概念さえも飛び越えているのかも。
DIY好きにおすすめの本。
自分の部屋の場合は壁紙をどのくらい買えば良いのか?という計算方法、壁紙を貼るために必要な道具と手順、窓やエアコン周辺といった細かい部分の処理方法、壁紙を全て剥がして原状回復させる方法などがまとめられています。
壁紙が個性的な分、家具や小物をシンプルにしてごちゃつかないようにする、といったバランスの取り方も学べます。
壁紙だけでなく、賃貸住まいでも原状回復可能な床のセルフリフォーム方法も紹介されています。
壁紙も床も、部屋の印象を大きく変えてくれるので面白いです。
自分の部屋の場合は壁紙をどのくらい買えば良いのか?という計算方法、壁紙を貼るために必要な道具と手順、窓やエアコン周辺といった細かい部分の処理方法、壁紙を全て剥がして原状回復させる方法などがまとめられています。
壁紙が個性的な分、家具や小物をシンプルにしてごちゃつかないようにする、といったバランスの取り方も学べます。
壁紙だけでなく、賃貸住まいでも原状回復可能な床のセルフリフォーム方法も紹介されています。
壁紙も床も、部屋の印象を大きく変えてくれるので面白いです。
「なぜなのかはうまく説明出来ないが、なんとなく違和感がある。または何となく好ましい」といった感覚についての本。
この直感的なひらめきのことを、この本では「第1感」と呼びます。
第1感が働くのは、最初のわずか2秒だけ。
例えば、初対面の人に会う時。
求職者を面接する時。
切羽詰まった状況でとっさに判断しなければならない時。
人は、大量のデータを瞬時に処理しているそうです。
思考のモードをその時の状況に応じてどうやって切り替えているのかは分かりませんが。
そう言えばわたしもこの本を見つけて「面白そう」と思ってから「読もう」と決めるまでに数秒程度しかかからなかったな…と、この本を読んでいてとても不思議な気持ちになりました。
わたしも「第1感」を鍛えていきたいです。
この直感的なひらめきのことを、この本では「第1感」と呼びます。
第1感が働くのは、最初のわずか2秒だけ。
例えば、初対面の人に会う時。
求職者を面接する時。
切羽詰まった状況でとっさに判断しなければならない時。
人は、大量のデータを瞬時に処理しているそうです。
思考のモードをその時の状況に応じてどうやって切り替えているのかは分かりませんが。
そう言えばわたしもこの本を見つけて「面白そう」と思ってから「読もう」と決めるまでに数秒程度しかかからなかったな…と、この本を読んでいてとても不思議な気持ちになりました。
わたしも「第1感」を鍛えていきたいです。
「このまま死んでしまうのでは?」と怖くなるくらい動悸・呼吸困難・胸の痛み・めまい・吐き気といった発作に突然襲われる「パニック症」。
「また発作が起きるのでは?」という不安のせいで、発作が起きそうな場所や、発作が起きても助けを求められない場所を避けるようになり(「広場恐怖症」)、それまで当たり前に送れていたはずの生活に支障をきたします。
この本は、パニック症の症状と治療について漫画を使って教えてくれる他、パニック症と間違えられやすい「心臓神経症」「不安神経症」「自律神経失調症」「メニエール病」「過呼吸症候群」「狭心症」の症状なども紹介しています。
「パニック発作で死ぬことはありません。あわてると発作はよけい激しくなります。つまり発作を怖がる必要はないんです」
(P83から抜粋)
という優しい言葉が素敵。
「また発作が起きるのでは?」という不安のせいで、発作が起きそうな場所や、発作が起きても助けを求められない場所を避けるようになり(「広場恐怖症」)、それまで当たり前に送れていたはずの生活に支障をきたします。
この本は、パニック症の症状と治療について漫画を使って教えてくれる他、パニック症と間違えられやすい「心臓神経症」「不安神経症」「自律神経失調症」「メニエール病」「過呼吸症候群」「狭心症」の症状なども紹介しています。
「パニック発作で死ぬことはありません。あわてると発作はよけい激しくなります。つまり発作を怖がる必要はないんです」
(P83から抜粋)
という優しい言葉が素敵。
著…ザビエル『なぜか、夫はいつも他人ゴト。』
2020年3月8日 おすすめの本一覧
「なぜ夫は人の話を聞かず、家事をやらず、育児に関心がなく、浮気をするのか」を疑問に思っている人におすすめの本。
夫に悪気はなく、というより妻の気持ちに気づいてすらいないので、
「夫はこれまでの人生でデリカシーを学んでこなかった。だからあなたがデリカシーを教えてあげるべし」
(P34から抜粋)
だそうです。
また、夫が真意を伝えてくれないのは、伝え方すら分かっていないから。
「〜して当たり前なのに」「〜できて当たり前なのに」と考えるのではなく、「この人は〜が出来ない。だとしたら〜して教えよう」という考え方で接する方が良さそうですね。
関わる機会を増やしてあげて、失敗しても許してあげて、気長に付き合っていく中で教えてあげるしか無さそう。
また、
「外国の人に日本の文化を教える場合、〝なんでそのぐらいのことを知らないの?〟とはならないですよね」
(P135〜136から抜粋)
という記述に、わたしは「なるほど!」と納得しました!
確かに、外国人だと思えばイライラせずに済みます!
そもそも、夫婦って赤の他人同士。
夫の方も妻のことを外国人だと思っていそう。
外国人同士で仲良く暮らしていくには、お互いの努力が必要ですよね。
この本の場合、妻側の努力を求める率が高いですが、ぜひ夫側も努力を!
夫に悪気はなく、というより妻の気持ちに気づいてすらいないので、
「夫はこれまでの人生でデリカシーを学んでこなかった。だからあなたがデリカシーを教えてあげるべし」
(P34から抜粋)
だそうです。
また、夫が真意を伝えてくれないのは、伝え方すら分かっていないから。
「〜して当たり前なのに」「〜できて当たり前なのに」と考えるのではなく、「この人は〜が出来ない。だとしたら〜して教えよう」という考え方で接する方が良さそうですね。
関わる機会を増やしてあげて、失敗しても許してあげて、気長に付き合っていく中で教えてあげるしか無さそう。
また、
「外国の人に日本の文化を教える場合、〝なんでそのぐらいのことを知らないの?〟とはならないですよね」
(P135〜136から抜粋)
という記述に、わたしは「なるほど!」と納得しました!
確かに、外国人だと思えばイライラせずに済みます!
そもそも、夫婦って赤の他人同士。
夫の方も妻のことを外国人だと思っていそう。
外国人同士で仲良く暮らしていくには、お互いの努力が必要ですよね。
この本の場合、妻側の努力を求める率が高いですが、ぜひ夫側も努力を!
挑発的なタイトルですが、血液型別の性格診断も心理テストも根拠は特に無く、誰にでも当てはまるようなことを言う「遊び」だったんだなぁ…と気づかせてくれる本です。
学生時代はよく友人たちと心理テストをやって「当たってる!」「えー、なんか違う!」と盛り上がらせてもらったので、たとえそこに信憑性が無くても良しとしたいと思います。
そういえば以前友人から「〇〇ちゃん(わたしのこと)って本当にA型なの? AB型かB型っぽい。血液検査で調べ直してもらったら?」とまで言われたことがありましたが、人間の性格をA・B・O・ABというたった4パターンに当て嵌めようとする方が無茶ですよね。
娯楽なのだからと割り切って楽しむ分には良いけれど、あまり深入りし過ぎて「〇〇型の人はうちの職場には採用しない」などと血液型差別をしないよう、自分自身も気をつけようと思います。
学生時代はよく友人たちと心理テストをやって「当たってる!」「えー、なんか違う!」と盛り上がらせてもらったので、たとえそこに信憑性が無くても良しとしたいと思います。
そういえば以前友人から「〇〇ちゃん(わたしのこと)って本当にA型なの? AB型かB型っぽい。血液検査で調べ直してもらったら?」とまで言われたことがありましたが、人間の性格をA・B・O・ABというたった4パターンに当て嵌めようとする方が無茶ですよね。
娯楽なのだからと割り切って楽しむ分には良いけれど、あまり深入りし過ぎて「〇〇型の人はうちの職場には採用しない」などと血液型差別をしないよう、自分自身も気をつけようと思います。
著…川島眞『化粧品を正しく使えばあなたはもっとキレイになる。』
2020年3月2日 おすすめの本一覧
特に、P66〜68掲載の「スキンケア」と「治療」の境界線についての話が勉強になります。
自分の自然治癒能力を過信して「スキンケアで治る」と思い、治療をせずに悪化させてしまい、耐えきれなくなってようやく病院に来る患者さんが沢山いるそうです。
「皮膚には、外部の刺激から体の内側を守る役割があると同時に、体の内側の異常を目で見える形にして伝えるという役割もあるわけです。(中略)いつものスキンケアを続けていても皮膚の症状がよくならない場合は、何らかの原因があるのです」
(P42から抜粋)
と著者が話している通り、どこまでが「スキンケア」による自己対応が可能で、どこからが専門医による「治療」の範囲なのか、一人ひとりが理解しておくことが大切ですね。
取り返しがつかないほど肌がボロボロになってから皮膚科に駆け込んでも遅いでしょうから…。
また、P118〜120掲載の「無添加神話」についての話も分かりやすいです。
パラベンは防腐剤の一つなので、もし化粧品に「パラベンフリー」と書かれていても他の防腐剤を入れている場合があることや、防腐剤のない化粧品に指を突っ込んで指の菌を付着させたり冷蔵庫に入れ忘れたりすると菌やカビが生えるリスクもあることが書かれています。
化粧品を安全に使って、トラブルの無い肌を手に入れたいですね。
自分の自然治癒能力を過信して「スキンケアで治る」と思い、治療をせずに悪化させてしまい、耐えきれなくなってようやく病院に来る患者さんが沢山いるそうです。
「皮膚には、外部の刺激から体の内側を守る役割があると同時に、体の内側の異常を目で見える形にして伝えるという役割もあるわけです。(中略)いつものスキンケアを続けていても皮膚の症状がよくならない場合は、何らかの原因があるのです」
(P42から抜粋)
と著者が話している通り、どこまでが「スキンケア」による自己対応が可能で、どこからが専門医による「治療」の範囲なのか、一人ひとりが理解しておくことが大切ですね。
取り返しがつかないほど肌がボロボロになってから皮膚科に駆け込んでも遅いでしょうから…。
また、P118〜120掲載の「無添加神話」についての話も分かりやすいです。
パラベンは防腐剤の一つなので、もし化粧品に「パラベンフリー」と書かれていても他の防腐剤を入れている場合があることや、防腐剤のない化粧品に指を突っ込んで指の菌を付着させたり冷蔵庫に入れ忘れたりすると菌やカビが生えるリスクもあることが書かれています。
化粧品を安全に使って、トラブルの無い肌を手に入れたいですね。