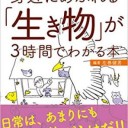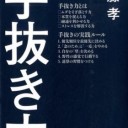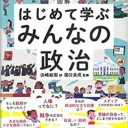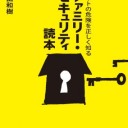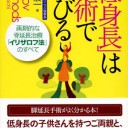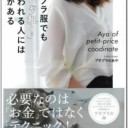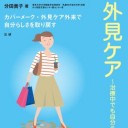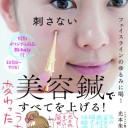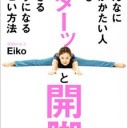著…山崎まゆみ『続・バリアフリー温泉で家族旅行』
2019年7月7日 おすすめの本一覧
「温泉が大好きだけど、足腰が弱ったから、もう行けないね」なんてセリフを大好きな人に言わせないで済む本。
物理的なバリアフリーが進んでいるのは勿論、宿の代表者に体の不自由な人を受け入れる気持ちがある全国各地の温泉付き施設を紹介しています。
車椅子使用者の駐車場が何台分あるか、車椅子対応のトイレがあるか、車椅子に乗って温泉にどこまで入れるか(貸切温泉のみか、大浴場も入れるのか等)、湯船のつくりはどうか、館内または近くに車椅子に乗って立ち寄れる食事処があるか、近くに観光名所はあるか、等も掲載されています。
わたしはこの本を読みながら、「祖母たちが生きているうちに温泉に連れて行ってあげたかったな」とつくづく後悔しました。
出来る限りの在宅介護をして看取ったつもりではありますが、あれをしてあげれば良かった、これもしてあげられたのではないか、と後悔は尽きません。
亡くなった人にはもはや何もしてあげられませんが、生きている人のために、こうしたバリアフリー情報を役立てたいです。
わたし自身も、今は健康ですが、もしかしたら病気や事故や災害などで車椅子生活になるかもしれませんし、我が事としてこうした情報を把握しておきたいです。
また、ここ本のP84〜87には、手術などで体に傷あとがある人に配慮した宿が紹介されています。
浴槽の中で使用しても衛生上の心配が一切ない専用ガーゼタオルを使って、人目を気にせず心身を癒せるという取り組みが素晴らしいと思います。
「ピンクリボンのお宿」というんですね。
友達が乳がんの手術をしたのですが、こうした所ならまた一緒に温泉旅行が出来るかも…。
物理的なバリアフリーが進んでいるのは勿論、宿の代表者に体の不自由な人を受け入れる気持ちがある全国各地の温泉付き施設を紹介しています。
車椅子使用者の駐車場が何台分あるか、車椅子対応のトイレがあるか、車椅子に乗って温泉にどこまで入れるか(貸切温泉のみか、大浴場も入れるのか等)、湯船のつくりはどうか、館内または近くに車椅子に乗って立ち寄れる食事処があるか、近くに観光名所はあるか、等も掲載されています。
わたしはこの本を読みながら、「祖母たちが生きているうちに温泉に連れて行ってあげたかったな」とつくづく後悔しました。
出来る限りの在宅介護をして看取ったつもりではありますが、あれをしてあげれば良かった、これもしてあげられたのではないか、と後悔は尽きません。
亡くなった人にはもはや何もしてあげられませんが、生きている人のために、こうしたバリアフリー情報を役立てたいです。
わたし自身も、今は健康ですが、もしかしたら病気や事故や災害などで車椅子生活になるかもしれませんし、我が事としてこうした情報を把握しておきたいです。
また、ここ本のP84〜87には、手術などで体に傷あとがある人に配慮した宿が紹介されています。
浴槽の中で使用しても衛生上の心配が一切ない専用ガーゼタオルを使って、人目を気にせず心身を癒せるという取り組みが素晴らしいと思います。
「ピンクリボンのお宿」というんですね。
友達が乳がんの手術をしたのですが、こうした所ならまた一緒に温泉旅行が出来るかも…。
まずウイルスや細菌に触れているのが興味深いです。
ウイルスも細菌も、肉眼では見えないけれどあちこちに居ます。
居ないところを見つける方が難しいほど。
「昨今は、何でも殺菌したほうがいいかのような「抗菌ブーム」がおきていますが、そもそも人のからだにすみつく常在菌がいなかったら健康な生活は困難になってしまいます。細菌も自然界や人体の微妙なバランスのうえに存在しています。そのバランスを崩してしまうことにならないようにしたいものです」
(P17から抜粋)
という文に共感。
赤痢菌や結核菌といった危険な菌ならともかく、細菌を必要以上に怖がると、良い菌まで殺してしまって、かえって人体に悪影響をもたらす場合があります。
何事もバランスが大切。
この本には他にも、
「なぜハエをたたくのは難しいの?」
「ミミズが夏の炎天下で干からびているのはなぜ?」
「スズメはなぜ毎朝チュンチュン鳴いているの?」
「ウサギはなぜ自分のうんちを食べるの?」
「ヘビはなぜ大きな獲物を丸呑みできるの?」
「シカの角は骨じゃなくて皮膚?」
「なぜクラゲはお盆の頃に大量発生するの?」
といった素朴な疑問とその答えとなる説が書かれていて、興味深いです。
ウイルスも細菌も、肉眼では見えないけれどあちこちに居ます。
居ないところを見つける方が難しいほど。
「昨今は、何でも殺菌したほうがいいかのような「抗菌ブーム」がおきていますが、そもそも人のからだにすみつく常在菌がいなかったら健康な生活は困難になってしまいます。細菌も自然界や人体の微妙なバランスのうえに存在しています。そのバランスを崩してしまうことにならないようにしたいものです」
(P17から抜粋)
という文に共感。
赤痢菌や結核菌といった危険な菌ならともかく、細菌を必要以上に怖がると、良い菌まで殺してしまって、かえって人体に悪影響をもたらす場合があります。
何事もバランスが大切。
この本には他にも、
「なぜハエをたたくのは難しいの?」
「ミミズが夏の炎天下で干からびているのはなぜ?」
「スズメはなぜ毎朝チュンチュン鳴いているの?」
「ウサギはなぜ自分のうんちを食べるの?」
「ヘビはなぜ大きな獲物を丸呑みできるの?」
「シカの角は骨じゃなくて皮膚?」
「なぜクラゲはお盆の頃に大量発生するの?」
といった素朴な疑問とその答えとなる説が書かれていて、興味深いです。
著…齋藤孝『手抜き力』
2019年5月14日 おすすめの本一覧
「手抜き」というと、サボるかのような印象がありますが、そうではありません。
「念のため」「一応」といった的外れで無駄な努力を省くのが「手抜き力」。
ゴールのビジョンを明確に持ち、そこから逆算して段取りをして、要領良く進めないと、ダラダラと大変な思いをしてモチベーションが下がっていくだけ。
適度に「手抜き」をしてエネルギー配分をすることで、時間や労力を節約でき、その空いた分で違うことをすることが出来ます。
早速手抜き力を身に付けたい人には、この本の『第4章 手抜き力を磨くトレーニング』を読むのがおすすめ。
「念のため」「一応」といった的外れで無駄な努力を省くのが「手抜き力」。
ゴールのビジョンを明確に持ち、そこから逆算して段取りをして、要領良く進めないと、ダラダラと大変な思いをしてモチベーションが下がっていくだけ。
適度に「手抜き」をしてエネルギー配分をすることで、時間や労力を節約でき、その空いた分で違うことをすることが出来ます。
早速手抜き力を身に付けたい人には、この本の『第4章 手抜き力を磨くトレーニング』を読むのがおすすめ。
「若いか老けているかよりかっこいいかどうか」
(P116から抜粋)
という言葉が印象的な本。
『ムリせず自然に美しく グレイヘアという選択』(レビューはこちら→https://20756.diarynote.jp/201808032217118892/)の続編です。
前作同様、黒染めをした髪からグレイヘアへの移行期間や、グレイヘアだからこそ映える鮮やかな色を使ってお洒落を楽しんでいる写真が多いです。
大人の女性が自分の変化に向き合って、より自分らしく輝いていく様子が伝わってきます。
「若さ」と「美しさ」は必ずしもイコールじゃない。
グレイヘアとは、単に白髪を伸ばしっぱなしにすることではない。
年齢を重ねたからこそ出来るお洒落を楽しむ大人の優雅さを感じさせます。
日々ニュアンスが変化していく自分の髪の色を楽しみながら、お肌もネイルもお手入れをして、今まで挑戦しなかったメイクや服に挑戦するなど、グレイヘアは自分らしく生きていくきっかけなのだ、と気付かされます。
(P116から抜粋)
という言葉が印象的な本。
『ムリせず自然に美しく グレイヘアという選択』(レビューはこちら→https://20756.diarynote.jp/201808032217118892/)の続編です。
前作同様、黒染めをした髪からグレイヘアへの移行期間や、グレイヘアだからこそ映える鮮やかな色を使ってお洒落を楽しんでいる写真が多いです。
大人の女性が自分の変化に向き合って、より自分らしく輝いていく様子が伝わってきます。
「若さ」と「美しさ」は必ずしもイコールじゃない。
グレイヘアとは、単に白髪を伸ばしっぱなしにすることではない。
年齢を重ねたからこそ出来るお洒落を楽しむ大人の優雅さを感じさせます。
日々ニュアンスが変化していく自分の髪の色を楽しみながら、お肌もネイルもお手入れをして、今まで挑戦しなかったメイクや服に挑戦するなど、グレイヘアは自分らしく生きていくきっかけなのだ、と気付かされます。
訳…浜崎絵梨 監修…国分良成『図解 はじめて学ぶみんなの政治』
2019年4月20日 おすすめの本一覧
「政治」と聞くと堅苦しいイメージがありますが、この本は誰もが政治に興味を持ちやすいように作られています。
フルカラーで、漫画を豊富に使い、子どもにも分かりやすい表現で政治について教えてくれます。
例えば、民主制・共和制・絶対君主制といった様々な政治の成り立ちとメリット・デメリット、選挙権を勝ち取るまでの歴史と投票の仕組み、世界中で実際に今起きている現代の社会問題(戦争、テロリズム、移民、難民、差別、地球環境への責任など)についても解説。
もっと早くこの本が出版されていたら良かったのに!
学生時代のうちにこの本と出会えていたら、わたしはもっと世界史や政治経済の授業に楽しく取り組めたのに。
フルカラーで、漫画を豊富に使い、子どもにも分かりやすい表現で政治について教えてくれます。
例えば、民主制・共和制・絶対君主制といった様々な政治の成り立ちとメリット・デメリット、選挙権を勝ち取るまでの歴史と投票の仕組み、世界中で実際に今起きている現代の社会問題(戦争、テロリズム、移民、難民、差別、地球環境への責任など)についても解説。
もっと早くこの本が出版されていたら良かったのに!
学生時代のうちにこの本と出会えていたら、わたしはもっと世界史や政治経済の授業に楽しく取り組めたのに。
著…荻上チキ、内田良『ブラック校則 理不尽な苦しみの現実』
2019年4月13日 おすすめの本一覧
生まれつき髪が茶色いのに髪を黒く染めさせられる、日焼け止めクリームを塗るのを禁じられる、心の性別への配慮がなく制服を制限される…、そんな納得しがたい校則についての本。
わたしも小・中・高校で、こうした校則に苦しんできました。
わたしはもともと地毛がやや茶色いので、生徒指導の先生から「染めるのは校則違反だ!」と言われて、「地毛です」と言い続けていました。
「子どもの頃の写真を持って来なさい」と指示され、何度持って行ったことか。
写真を見せたら見せたで、「子どもの頃は髪が茶色くて、後から黒くなる人もいる。写真は証拠にならない。黒く染めなさい」と言われて、じゃあどうせーっちゅーねん!と困ったこともありました。
日焼け止めクリーム塗布禁止も意味不明。
日焼け止めは化粧と同じだ、という考え方らしいけれど、一度浴びてしまった紫外線によるダメージを0にすることは出来ません。
体育の授業、屋外での行事などで蓄積されたダメージは大人になってからシミ・シワ・たるみとして現れるし、皮膚ガンなどのリスクもあります。
一番納得出来ないのは制服の制限。
わたしの同級生の中に、体の性別は男性だけれど心は女性、という子がいて、その子はスカートをはきたがっていたけれど、「男だからダメだ」と言われてガックリきていたし、髪の毛を伸ばしたかったけれど髪を長くすると先生から「男子はみんな丸刈りだ!」と怒られていました。
その逆で、体の性別は女性だけれど心は男性、という子は、スカートをはくのが嫌で、仕方なくスカートの下にジャージをはいていたけれど、それも先生に怒られていました。
もう平成も終わるというのに、いまだにこうした校則が世の中に残っていることに驚かされます。
改善してきている学校もあるけれど…。
子どもたちにはこれ以上同じ思いをさせたくないです。
わたしも小・中・高校で、こうした校則に苦しんできました。
わたしはもともと地毛がやや茶色いので、生徒指導の先生から「染めるのは校則違反だ!」と言われて、「地毛です」と言い続けていました。
「子どもの頃の写真を持って来なさい」と指示され、何度持って行ったことか。
写真を見せたら見せたで、「子どもの頃は髪が茶色くて、後から黒くなる人もいる。写真は証拠にならない。黒く染めなさい」と言われて、じゃあどうせーっちゅーねん!と困ったこともありました。
日焼け止めクリーム塗布禁止も意味不明。
日焼け止めは化粧と同じだ、という考え方らしいけれど、一度浴びてしまった紫外線によるダメージを0にすることは出来ません。
体育の授業、屋外での行事などで蓄積されたダメージは大人になってからシミ・シワ・たるみとして現れるし、皮膚ガンなどのリスクもあります。
一番納得出来ないのは制服の制限。
わたしの同級生の中に、体の性別は男性だけれど心は女性、という子がいて、その子はスカートをはきたがっていたけれど、「男だからダメだ」と言われてガックリきていたし、髪の毛を伸ばしたかったけれど髪を長くすると先生から「男子はみんな丸刈りだ!」と怒られていました。
その逆で、体の性別は女性だけれど心は男性、という子は、スカートをはくのが嫌で、仕方なくスカートの下にジャージをはいていたけれど、それも先生に怒られていました。
もう平成も終わるというのに、いまだにこうした校則が世の中に残っていることに驚かされます。
改善してきている学校もあるけれど…。
子どもたちにはこれ以上同じ思いをさせたくないです。
著…一田和樹『ネットの危険を正しく知る ファミリー・セキュリティ読本』
2019年4月13日 おすすめの本一覧
ネットバンキングの口座などからお金を奪われたり、なりすましによって社会的立場を危うくされたり、サイバー犯罪の加害者に仕立て上げられたり…。
「自分の身にそんなことが起きるはずがない」と根拠のない自信を持ってしまっている人に、この本をお勧めしたいです。
ネットの世界は無法地帯。
誰かが責任を持って安全管理を行っているわけではなく、何が起きてもおかしくありません。
わたしはこの本の第2章を特に興味深く読みました。
第2章には、SNSや動画共有サービスを利用する際の注意点が書かれています。
「気がつくと近所の人たちに、昨晩の献立から見ていたテレビ、最近の心配事や夫婦げんかの理由まで知られているということになりかねません。近所の人だけでなく、空き巣や犯罪者にも知られてしまいかねません。みなさんのお子さんが、食事中スマホをいじっていたら、それは生放送しているのかもしれません」
(P63から抜粋)
そう考えるとゾッとしますよね。
発信した情報を誰が目にするか分かりません。
旅行中だという情報をSNSに載せたら空き巣に「留守です」とわざわざ知らせるようなものだし、よく行くお店を動画で紹介したらストーカーに待ち伏せされるかもしれません。
また、わたしは先日繁華街を歩いていたら、一人で歩きながらスマホに向かって喋り続けている人を見かけました。
恐らく、動画撮影をして何らかの動画共有サイトにアップロードする、もしくは今まさに生放送配信中だったのかもしれませんが、注意力散漫になって危ないし、実際にその人は歩きながら他の人にぶつかっていたから、見ているこっちがハラハラしました。
そのまま車に轢かれたり、階段から落ちたりしたら危ないのに!
それに、動画に映り込みたくない人もいるから、不特定多数の人がいる場所での撮影はトラブルのもとにもなります。
もし撮影者本人が「後で編集して通行人の顔は消すよ」というつもりでも、そんなこと周りの人たちには分からないので、「お前、俺を撮っただろう!」と殴られたりするかも。
それに、もしかしたらストーカーや暴力の被害者がたまたま映ってしまって、加害者に居場所を特定されてしまうかも…。
自宅内で撮影する分には何があっても自己責任だけれど、屋外での撮影で不特定多数の他人を巻き込むのはやめて欲しいです。
「自分の身にそんなことが起きるはずがない」と根拠のない自信を持ってしまっている人に、この本をお勧めしたいです。
ネットの世界は無法地帯。
誰かが責任を持って安全管理を行っているわけではなく、何が起きてもおかしくありません。
わたしはこの本の第2章を特に興味深く読みました。
第2章には、SNSや動画共有サービスを利用する際の注意点が書かれています。
「気がつくと近所の人たちに、昨晩の献立から見ていたテレビ、最近の心配事や夫婦げんかの理由まで知られているということになりかねません。近所の人だけでなく、空き巣や犯罪者にも知られてしまいかねません。みなさんのお子さんが、食事中スマホをいじっていたら、それは生放送しているのかもしれません」
(P63から抜粋)
そう考えるとゾッとしますよね。
発信した情報を誰が目にするか分かりません。
旅行中だという情報をSNSに載せたら空き巣に「留守です」とわざわざ知らせるようなものだし、よく行くお店を動画で紹介したらストーカーに待ち伏せされるかもしれません。
また、わたしは先日繁華街を歩いていたら、一人で歩きながらスマホに向かって喋り続けている人を見かけました。
恐らく、動画撮影をして何らかの動画共有サイトにアップロードする、もしくは今まさに生放送配信中だったのかもしれませんが、注意力散漫になって危ないし、実際にその人は歩きながら他の人にぶつかっていたから、見ているこっちがハラハラしました。
そのまま車に轢かれたり、階段から落ちたりしたら危ないのに!
それに、動画に映り込みたくない人もいるから、不特定多数の人がいる場所での撮影はトラブルのもとにもなります。
もし撮影者本人が「後で編集して通行人の顔は消すよ」というつもりでも、そんなこと周りの人たちには分からないので、「お前、俺を撮っただろう!」と殴られたりするかも。
それに、もしかしたらストーカーや暴力の被害者がたまたま映ってしまって、加害者に居場所を特定されてしまうかも…。
自宅内で撮影する分には何があっても自己責任だけれど、屋外での撮影で不特定多数の他人を巻き込むのはやめて欲しいです。
「家を片づけないといけない」と義務的になるのではなく「家を整えられる」ことを楽しもうという本。
まず、お気に入りの場所を「S席」と捉えて、S席がより寛げる場所になるよう整えることで、身の回りを整えるクセを身につけていこうという内容。
「S席」がダイニングなのか、リビングなのか、キッチンなのか、ベッドルームなのか、といった場所別の整え方が書かれていて、すぐ参考になります。
なお、わたしのS席はバスルーム。
日本は湿気が多いので、カラリとした気候の外国のバスルームのように色んな物を飾るのには向いていないので、最低限のものしか置けないそうです。
確かに、例えばシャンプーのボトルをバスルームに置きっ放しにしていると、いつの間にかどうしてもボトルの底がヌルヌルしちゃいますものね…。
わたしも早速、滅多に使わないものはバスルームから出してみました。
また、映画『アメリ』の部屋はヒントが沢山あり、インテリアや色使いが必見…と書かれているのを読んで、久しぶりに『アメリ』が観たくなりました。
アメリのお部屋は、決して物が少ないわけではないけれど、色使いが綺麗で、さりげなくアートを取り入れたり、好きな物に囲まれた、魅力的なお部屋ですよね。
まず、お気に入りの場所を「S席」と捉えて、S席がより寛げる場所になるよう整えることで、身の回りを整えるクセを身につけていこうという内容。
「S席」がダイニングなのか、リビングなのか、キッチンなのか、ベッドルームなのか、といった場所別の整え方が書かれていて、すぐ参考になります。
なお、わたしのS席はバスルーム。
日本は湿気が多いので、カラリとした気候の外国のバスルームのように色んな物を飾るのには向いていないので、最低限のものしか置けないそうです。
確かに、例えばシャンプーのボトルをバスルームに置きっ放しにしていると、いつの間にかどうしてもボトルの底がヌルヌルしちゃいますものね…。
わたしも早速、滅多に使わないものはバスルームから出してみました。
また、映画『アメリ』の部屋はヒントが沢山あり、インテリアや色使いが必見…と書かれているのを読んで、久しぶりに『アメリ』が観たくなりました。
アメリのお部屋は、決して物が少ないわけではないけれど、色使いが綺麗で、さりげなくアートを取り入れたり、好きな物に囲まれた、魅力的なお部屋ですよね。
世の中に蔓延る様々な悪質商法の手口について、引っかかってしまう前に知っておこう、という本。
「自分は騙されない」と根拠のない自信を持っている人にこそ読んでほしいです。
「自分は若いから大丈夫」「一人暮らしではないから狙われない」「自分にはお金が無いから業者は寄って来ない」などと油断するのは大きな間違い。
人を騙そうとする人は、ちょっとした不安や、「貰わなきゃ損」「買わなきゃ損」といった欲に、あの手この手でつけこんでくるから。
見るからに怪しい人ではなく、公的機関や優しそうな人を装って信用させたりするから、尚更たちが悪い。
「無料で点検する」と言って入り込んで高額な料金を請求したり、インチキな検査をして見せて「あなたの体が心配」と親身になっている風を装って健康食品まがいのものを売りつけたり。
なお、この本は、「騙された!」と気付いても、恥ずかしくて、詐欺被害にあったと誰にも打ち明けられない人の心理にも触れています。
周りの人が被害にあった時、「騙される方が悪い」などと責めずに、力になってあげられる人が増えて、また、騙される人の数も減りますように。
本当は、騙す人の数が減れば一番良いのですが、残念ながら世の中にはけしからん輩が沢山いますから…、まずは「騙されない」ことを目指しましょう!
「自分は騙されない」と根拠のない自信を持っている人にこそ読んでほしいです。
「自分は若いから大丈夫」「一人暮らしではないから狙われない」「自分にはお金が無いから業者は寄って来ない」などと油断するのは大きな間違い。
人を騙そうとする人は、ちょっとした不安や、「貰わなきゃ損」「買わなきゃ損」といった欲に、あの手この手でつけこんでくるから。
見るからに怪しい人ではなく、公的機関や優しそうな人を装って信用させたりするから、尚更たちが悪い。
「無料で点検する」と言って入り込んで高額な料金を請求したり、インチキな検査をして見せて「あなたの体が心配」と親身になっている風を装って健康食品まがいのものを売りつけたり。
なお、この本は、「騙された!」と気付いても、恥ずかしくて、詐欺被害にあったと誰にも打ち明けられない人の心理にも触れています。
周りの人が被害にあった時、「騙される方が悪い」などと責めずに、力になってあげられる人が増えて、また、騙される人の数も減りますように。
本当は、騙す人の数が減れば一番良いのですが、残念ながら世の中にはけしからん輩が沢山いますから…、まずは「騙されない」ことを目指しましょう!
著…北健一『電通事件 なぜ死ぬまで働かなければならないのか』
2019年2月3日 おすすめの本一覧
高橋まつりさんが身を投げたこと、そして、その遺書の内容は、今もなお衝撃的です。
自殺というと、よく、「命を粗末にして…」と眉をひそめる人や、「職場から逃げれば済んだのに」と言う人がいます。
ところが、高橋さんの職場での異常な労働状況を知ると、高橋さんが死を選んだというより、死に追いやられたのだ、ということがうかがえます。
ずーっと職場で働いていたのですから。
ずーっと。
ずーっと…。
睡眠時間はごくわずか。
休息を取れないと、人間の心のバランスはあっという間に崩れます。
真面目で努力家であればあるほど、職場からバックレるなんてことは出来ず、つい頑張ってしまいます。
頑張って、頑張って、なおも職場の人間からは罵倒され、更なる残業を求められ…。
高橋さんの遺書には「大好きで大切なお母さん」「ありがとう」「お母さん、自分を責めないでね。最高のお母さんだから」という言葉が綴られています。
極限状態になろうとも、最後の最後まで家族への気遣いを忘れなかった高橋さんの心情を想像すると泣けてきます。
ところが、高橋さんに限らず、死に追いやられる労働者は沢山います。
この本は、電通も含めて、過酷な労働を強いる職場の数々、その職場環境が労働者に与える心身への危険について訴えています。
ある人がインタビューで語った、
「これから人口が減っていくのに、このサービスと社会のあり方を続けてたら、そりゃ破綻しますよね」
(P59から抜粋)
という言葉が読み手の心に刺さります。
がむしゃらに頑張る「誰か」に過酷な量の仕事をさせてどうにか成り立ってきた社会が、その「誰か」の数が少なくなったら、立ち行かなくなるのは明らか…。
自殺というと、よく、「命を粗末にして…」と眉をひそめる人や、「職場から逃げれば済んだのに」と言う人がいます。
ところが、高橋さんの職場での異常な労働状況を知ると、高橋さんが死を選んだというより、死に追いやられたのだ、ということがうかがえます。
ずーっと職場で働いていたのですから。
ずーっと。
ずーっと…。
睡眠時間はごくわずか。
休息を取れないと、人間の心のバランスはあっという間に崩れます。
真面目で努力家であればあるほど、職場からバックレるなんてことは出来ず、つい頑張ってしまいます。
頑張って、頑張って、なおも職場の人間からは罵倒され、更なる残業を求められ…。
高橋さんの遺書には「大好きで大切なお母さん」「ありがとう」「お母さん、自分を責めないでね。最高のお母さんだから」という言葉が綴られています。
極限状態になろうとも、最後の最後まで家族への気遣いを忘れなかった高橋さんの心情を想像すると泣けてきます。
ところが、高橋さんに限らず、死に追いやられる労働者は沢山います。
この本は、電通も含めて、過酷な労働を強いる職場の数々、その職場環境が労働者に与える心身への危険について訴えています。
ある人がインタビューで語った、
「これから人口が減っていくのに、このサービスと社会のあり方を続けてたら、そりゃ破綻しますよね」
(P59から抜粋)
という言葉が読み手の心に刺さります。
がむしゃらに頑張る「誰か」に過酷な量の仕事をさせてどうにか成り立ってきた社会が、その「誰か」の数が少なくなったら、立ち行かなくなるのは明らか…。
病気による低身長で悩む人、美容的な理由で背を高くしたい人、身長制限のある職業への挑戦権を得たい人…。
これは、そうした様々な理由で「身長を伸ばしたい!」と願う人なら一度は耳にしたことがあるであろう「イリザロフ法」の本。
折れた骨が元に戻ろうとする力を利用して身長を伸ばす治療法です。
人工的な骨折を行い、ワイヤーと固定器を使用するのが特徴。
わたし自身、成人女性の平均身長より小柄なので、同僚や上司などから「小学生」「今着てるのは子供服?」と馬鹿にされることが多く、悔しい思いをしているため、この本を読んでみました。
症例の術前・術後の写真や、具体的な手術内容、リハビリ内容も載っているので、イメージしやすいです。
「1センチ延ばすのにだいたい60日かかります」
(P133から抜粋)
と、無理やり人体に手を加えるから仕方ないとはいえ、かなり必要日数がかかることや(髄内釘を打てば治療期間短縮は可能なようですが…)、
骨が順調に延びても概ね10センチ程度までのようで、しかも数百万円+治療中の生活費等もかかるため、メリットとデメリットを考慮し、わたしにとってはデメリットの方が上回ったので、残念ながらわたしは断念することにしました。
となると、成長期をとうに過ぎたわたしの身長が伸びることは無いので、今後も「ちんちくりん」等とからかわれ続けることになります。
他人の口を塞ぐことは出来ないので、「せめて自分自身は他人の身体的特徴をからかわない人間になろう」と決意するに至りました。
「チビ」に限らず、世の中には「ブサイク」「デブ」「ハゲ」などなど、他人の身体的特徴をからかう言葉が沢山あります。
言う側は「イジっているだけ」「ただの冗談」のつもりでも、からかわれる側は傷つきますから、せめて自分は言わないようにしたいです。
これは、そうした様々な理由で「身長を伸ばしたい!」と願う人なら一度は耳にしたことがあるであろう「イリザロフ法」の本。
折れた骨が元に戻ろうとする力を利用して身長を伸ばす治療法です。
人工的な骨折を行い、ワイヤーと固定器を使用するのが特徴。
わたし自身、成人女性の平均身長より小柄なので、同僚や上司などから「小学生」「今着てるのは子供服?」と馬鹿にされることが多く、悔しい思いをしているため、この本を読んでみました。
症例の術前・術後の写真や、具体的な手術内容、リハビリ内容も載っているので、イメージしやすいです。
「1センチ延ばすのにだいたい60日かかります」
(P133から抜粋)
と、無理やり人体に手を加えるから仕方ないとはいえ、かなり必要日数がかかることや(髄内釘を打てば治療期間短縮は可能なようですが…)、
骨が順調に延びても概ね10センチ程度までのようで、しかも数百万円+治療中の生活費等もかかるため、メリットとデメリットを考慮し、わたしにとってはデメリットの方が上回ったので、残念ながらわたしは断念することにしました。
となると、成長期をとうに過ぎたわたしの身長が伸びることは無いので、今後も「ちんちくりん」等とからかわれ続けることになります。
他人の口を塞ぐことは出来ないので、「せめて自分自身は他人の身体的特徴をからかわない人間になろう」と決意するに至りました。
「チビ」に限らず、世の中には「ブサイク」「デブ」「ハゲ」などなど、他人の身体的特徴をからかう言葉が沢山あります。
言う側は「イジっているだけ」「ただの冗談」のつもりでも、からかわれる側は傷つきますから、せめて自分は言わないようにしたいです。
著…阿久津直記『練習しないで、字がうまくなる! 15分でガラリと変わる上達法』
2018年12月23日 おすすめの本一覧
綺麗な字を書けるようになるまでの道のりは大変。
けれど、綺麗な字の特徴を意識出来れば、「綺麗」までいかなくても、「うまい」字に見せることはすぐに可能。
ポイントは、起筆、トメ、ハライ、線の太さの変化といった毛筆らしいメリハリや、フォントのようにブレのない一定の字を意識すること。
逆に、どんなに形の良い字でも、これらが出来ていなければ美しく見えないのだそう。
わたしはひらがながどうもうまく書けないので、
「ひらがなはハネを次画の始点に向けること、そして縦の線をしっかりと伸ばすことを意識するだけで美しくなります」
「P124から抜粋)
という方法を取り入れてみます。
けれど、綺麗な字の特徴を意識出来れば、「綺麗」までいかなくても、「うまい」字に見せることはすぐに可能。
ポイントは、起筆、トメ、ハライ、線の太さの変化といった毛筆らしいメリハリや、フォントのようにブレのない一定の字を意識すること。
逆に、どんなに形の良い字でも、これらが出来ていなければ美しく見えないのだそう。
わたしはひらがながどうもうまく書けないので、
「ひらがなはハネを次画の始点に向けること、そして縦の線をしっかりと伸ばすことを意識するだけで美しくなります」
「P124から抜粋)
という方法を取り入れてみます。
服を安く買えたけれど、お洒落に見えないから結局着なかった、なんて経験はありませんか?
この本は、そんな風にお金を無駄にしないための本。
透ける生地は安っぽく見えるので避ける、といった服選びのポイントから、お洒落に見える=スタイルが良く見える、ということで、ストール、帽子、時計、アクセサリーといった小物を取り入れて視線を集める方法、こなれ感を出せる着崩し方が紹介されています。
アクセサリーに関しては、特に耳を飾るだけでグッと華やかになるから不思議。
安いものでも良いので、ピアス、イヤリング、ノンホールピアスのどれかは着けたいです。
また、この本の写真を見ていてわたしが思うのは、ヘアスタイルも重要な要素だということ。
せっかく素敵なコーディネートをしていても、首から上が残念なら総合点が満点になることはありません。
顔立ちは簡単には変えられないけれど、ちょっとヘアアレンジを加えるだけで雰囲気がガラッと変わるから、「面倒くさいから今日は髪の毛をドライヤーで適当に乾かしてブラシでといただけで外出して来ました」なんてことがないよう、面倒な時でもせめてブローだけでも丁寧にすることを徹底したいです。
また、「シワのある服は、「自分を安く見せる」と知る」と書かれたP66〜67は、プチプラ服に限らず参考になります。
せっかく高いお金を出して買った服でも、シワシワ、ヨレヨレだったらダサいし、清潔感が無いですよね。
シワだけでなく、毛玉のある服も自分をだらしなく見せる原因になるので、毛玉カットも欠かせませんね。
この本は、そんな風にお金を無駄にしないための本。
透ける生地は安っぽく見えるので避ける、といった服選びのポイントから、お洒落に見える=スタイルが良く見える、ということで、ストール、帽子、時計、アクセサリーといった小物を取り入れて視線を集める方法、こなれ感を出せる着崩し方が紹介されています。
アクセサリーに関しては、特に耳を飾るだけでグッと華やかになるから不思議。
安いものでも良いので、ピアス、イヤリング、ノンホールピアスのどれかは着けたいです。
また、この本の写真を見ていてわたしが思うのは、ヘアスタイルも重要な要素だということ。
せっかく素敵なコーディネートをしていても、首から上が残念なら総合点が満点になることはありません。
顔立ちは簡単には変えられないけれど、ちょっとヘアアレンジを加えるだけで雰囲気がガラッと変わるから、「面倒くさいから今日は髪の毛をドライヤーで適当に乾かしてブラシでといただけで外出して来ました」なんてことがないよう、面倒な時でもせめてブローだけでも丁寧にすることを徹底したいです。
また、「シワのある服は、「自分を安く見せる」と知る」と書かれたP66〜67は、プチプラ服に限らず参考になります。
せっかく高いお金を出して買った服でも、シワシワ、ヨレヨレだったらダサいし、清潔感が無いですよね。
シワだけでなく、毛玉のある服も自分をだらしなく見せる原因になるので、毛玉カットも欠かせませんね。
著…上野正彦『死体が教えてくれたこと』
2018年11月23日 おすすめの本一覧
誰かに殺された人が幽霊となって「自分は事故死でも病死でもなく殺されたんだ!」と言えれば良いのですが、まさに死人に口無し。
物言えぬ沢山の遺体を解剖し、死者の声なき声、すなわち死因を明らかにしてきた元監察医・上野先生。
先生の著書をわたしはこれまで何冊も読んできたのですが、この本は10代の若者に向けて書かれており、他の著書と比べるとかなり平易な文章なので、「上野先生の本って沢山出版されているから、どれから読めば良いのか分からない」という人におすすめです。
他の著書と違って、先生のプライベートな心情が吐露されているのもこの本の特徴です。
家族の死、ペットの死…。
どんなに遺体と向き合ってきた方でも、死に慣れるということは無くて、大切な人を見送る時はとても辛いということが伝わってきます。
いじめられて「死にたい」と思い詰めている子どもへのメッセージも書かれています。
今まさに苦しんでいる子は、本を開くのも辛いと思うけれど、どうか第4章のP153〜154だけでも読んで欲しいです。
「生きて欲しい」と書かれているから。
死にたい人などいない。
先生のおっしゃる通りだと思います。
いじめに限らず、様々な理由で自ら死を選ぼうとする大人にも読んで欲しいです。
わたし自身も今まで何度も死のうと思ったし、いまだに時々死んでしまおうと思うことがあるけれど、わたしが生き続けることで何かの形で少しでも誰かの役に立てる可能性があるかもしれないと思い、まだ生者の側に踏み止まっています。
この本に、
「退職してから、もう何十年もたった。監察医たちはあいかわらずいそがしく飛びまわっている。重い責任のある仕事をうけおってくれていることを、心強く思う。だがその反面、私は思うのだ。監察医がいらない世の中になったら、どんなにかいいだろうと。それは犯罪で亡くなったり、せつない理由で死んだりする人たちがいなくなるということだ。そんな世の中になったら、なんともうれしいことだ」
(P187から抜粋)
と書かれているのも印象的でした。
もう誰も、殺したり、殺されたり、自ら死んだりしない世の中にしていきたいです。
そんな先生はもう90歳になられるそうで、
かつて取材に来た記者に言われたという、
「先生ほど死者の人権を大切に守ってきた人はいません。もしも先生があの世に行ったときには、お世話になった2万人の死者たちが、花束を持って出迎えてくれるでしょう」
(P192から抜粋)
という言葉にしみじみしていたようですが、わたしは本当にそうなるような気がします。
残念ながら、誰もが死亡率は100%。
先生だって例外ではありませんから。
いつか彼岸で会いたい人に会えますように。
物言えぬ沢山の遺体を解剖し、死者の声なき声、すなわち死因を明らかにしてきた元監察医・上野先生。
先生の著書をわたしはこれまで何冊も読んできたのですが、この本は10代の若者に向けて書かれており、他の著書と比べるとかなり平易な文章なので、「上野先生の本って沢山出版されているから、どれから読めば良いのか分からない」という人におすすめです。
他の著書と違って、先生のプライベートな心情が吐露されているのもこの本の特徴です。
家族の死、ペットの死…。
どんなに遺体と向き合ってきた方でも、死に慣れるということは無くて、大切な人を見送る時はとても辛いということが伝わってきます。
いじめられて「死にたい」と思い詰めている子どもへのメッセージも書かれています。
今まさに苦しんでいる子は、本を開くのも辛いと思うけれど、どうか第4章のP153〜154だけでも読んで欲しいです。
「生きて欲しい」と書かれているから。
死にたい人などいない。
先生のおっしゃる通りだと思います。
いじめに限らず、様々な理由で自ら死を選ぼうとする大人にも読んで欲しいです。
わたし自身も今まで何度も死のうと思ったし、いまだに時々死んでしまおうと思うことがあるけれど、わたしが生き続けることで何かの形で少しでも誰かの役に立てる可能性があるかもしれないと思い、まだ生者の側に踏み止まっています。
この本に、
「退職してから、もう何十年もたった。監察医たちはあいかわらずいそがしく飛びまわっている。重い責任のある仕事をうけおってくれていることを、心強く思う。だがその反面、私は思うのだ。監察医がいらない世の中になったら、どんなにかいいだろうと。それは犯罪で亡くなったり、せつない理由で死んだりする人たちがいなくなるということだ。そんな世の中になったら、なんともうれしいことだ」
(P187から抜粋)
と書かれているのも印象的でした。
もう誰も、殺したり、殺されたり、自ら死んだりしない世の中にしていきたいです。
そんな先生はもう90歳になられるそうで、
かつて取材に来た記者に言われたという、
「先生ほど死者の人権を大切に守ってきた人はいません。もしも先生があの世に行ったときには、お世話になった2万人の死者たちが、花束を持って出迎えてくれるでしょう」
(P192から抜粋)
という言葉にしみじみしていたようですが、わたしは本当にそうなるような気がします。
残念ながら、誰もが死亡率は100%。
先生だって例外ではありませんから。
いつか彼岸で会いたい人に会えますように。
今や、いつ誰がどんながんを発症してもおかしくない時代。
この本は、「化学療法で眉毛が抜けてしまいました。上手に描く方法はありますか?」といった、がん治療中の外見の悩みに特化した本。
タイトルに「女性の」とある通り、女性が発症しやすいがんについての内容が中心ですが、がん治療による肌荒れや脱毛に悩む男性にも参考になると思いますし、がんに限らず様々な病気や怪我によって以前とは外見が変わってしまった人にもおすすめしたい本です。
ウィッグ、スキンケア、ネイルケア、手術痕や痣などを目立たなくするメイク、胸を切除したあとをカバーするパッド、エピテーゼ(義手、義足など)を使って、自分らしい見た目を取り戻そうというアイディアが紹介されています。
「一度きれいになると、不思議なもので、「ちゃんとケアしなきゃ」という気持ちになりました」
「見た目が整うと、自分がうれしかったのはもちろんですが、家族や周りも喜んでくれました」
(P134から抜粋)
という患者さんの声が素敵。
病気や怪我で治療中の人に限らず、綺麗になることって生きる希望に繋がりますよね。
この本は、「化学療法で眉毛が抜けてしまいました。上手に描く方法はありますか?」といった、がん治療中の外見の悩みに特化した本。
タイトルに「女性の」とある通り、女性が発症しやすいがんについての内容が中心ですが、がん治療による肌荒れや脱毛に悩む男性にも参考になると思いますし、がんに限らず様々な病気や怪我によって以前とは外見が変わってしまった人にもおすすめしたい本です。
ウィッグ、スキンケア、ネイルケア、手術痕や痣などを目立たなくするメイク、胸を切除したあとをカバーするパッド、エピテーゼ(義手、義足など)を使って、自分らしい見た目を取り戻そうというアイディアが紹介されています。
「一度きれいになると、不思議なもので、「ちゃんとケアしなきゃ」という気持ちになりました」
「見た目が整うと、自分がうれしかったのはもちろんですが、家族や周りも喜んでくれました」
(P134から抜粋)
という患者さんの声が素敵。
病気や怪我で治療中の人に限らず、綺麗になることって生きる希望に繋がりますよね。
不整脈・心房細動がわかる本 脈の乱れが気になる人へ
2018年11月12日 おすすめの本一覧
友人が期外収縮で悩んでいるので、その不安を少しでも分かち合いたいと思ってわたしはこの本を読んでみました。
脈が抜ける・飛ぶ、心臓が通常より大きくドキンッとする、脈が不規則で触れにくい、脈が速い、脈が弱い・遅い、といった「脈の乱れ」に関する本です。
正常の範囲内での脈の乱れと、病院で検査・治療の必要がある症状の違いを、イラストを豊富に使って分かりやすく説明してくれています。
期外収縮だけなら基本的には命を脅かす心配はなく、基本的には治療は不要、と書かれていて、安心しました。
しかし、実は別の症状が潜んでいるかもしれないので、定期的な検診は必要ですね。
ひとまず友人は漢方薬を飲み始めました。
それにしても、心臓って偉いですよね。
ぼんやりしている時も、眠っている時も、心臓は決して休まず常に動き続けてくれていて有り難いなあ…と、わたしはこの本を読みながらしみじみ感じました。
それは心臓に限らず、どの臓器や組織にも言えることだけれど。
残念ながら、命のあるうちは心臓にお休みをあげられないので、せめて心臓が元気に働きやすいよう労わる生活習慣を心がけたいです。
また、不整脈が原因で脳梗塞を引き起こすこともあるので、P21掲載の脳梗塞の発症サイン「FAST」をしっかり覚えておきたいです。
Face…顔に現れるサイン。半身マヒの現れのひとつ。笑顔を作ろうとしたり、「イー」と発音しようとしたりしても、片側の口角が上がらない。
Arm…腕に現れるサイン。両腕をまっすぐ前に伸ばしたままの状態を維持できず、片方の腕だけが下がってきてしまう。
Speech…言葉に現れるサイン。簡単な短い文でも舌がもつれて話せない。話そうとしても言葉が出てこない。
Time…一刻も早く! すぐに119に連絡。救急車で受診を。
(P21から抜粋)
自分自身や周囲の人たちが脳梗塞で命を落としたり、後遺症に悩んだりしないためにも、FASTを色んな方々に知っていただきたいです。
脈が抜ける・飛ぶ、心臓が通常より大きくドキンッとする、脈が不規則で触れにくい、脈が速い、脈が弱い・遅い、といった「脈の乱れ」に関する本です。
正常の範囲内での脈の乱れと、病院で検査・治療の必要がある症状の違いを、イラストを豊富に使って分かりやすく説明してくれています。
期外収縮だけなら基本的には命を脅かす心配はなく、基本的には治療は不要、と書かれていて、安心しました。
しかし、実は別の症状が潜んでいるかもしれないので、定期的な検診は必要ですね。
ひとまず友人は漢方薬を飲み始めました。
それにしても、心臓って偉いですよね。
ぼんやりしている時も、眠っている時も、心臓は決して休まず常に動き続けてくれていて有り難いなあ…と、わたしはこの本を読みながらしみじみ感じました。
それは心臓に限らず、どの臓器や組織にも言えることだけれど。
残念ながら、命のあるうちは心臓にお休みをあげられないので、せめて心臓が元気に働きやすいよう労わる生活習慣を心がけたいです。
また、不整脈が原因で脳梗塞を引き起こすこともあるので、P21掲載の脳梗塞の発症サイン「FAST」をしっかり覚えておきたいです。
Face…顔に現れるサイン。半身マヒの現れのひとつ。笑顔を作ろうとしたり、「イー」と発音しようとしたりしても、片側の口角が上がらない。
Arm…腕に現れるサイン。両腕をまっすぐ前に伸ばしたままの状態を維持できず、片方の腕だけが下がってきてしまう。
Speech…言葉に現れるサイン。簡単な短い文でも舌がもつれて話せない。話そうとしても言葉が出てこない。
Time…一刻も早く! すぐに119に連絡。救急車で受診を。
(P21から抜粋)
自分自身や周囲の人たちが脳梗塞で命を落としたり、後遺症に悩んだりしないためにも、FASTを色んな方々に知っていただきたいです。
東村アキコ先生の漫画『即席ビジンのつくりかた』4話目に登場した「エッフェルドゥース」が気になりつつも、「1本 8,500円(税込)かぁ…。買えないな…。自分の指で顔のマッサージを続けよう」と溜息をついていたわたしが偶然書店に立ち寄ったところ、なんと!
平積みされているではありませんか、「エッフェルドゥース」のミニチュア版が付録となった本が!
けしからん、いつの間に発売されていたのだ!
2,200円(税別)で!
わたしが家計簿とにらめっこした時間を返したまえ!
↑なぜさっきから強気な口調?
ミニチュア版の名前は「ビバリー」。
…美容のための刺さない鍼、略して美鍼=ビバリーなのかも…?
いやまさか…。
そんなダジャレなわけ…あるのかな?
何でもかんでも付録として手に入る有り難い時代ですね、ほんと。
雑誌も、もはや雑誌を買うのか付録を買うのか分からないくらい豪華な付録が付いてきて当たり前になりましたし、出版業界も苦戦しつつも頑張っていて、とにかく売るために必死です。
さて、この本は(ページ数が少ないので本というより冊子ですが)、ビバリーの使用方法を掲載しています。
頭皮、眉頭周辺、顎、ほうれい線、センターポイント(目の下の頬骨が出ているところ)、首の後ろといった、たるみ・むくみ・シワに影響するところのコリをビバリーでどうほぐしていくかが写真付きで紹介されています。
洗顔後にジェルかクリームを塗ってから使います。
エッフェル塔をイメージした金色のデザインで、見た目が可愛いので、ビバリーを持つだけでテンションが上がります。
※ただし、金属ですので、残念ながら金属アレルギーの方は使えません。
指先ではなかなか把握しきれない細かい部分の詰まりが、ビバリーを通してだと「あっ!ここにゴリゴリする感じがある! さてはここにリンパが詰まってるな!」と分かりやすいので、マッサージしていて楽しくてつい夢中になってしまうため、やり過ぎて筋肉や神経を傷つけないように注意。
平積みされているではありませんか、「エッフェルドゥース」のミニチュア版が付録となった本が!
けしからん、いつの間に発売されていたのだ!
2,200円(税別)で!
わたしが家計簿とにらめっこした時間を返したまえ!
↑なぜさっきから強気な口調?
ミニチュア版の名前は「ビバリー」。
…美容のための刺さない鍼、略して美鍼=ビバリーなのかも…?
いやまさか…。
そんなダジャレなわけ…あるのかな?
何でもかんでも付録として手に入る有り難い時代ですね、ほんと。
雑誌も、もはや雑誌を買うのか付録を買うのか分からないくらい豪華な付録が付いてきて当たり前になりましたし、出版業界も苦戦しつつも頑張っていて、とにかく売るために必死です。
さて、この本は(ページ数が少ないので本というより冊子ですが)、ビバリーの使用方法を掲載しています。
頭皮、眉頭周辺、顎、ほうれい線、センターポイント(目の下の頬骨が出ているところ)、首の後ろといった、たるみ・むくみ・シワに影響するところのコリをビバリーでどうほぐしていくかが写真付きで紹介されています。
洗顔後にジェルかクリームを塗ってから使います。
エッフェル塔をイメージした金色のデザインで、見た目が可愛いので、ビバリーを持つだけでテンションが上がります。
※ただし、金属ですので、残念ながら金属アレルギーの方は使えません。
指先ではなかなか把握しきれない細かい部分の詰まりが、ビバリーを通してだと「あっ!ここにゴリゴリする感じがある! さてはここにリンパが詰まってるな!」と分かりやすいので、マッサージしていて楽しくてつい夢中になってしまうため、やり過ぎて筋肉や神経を傷つけないように注意。
著…渡邉みどり『美智子さまに学ぶエレガンス』
2018年11月5日 おすすめの本一覧
気品と清潔感溢れるロイヤルファッションにうっとり出来る本。
お出かけ先が華やかな場なのか、親善の場なのか、慰問の場なのか、という事情に合わせて装いを変えていらっしゃる美智子さま。
「美智子さまの場合、どういう色を着ていったら喜んでもらえるか、あるいは、悲しみに沈んでいる人には、どういう色を着ていったら、その悲しみを少しでもやわらげたり、慰めたりできるかと、ともかく相手のことばかりお考えになりました」
(P20から抜粋)
というのが素敵。
これから会う人の気持ちを想像してファッションを工夫することって、当たり前のようでいて、実は出来ない人が意外と多いものです。
専属デザイナーがいて、ドレスもお着物も、生地、縫製、染色、刺繍といった全てが超一流のお召し物をお使いの美智子さまのファッションを一般人が真似するのは困難ですが、会う人への気配りをする、という精神は是非真似したいです。
「釜石の避難所にいらしたときには、余震に見舞われました。ちょうど美智子さまは避難してきた女性とお話をされていたときでした。ガーンと響きわたる大きな音に、女性は思わず美智子さまの手を握ってしまったのです。美智子さまはその手にやさしくご自分の手を重ねられ、「落ち着いてください」と声をおかけになりました。「こうした地震は今でもあるのですね。怖いでしょう」美智子さまは、「大丈夫ですよ」と勇気づけられました。そののちも、陛下と美智子さまは被災者ひとりひとりの前で歩みを止め、人々を激励し続けられました」
(P100から抜粋)
というエピソードにわたしは心を打たれました。
美智子さまの、内側から発光しているかのようなあの美しさは、自分の心を相手の心に重ねて痛みを分かち合おうとする優しさからきているのかもしれません。
わたしもそういう女性になりたいです。
お出かけ先が華やかな場なのか、親善の場なのか、慰問の場なのか、という事情に合わせて装いを変えていらっしゃる美智子さま。
「美智子さまの場合、どういう色を着ていったら喜んでもらえるか、あるいは、悲しみに沈んでいる人には、どういう色を着ていったら、その悲しみを少しでもやわらげたり、慰めたりできるかと、ともかく相手のことばかりお考えになりました」
(P20から抜粋)
というのが素敵。
これから会う人の気持ちを想像してファッションを工夫することって、当たり前のようでいて、実は出来ない人が意外と多いものです。
専属デザイナーがいて、ドレスもお着物も、生地、縫製、染色、刺繍といった全てが超一流のお召し物をお使いの美智子さまのファッションを一般人が真似するのは困難ですが、会う人への気配りをする、という精神は是非真似したいです。
「釜石の避難所にいらしたときには、余震に見舞われました。ちょうど美智子さまは避難してきた女性とお話をされていたときでした。ガーンと響きわたる大きな音に、女性は思わず美智子さまの手を握ってしまったのです。美智子さまはその手にやさしくご自分の手を重ねられ、「落ち着いてください」と声をおかけになりました。「こうした地震は今でもあるのですね。怖いでしょう」美智子さまは、「大丈夫ですよ」と勇気づけられました。そののちも、陛下と美智子さまは被災者ひとりひとりの前で歩みを止め、人々を激励し続けられました」
(P100から抜粋)
というエピソードにわたしは心を打たれました。
美智子さまの、内側から発光しているかのようなあの美しさは、自分の心を相手の心に重ねて痛みを分かち合おうとする優しさからきているのかもしれません。
わたしもそういう女性になりたいです。
著…Eiko『どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法』
2018年10月24日 おすすめの本一覧
ランナーズ・ハイ、クライマーズ・ハイ、のような、開脚ハイを味わおう!という本。
高価な道具を買い揃えなくてもOK。
タオル、椅子、壁、ドアなど家庭にある物を使うストレッチが紹介されています。
体が硬い60代以上の人でも、たった4週間で、開脚して両肘を床にぺたっと付けられるようになるそうです。
羨ましい!
わたしも同じポーズをしてドヤ顔をしてみたい!
BeforeとAfterを見比べて、達成感を味わいたい!
この本自体も「開く」をとことん意識して作られており、まるで開脚しているみたいにパッと開ききれる製本をしてあるので、こういう茶目っ気が楽しいです。
わたしもこの本を参考にして、まずはタオルストレッチから始めてみます。
高価な道具を買い揃えなくてもOK。
タオル、椅子、壁、ドアなど家庭にある物を使うストレッチが紹介されています。
体が硬い60代以上の人でも、たった4週間で、開脚して両肘を床にぺたっと付けられるようになるそうです。
羨ましい!
わたしも同じポーズをしてドヤ顔をしてみたい!
BeforeとAfterを見比べて、達成感を味わいたい!
この本自体も「開く」をとことん意識して作られており、まるで開脚しているみたいにパッと開ききれる製本をしてあるので、こういう茶目っ気が楽しいです。
わたしもこの本を参考にして、まずはタオルストレッチから始めてみます。
書籍・雑誌・カタログ・CD・缶コーヒーといったあらゆる物の表紙、パッケージ、見返し、カバー、写真、文字組み、字形…。
身の回りの物たちは全てどこかの誰かがデザインしたものなのだ、と気づかされる本。
書籍は単行本と文庫とでデザインが変わることで同じ作品なのに新たなイメージで読めたりするし、缶コーヒーの「BOSS」も通常のボスから優しいボスに変わったりと色んな変化があって飽きさせません。
寒色系でクールにまとめるか、アースカラーでナチュラルに仕上げるか、それとも反対色でにぎやかにするか、といった色使いや、配置の仕方や写真の大きさを工夫して、緩急をつけたり、ゆったり読ませたり…。
イラストを使用するにしても、イラストのタッチやサイズで雰囲気がガラリと変わるし…。
材質や特殊印刷・特殊加工によってインパクトを与える世界も奥深いです。
デザインにまつわる技の多さ、凄さに圧倒されます。
身の回りの物たちは全てどこかの誰かがデザインしたものなのだ、と気づかされる本。
書籍は単行本と文庫とでデザインが変わることで同じ作品なのに新たなイメージで読めたりするし、缶コーヒーの「BOSS」も通常のボスから優しいボスに変わったりと色んな変化があって飽きさせません。
寒色系でクールにまとめるか、アースカラーでナチュラルに仕上げるか、それとも反対色でにぎやかにするか、といった色使いや、配置の仕方や写真の大きさを工夫して、緩急をつけたり、ゆったり読ませたり…。
イラストを使用するにしても、イラストのタッチやサイズで雰囲気がガラリと変わるし…。
材質や特殊印刷・特殊加工によってインパクトを与える世界も奥深いです。
デザインにまつわる技の多さ、凄さに圧倒されます。