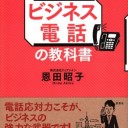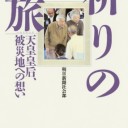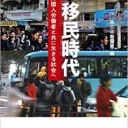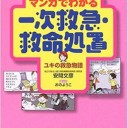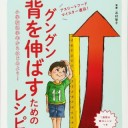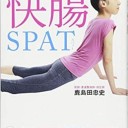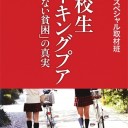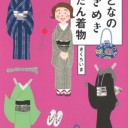著…河合香織『選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子』
2018年10月8日 おすすめの本一覧
ドキリとするタイトルの本です。
「選べなかった」、「誤診で生まれた子」…。
このタイトルを、該当する子どもが見たらどう思うのでしょうか…。
子ども自身に選択の余地は無く、生かすも殺すも親次第…。
しかし、親にとって出産は命がけの行為なのだし、親が子どもを一生養えるわけでもないのだから、もし選択できるなら健康な子どもを選んで生みたいという気持ちを誰にも責められません。
我が子に障害があっても産みたい人もいれば、我が子が障害で苦しむのを見たくない人もいるのです。
この本で紹介されているケースでは、もしお腹の中の子がダウン症なら諦めようと話して羊水検査を受けた親が、医師から異常なしと告げられたためそれを信じて出産したら、実は医師が羊水検査の結果を見誤っていてダウン症の子どもが生まれたそうです。
子どもはダウン症による一過性骨髄異常増殖症から肝不全、無気肺、敗血症を併発して生後約3か月半で病死。
親は医師と医院を提訴。
親としては、医師や医院を恨むとか、中絶を容認するとか、我が子が生まれたことを誤りだったと言いたいのではなく、ましてや障害がある人を生かすべきか否かといった優生学的思想を主張したいわけでもないのに、様々なメディアなどで親がバッシングされたそうです。
親としては、人間が人間を診断するのだから二度とミスが起こらないわけではないし、医師や医院が我が子をダウン症にしたわけではないと理解していますが、万が一またこんなことが起きたら医療はどうあるべきなのかを問い、そして何よりも、医師から我が子に「苦しい思いをさせてごめん」と謝って欲しかったのです。
お金の問題でも、保険の問題でも、裁判の問題でも無かった…。
「選べなかった」、「誤診で生まれた子」…。
このタイトルを、該当する子どもが見たらどう思うのでしょうか…。
子ども自身に選択の余地は無く、生かすも殺すも親次第…。
しかし、親にとって出産は命がけの行為なのだし、親が子どもを一生養えるわけでもないのだから、もし選択できるなら健康な子どもを選んで生みたいという気持ちを誰にも責められません。
我が子に障害があっても産みたい人もいれば、我が子が障害で苦しむのを見たくない人もいるのです。
この本で紹介されているケースでは、もしお腹の中の子がダウン症なら諦めようと話して羊水検査を受けた親が、医師から異常なしと告げられたためそれを信じて出産したら、実は医師が羊水検査の結果を見誤っていてダウン症の子どもが生まれたそうです。
子どもはダウン症による一過性骨髄異常増殖症から肝不全、無気肺、敗血症を併発して生後約3か月半で病死。
親は医師と医院を提訴。
親としては、医師や医院を恨むとか、中絶を容認するとか、我が子が生まれたことを誤りだったと言いたいのではなく、ましてや障害がある人を生かすべきか否かといった優生学的思想を主張したいわけでもないのに、様々なメディアなどで親がバッシングされたそうです。
親としては、人間が人間を診断するのだから二度とミスが起こらないわけではないし、医師や医院が我が子をダウン症にしたわけではないと理解していますが、万が一またこんなことが起きたら医療はどうあるべきなのかを問い、そして何よりも、医師から我が子に「苦しい思いをさせてごめん」と謝って欲しかったのです。
お金の問題でも、保険の問題でも、裁判の問題でも無かった…。
著…恩田昭子『仕事に差がつくビジネス電話の教科書』
2018年9月25日 おすすめの本一覧
電話を受ける、かける、取り次ぐ、取り次いでもらう。
この4点の基本を丁寧に押さえた本。
電話ではお互いの姿が見えないからこそ、相手の話をよく聞く必要がありますし、こちらが伝えたいことについて5W3H(誰が・誰に、いつ・いつまでに、どこで・どこに、何を・何が、なぜ、いくつ、いくらで、どうやって)をはっきりさせ、接続語やクッション言葉も活用しながら、より分かりやすく話す必要がある、と紹介されています。
また、
「すぐに」「ただちに」…5分以内
「のちほど」…30分以内
「後日」…2日以内
「少々」…30秒以内
「折り返し」…5分以内
「しばらくお待ちください」…1分
「少しお時間よろしいでしょうか」…3分くらい
「お待たせしました」…4コール以上
「大変お待たせしました」…6コール程度
(P92から抜粋)
など、分かっているようで実ははっきり分かっていない時間の基準なども載っています。
また、
「ある調査によれば、待つ側の感じる時間は実際の3倍ぐらいになるのだそうです。しかも、待たせる側の時間感覚は実際の2分の1。つまり、待つ側と待たせる側では、時間感覚の差はおよそ6倍にもなるのです」
(P91から抜粋)
ともこの本に書かれています。
確かに自分が待つ側だとイライラしますよね…。
自分が待たせる側の時は、確認作業などのために最低限の時間お待たせすることがあったとしても、出来る限りお待たせしないよう気をつけます。
この4点の基本を丁寧に押さえた本。
電話ではお互いの姿が見えないからこそ、相手の話をよく聞く必要がありますし、こちらが伝えたいことについて5W3H(誰が・誰に、いつ・いつまでに、どこで・どこに、何を・何が、なぜ、いくつ、いくらで、どうやって)をはっきりさせ、接続語やクッション言葉も活用しながら、より分かりやすく話す必要がある、と紹介されています。
また、
「すぐに」「ただちに」…5分以内
「のちほど」…30分以内
「後日」…2日以内
「少々」…30秒以内
「折り返し」…5分以内
「しばらくお待ちください」…1分
「少しお時間よろしいでしょうか」…3分くらい
「お待たせしました」…4コール以上
「大変お待たせしました」…6コール程度
(P92から抜粋)
など、分かっているようで実ははっきり分かっていない時間の基準なども載っています。
また、
「ある調査によれば、待つ側の感じる時間は実際の3倍ぐらいになるのだそうです。しかも、待たせる側の時間感覚は実際の2分の1。つまり、待つ側と待たせる側では、時間感覚の差はおよそ6倍にもなるのです」
(P91から抜粋)
ともこの本に書かれています。
確かに自分が待つ側だとイライラしますよね…。
自分が待たせる側の時は、確認作業などのために最低限の時間お待たせすることがあったとしても、出来る限りお待たせしないよう気をつけます。
著…稲垣俊彦『自分でできる前髪カット』
2018年9月16日 おすすめの本一覧
美容室に「前髪カット」のメニューがあっても、なかなか前髪だけのために美容室に行けないですよね…。
この本には、流しバング、シャギーバング、フルバング、ななめバング、エレガンスパート、サイドパート、ノーパート、ランダムバング、ダブルバング、ふんわりバング、下ろし流しバング、レイヤーバング、ボールバング、逆流バング、直線バング、レイヤーフルバングのやり方が載っています。
前髪ってこんなにパターンがあるんですね!
前髪だけで印象ってガラリと変わりますから、自分にどれが似合うのか色々試したいです…が、わたしはいつもYouTubeの前髪カット動画を見ながら、それが自分に本当に似合っているのかもよく分からないまま、つい適当に眉バサミで切ってしまっています…。
この本には、顔の形別の前髪の幅・厚み・形の決め方、道具をうまく使うコツ、自分の前髪だけでなく男性や子どもの前髪を切る方法や、スタイリングのコツも載っています。
子どもの前髪をカットするのは大変そうですね…。
予測不能な動きをしますよね、子どもって。
ハサミで怪我をさせたくないし、DVDなどに集中している間や眠っている隙に手早くカットしたいですね。
知人の子どもが一度、カットの際に怪我をして以来ハサミを怖がるようになってしまい、前髪どころか横も後ろも、もうすごいことになっているのですがそれでもカット出来ずに、知人が周囲からネグレクトまで疑われて嘆いています…。
この本には、流しバング、シャギーバング、フルバング、ななめバング、エレガンスパート、サイドパート、ノーパート、ランダムバング、ダブルバング、ふんわりバング、下ろし流しバング、レイヤーバング、ボールバング、逆流バング、直線バング、レイヤーフルバングのやり方が載っています。
前髪ってこんなにパターンがあるんですね!
前髪だけで印象ってガラリと変わりますから、自分にどれが似合うのか色々試したいです…が、わたしはいつもYouTubeの前髪カット動画を見ながら、それが自分に本当に似合っているのかもよく分からないまま、つい適当に眉バサミで切ってしまっています…。
この本には、顔の形別の前髪の幅・厚み・形の決め方、道具をうまく使うコツ、自分の前髪だけでなく男性や子どもの前髪を切る方法や、スタイリングのコツも載っています。
子どもの前髪をカットするのは大変そうですね…。
予測不能な動きをしますよね、子どもって。
ハサミで怪我をさせたくないし、DVDなどに集中している間や眠っている隙に手早くカットしたいですね。
知人の子どもが一度、カットの際に怪我をして以来ハサミを怖がるようになってしまい、前髪どころか横も後ろも、もうすごいことになっているのですがそれでもカット出来ずに、知人が周囲からネグレクトまで疑われて嘆いています…。
著…朝日新聞社会部『祈りの旅 天皇皇后、被災地への想い』
2018年9月16日 おすすめの本一覧
ひざ立ちや中腰のまま、被災された方々と同じ目の高さで話をする…というのは、一般人の若い人にも疲れる姿勢です。
けれど、天皇皇后両陛下は皇太子ご夫妻時代から被災地を訪問し、お年を召されてからも、東日本大震災や熊本地震などの被災地を訪れ、被災された方々に「大変おつらいことでしたね」とお声をかけて下さったことが、この本で紹介されています。
また、被災者を救援する立場の方にも、「ご苦労さま」「被災した人のため活動していただいてありがとうございます」とおっしゃったそうです。
天皇制が日本に生まれた当初から、庶民にとっては御簾の向こうどころか御簾さえ見ることは叶わなかったのに、凄いことですよね…。
声に耳を傾け、思いに寄り添ってくださる、というのは…。
来年はついに元号が変わります。
これまで頑張ってこられた分、天皇皇后両陛下には、これからは出来る限りのんびりしていただきたいです。
けれど、天皇皇后両陛下は皇太子ご夫妻時代から被災地を訪問し、お年を召されてからも、東日本大震災や熊本地震などの被災地を訪れ、被災された方々に「大変おつらいことでしたね」とお声をかけて下さったことが、この本で紹介されています。
また、被災者を救援する立場の方にも、「ご苦労さま」「被災した人のため活動していただいてありがとうございます」とおっしゃったそうです。
天皇制が日本に生まれた当初から、庶民にとっては御簾の向こうどころか御簾さえ見ることは叶わなかったのに、凄いことですよね…。
声に耳を傾け、思いに寄り添ってくださる、というのは…。
来年はついに元号が変わります。
これまで頑張ってこられた分、天皇皇后両陛下には、これからは出来る限りのんびりしていただきたいです。
著…岡田晴恵『怖くて眠れなくなる感染症』
2018年9月8日 おすすめの本一覧
エボラ出血熱、MERS、ジカウイルス、デング出血熱、マラリア、梅毒、ペスト、コレラ、黄熱病、天然痘、結核、破傷風、麻疹、狂犬病、風疹、アタマジラミ、重症熱性血小板減少症、ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌O157。
この本は、こうした感染症のもとになる細菌、ウイルス、真菌、原虫がどう人間の体内へ侵入し、発症するとどんな症状が出て、どう治療すれば良いのか、また、そもそも感染しないためにはどう行動すれば良いのかをまとめた本です。
エボラ出血熱の存在を知らない人たちが、病名も治療法も分からないまま患者の看護にあたり、患者が死亡した後、
「男性の遺体は、この土地の習慣にのっとり、母や妻などの女性親族を中心とした女性たちの素手で、〝食べたものや排泄物を全て体外に出す〟作業がなされた後、埋葬されました」
(P22から抜粋)
と書かれているのが衝撃的!
変異していない通常のエボラウイルスは空気感染しません。
エボラウイルスを体内に宿していたとしても、発症していない人からは感染しません。
でも、発症後の遺体なら話は別です。
宿主が亡くなっても、その体内にはまだウイルスはウヨウヨいます。
その遺体の体液に、よりにもよって素手で触れたのですか?
そんなことをしたら、感染して死んでしまいます!!
と、エボラ出血熱の存在を知っている人なら悲鳴をあげるでしょうが、知らない人からすれば、人間が血を吐いて目からも出血して錯乱状態になって死ぬという訳の分からない症状を目の当たりにして、せめて最期は丁重に葬りたいと願ったのは無理もありません。
…葬儀の作業にあたった女性たちは、次々と発症して亡くなってしまったそうです。
発症者の体液に素手で触れてはいけないという知識さえあれば助かった命もあったのでは?
…と、わたしはこの本を読んでいてショックを受けました。
感染症はかつて世界史を塗り変えてきましたが、現代も様々な感染症が世界中に散らばって猛威をふるっています。
特に今、日本では梅毒患者が激増しています。
梅毒トレポネーマという細菌によって引き起こされる梅毒は抗生物質による適切な治療を行えば治りますが、無症状の期間もあるため「治った」と勘違いしやすく、何回でも感染するので、自分が梅毒に感染していることにさえ気づかないまま他人にうつしていることもあるので、爆発的に日本で拡がっています。
まずは感染症について「知る」ことで命を守りたいです。
この本は、こうした感染症のもとになる細菌、ウイルス、真菌、原虫がどう人間の体内へ侵入し、発症するとどんな症状が出て、どう治療すれば良いのか、また、そもそも感染しないためにはどう行動すれば良いのかをまとめた本です。
エボラ出血熱の存在を知らない人たちが、病名も治療法も分からないまま患者の看護にあたり、患者が死亡した後、
「男性の遺体は、この土地の習慣にのっとり、母や妻などの女性親族を中心とした女性たちの素手で、〝食べたものや排泄物を全て体外に出す〟作業がなされた後、埋葬されました」
(P22から抜粋)
と書かれているのが衝撃的!
変異していない通常のエボラウイルスは空気感染しません。
エボラウイルスを体内に宿していたとしても、発症していない人からは感染しません。
でも、発症後の遺体なら話は別です。
宿主が亡くなっても、その体内にはまだウイルスはウヨウヨいます。
その遺体の体液に、よりにもよって素手で触れたのですか?
そんなことをしたら、感染して死んでしまいます!!
と、エボラ出血熱の存在を知っている人なら悲鳴をあげるでしょうが、知らない人からすれば、人間が血を吐いて目からも出血して錯乱状態になって死ぬという訳の分からない症状を目の当たりにして、せめて最期は丁重に葬りたいと願ったのは無理もありません。
…葬儀の作業にあたった女性たちは、次々と発症して亡くなってしまったそうです。
発症者の体液に素手で触れてはいけないという知識さえあれば助かった命もあったのでは?
…と、わたしはこの本を読んでいてショックを受けました。
感染症はかつて世界史を塗り変えてきましたが、現代も様々な感染症が世界中に散らばって猛威をふるっています。
特に今、日本では梅毒患者が激増しています。
梅毒トレポネーマという細菌によって引き起こされる梅毒は抗生物質による適切な治療を行えば治りますが、無症状の期間もあるため「治った」と勘違いしやすく、何回でも感染するので、自分が梅毒に感染していることにさえ気づかないまま他人にうつしていることもあるので、爆発的に日本で拡がっています。
まずは感染症について「知る」ことで命を守りたいです。
著…ジャック・ペレッティ 訳…関美和『世界を変えた14の密約』
2018年8月28日 おすすめの本一覧
人々の暮らしを変えるのは政治家でも国際的な事件でもない。
問題を作り出して解決策を売るといったような冷徹なビジネス上の損得勘定に基づいて、誰かと誰かが秘密裡に交わした取引によって、人々の暮らしは根底から作り変えられていく…という本。
クレジットカードや電子マネーを普及させることで、お金をつかうという痛みを人々に感じさせなくさせる。
ガンガンお金をつかった人々は、引き落とし日がくる頃には、何にお金をつかったのか忘れている。
4大食品会社が国際市場で小麦への投機を一斉に始めたことが原因で、食糧価額が天文学的に高騰し、露天商を営んでいた青年がお金を借りてまで何とか手に入れた露天に並べるための食品を警官に没収され、「どうやって生きていけと言うんだ?」と叫んで焼身自殺し、それによってアラブの春が始まった。
海外のタックスヘイブンに利益を置くことで、企業が払うべき税金を回避してしまい、本来ならば公共サービスやインフラへの再投資のために使われるはずの莫大な税収が失われる。
税金は「下層の人たち」が支払うものとなり、裕福な人たちは税金の支払いを巧妙に回避するようになった。
たとえるなら中流層の人々は砂時計のちょうど真ん中のくびれのところ。
砂時計の上半分は金持ちが支配し、下半分は貧乏人が支配する。
まるで砂時計の砂が落ちていくのと同じように、中流層はどんなにしがみつこうとしても下層へと落ちていき、貧富の差は開く一方。
中流階級が減れば社会は後戻り出来なくなる。
生命保険会社の統計家が、肥満の基準を厳しくすれば一夜にして保険料を高くできる!と閃いたことで、多くの人が「太り過ぎ」「肥満」と見なされて高い保険料を払うようになり、ダイエット業界は「太った」と焦る人々にダイエットとリバウンドを繰り返させることで人々を金づるにして儲けられるようになった。
…などが書かれた本。
断言や誇張をし過ぎている印象のページもありますが、確かに世の中のカラクリはこうなのだろうと思わせます。
世の中の問題も、流行も、ビジネスマンが儲けのために作り出すもの。
世界のどこかで誰かが引き金を引いている。
問題を作り出して解決策を売るといったような冷徹なビジネス上の損得勘定に基づいて、誰かと誰かが秘密裡に交わした取引によって、人々の暮らしは根底から作り変えられていく…という本。
クレジットカードや電子マネーを普及させることで、お金をつかうという痛みを人々に感じさせなくさせる。
ガンガンお金をつかった人々は、引き落とし日がくる頃には、何にお金をつかったのか忘れている。
4大食品会社が国際市場で小麦への投機を一斉に始めたことが原因で、食糧価額が天文学的に高騰し、露天商を営んでいた青年がお金を借りてまで何とか手に入れた露天に並べるための食品を警官に没収され、「どうやって生きていけと言うんだ?」と叫んで焼身自殺し、それによってアラブの春が始まった。
海外のタックスヘイブンに利益を置くことで、企業が払うべき税金を回避してしまい、本来ならば公共サービスやインフラへの再投資のために使われるはずの莫大な税収が失われる。
税金は「下層の人たち」が支払うものとなり、裕福な人たちは税金の支払いを巧妙に回避するようになった。
たとえるなら中流層の人々は砂時計のちょうど真ん中のくびれのところ。
砂時計の上半分は金持ちが支配し、下半分は貧乏人が支配する。
まるで砂時計の砂が落ちていくのと同じように、中流層はどんなにしがみつこうとしても下層へと落ちていき、貧富の差は開く一方。
中流階級が減れば社会は後戻り出来なくなる。
生命保険会社の統計家が、肥満の基準を厳しくすれば一夜にして保険料を高くできる!と閃いたことで、多くの人が「太り過ぎ」「肥満」と見なされて高い保険料を払うようになり、ダイエット業界は「太った」と焦る人々にダイエットとリバウンドを繰り返させることで人々を金づるにして儲けられるようになった。
…などが書かれた本。
断言や誇張をし過ぎている印象のページもありますが、確かに世の中のカラクリはこうなのだろうと思わせます。
世の中の問題も、流行も、ビジネスマンが儲けのために作り出すもの。
世界のどこかで誰かが引き金を引いている。
編…西日本新聞社『新 移民時代 外国人労働者と共に生きる社会へ』
2018年8月24日 おすすめの本一覧
わたしがよく行くコンビニではインド人がレジを打ってくれて、カレーを買うとなぜか褒めてくれます。
以前わたしが勤めていた介護施設では、インドネシア人が日本語を勉強しながらひたむきに働いており、その時仲良くなった子の一人は既にインドネシアに帰りましたが、今もわたしと連絡を取り合っています。
近所の工場では、日本人との間に子どもを授かった中国人やフィリピン人の女性たちが働いており、よく子どもを連れて公園に来るのを見かけるので挨拶すると、母国語を教えてもらえます。
おかげさまで中国語やタガログ語の簡単な挨拶が出来るようになりました(試しに翻訳アプリに向かって、教えてもらった挨拶を喋ってみたら、ちゃんと認識しました)。
わたしの方はお礼に日本語を教えています。
日本のあちこちで、外国人観光客だけでなく、日本に住んでいる外国人を見かけます。
見た目は外国人だけれど、中身は生まれながらの日本人、という人も少なくないでしょうが、話しかけてみると日本語が通じない場合が多いので、恐らく留学生か実習生なのだろうな、とわたしは勝手に想像しています。
日本は人口減と少子高齢化で人手不足が深刻になる一方ですから、これから先どんどん在留外国人労働者が増えるでしょうね。
日本政府は建前上「移民政策はとらない」としていますが、実質は外国人の労働力にかなり頼っています。
日本人と結婚して永住する人もいるし、在留外国人同士が結婚するケースもあるので、そのうち純血の日本人は絶滅危惧種になるのでは?と危惧して、わたしはこの本を読んでみました。
主に九州で暮らす外国人の実像についての本です。
留学生による不法就労、技能実習生の過酷労働の問題にも触れています。
現代の蟹工船とも言うべき酷い労働条件でこき使われ、給料は安く、しかも技能実習ビザは短い期間しかなくて、就労ビザ取得は困難。
母国に一旦帰る頃には日本が嫌いになっているという…何とも辛い現実が書かれています。
わたしは特に、P38〜39の外国人留学生・実習生の失踪についてのページに目をみはりました。
P39にある記述によると、2015年の1年間だけでも、福岡で157人、佐賀で14人、長崎で65人、熊本で89人、大分で61人、宮崎で34人、鹿児島で63人…計483人が失踪し、そのうち80人程度が留学生と見られるのだそう。
なんじゃこりゃ!
みんなどこへ消えたのですか?
よほどの爆弾が炸裂でもしない限り、人間が水分みたいにパッと蒸発するわけないのに、みんな一体どこへ行ってしまったのでしょう…。
勉強や仕事が嫌になって逃げ出して、いずれ不法滞在者として見つかって母国へ強制送還されるなら、まだ幸せな方かもしれません。
下手したら、犯罪に巻き込まれている場合や、逆に犯罪をする側となっている場合もありますから…。
そうなると相手国との対応が煩雑になってくるから厄介です。
それでも日本の人口減少には歯止めがきかないので、外国人に頼らざるを得ないのが現実…。
たまにアホな政治家などが「産まない人間は生産性がない」とのたまっていますが、今の日本では子どもを産めるのは相当恵まれた人か、相当楽観的な人だ、とわたしは思います。
給料が安く、サービス残業が多く、税金は上がる一方で、自分たちが年老いた時の年金をあてに出来ず(個別に企業年金などをしっかりかけている人は別ですが)、保育園や幼稚園に確実に子どもを入れられる保証もなく、かといってその親の世代はそのまた親の世代を老老介護や病病介護していて子育てを援助して貰えなかったりするので、「本当は子どもが2人くらい欲しいけど、きちんと育ててあげられるか自信がないから、子どもは1人までか0人にしよう」という思考に行き着くのは当然の流れ。
責任感のある人であればあるほど、そう考えると思います。
今の日本の平均給与水準では多くの人が共働きとなりますが、子どもってすぐ病気になるし、そうなったら保育園や幼稚園からは「迎えに来てください」と言われるし、職場に迷惑をかけて早退せざるを得なくなるなら、子どもの年齢が離れるように調整するか人数を調整するしか無いと考えるのはごく自然なこと。
子どもの年齢が離れるように調整した後、確実に妊娠できるかどうかは神のみぞ知るところで、やはり少子化は進みます。
よほど富裕層であるとか、親に子守りを頼めるとか、職場に子育てに理解があって子どものいない同僚だけに負担がいったりせず、みんなが働きやすい、などでない限り、現実はかなり厳しいです。
勿論、実家にも頼らず共働きしながら子どもを育てている人は沢山いますが、それはその人たちが頑張っているからであって、その努力を当たり前だと思って、そうしない、そうしたくでも出来ない人たちを「生産性がない」などと言われたらたまったものではありません。
安心して子どもが産める政策に今から慌てて日本がシフトしていったとしても既に手遅れで、子どもが義務教育や高等教育などを経てやっと社会人になれる時には…、日本国内には今以上に外国人が溢れかえっているのでしょうね。
以前わたしが勤めていた介護施設では、インドネシア人が日本語を勉強しながらひたむきに働いており、その時仲良くなった子の一人は既にインドネシアに帰りましたが、今もわたしと連絡を取り合っています。
近所の工場では、日本人との間に子どもを授かった中国人やフィリピン人の女性たちが働いており、よく子どもを連れて公園に来るのを見かけるので挨拶すると、母国語を教えてもらえます。
おかげさまで中国語やタガログ語の簡単な挨拶が出来るようになりました(試しに翻訳アプリに向かって、教えてもらった挨拶を喋ってみたら、ちゃんと認識しました)。
わたしの方はお礼に日本語を教えています。
日本のあちこちで、外国人観光客だけでなく、日本に住んでいる外国人を見かけます。
見た目は外国人だけれど、中身は生まれながらの日本人、という人も少なくないでしょうが、話しかけてみると日本語が通じない場合が多いので、恐らく留学生か実習生なのだろうな、とわたしは勝手に想像しています。
日本は人口減と少子高齢化で人手不足が深刻になる一方ですから、これから先どんどん在留外国人労働者が増えるでしょうね。
日本政府は建前上「移民政策はとらない」としていますが、実質は外国人の労働力にかなり頼っています。
日本人と結婚して永住する人もいるし、在留外国人同士が結婚するケースもあるので、そのうち純血の日本人は絶滅危惧種になるのでは?と危惧して、わたしはこの本を読んでみました。
主に九州で暮らす外国人の実像についての本です。
留学生による不法就労、技能実習生の過酷労働の問題にも触れています。
現代の蟹工船とも言うべき酷い労働条件でこき使われ、給料は安く、しかも技能実習ビザは短い期間しかなくて、就労ビザ取得は困難。
母国に一旦帰る頃には日本が嫌いになっているという…何とも辛い現実が書かれています。
わたしは特に、P38〜39の外国人留学生・実習生の失踪についてのページに目をみはりました。
P39にある記述によると、2015年の1年間だけでも、福岡で157人、佐賀で14人、長崎で65人、熊本で89人、大分で61人、宮崎で34人、鹿児島で63人…計483人が失踪し、そのうち80人程度が留学生と見られるのだそう。
なんじゃこりゃ!
みんなどこへ消えたのですか?
よほどの爆弾が炸裂でもしない限り、人間が水分みたいにパッと蒸発するわけないのに、みんな一体どこへ行ってしまったのでしょう…。
勉強や仕事が嫌になって逃げ出して、いずれ不法滞在者として見つかって母国へ強制送還されるなら、まだ幸せな方かもしれません。
下手したら、犯罪に巻き込まれている場合や、逆に犯罪をする側となっている場合もありますから…。
そうなると相手国との対応が煩雑になってくるから厄介です。
それでも日本の人口減少には歯止めがきかないので、外国人に頼らざるを得ないのが現実…。
たまにアホな政治家などが「産まない人間は生産性がない」とのたまっていますが、今の日本では子どもを産めるのは相当恵まれた人か、相当楽観的な人だ、とわたしは思います。
給料が安く、サービス残業が多く、税金は上がる一方で、自分たちが年老いた時の年金をあてに出来ず(個別に企業年金などをしっかりかけている人は別ですが)、保育園や幼稚園に確実に子どもを入れられる保証もなく、かといってその親の世代はそのまた親の世代を老老介護や病病介護していて子育てを援助して貰えなかったりするので、「本当は子どもが2人くらい欲しいけど、きちんと育ててあげられるか自信がないから、子どもは1人までか0人にしよう」という思考に行き着くのは当然の流れ。
責任感のある人であればあるほど、そう考えると思います。
今の日本の平均給与水準では多くの人が共働きとなりますが、子どもってすぐ病気になるし、そうなったら保育園や幼稚園からは「迎えに来てください」と言われるし、職場に迷惑をかけて早退せざるを得なくなるなら、子どもの年齢が離れるように調整するか人数を調整するしか無いと考えるのはごく自然なこと。
子どもの年齢が離れるように調整した後、確実に妊娠できるかどうかは神のみぞ知るところで、やはり少子化は進みます。
よほど富裕層であるとか、親に子守りを頼めるとか、職場に子育てに理解があって子どものいない同僚だけに負担がいったりせず、みんなが働きやすい、などでない限り、現実はかなり厳しいです。
勿論、実家にも頼らず共働きしながら子どもを育てている人は沢山いますが、それはその人たちが頑張っているからであって、その努力を当たり前だと思って、そうしない、そうしたくでも出来ない人たちを「生産性がない」などと言われたらたまったものではありません。
安心して子どもが産める政策に今から慌てて日本がシフトしていったとしても既に手遅れで、子どもが義務教育や高等教育などを経てやっと社会人になれる時には…、日本国内には今以上に外国人が溢れかえっているのでしょうね。
東京都内の図書館30館を紹介する本。
各図書館の蔵書数、利用条件、貸出の可否なども掲載されています。
図書館そのものがロマンを感じさせる美しい建築物であったり、各図書館が児童書、演劇台本、映画シナリオ、雑誌、その土地にゆかりのある作家の作品、洋書、写真と映像、展覧会カタログ、漫画、広告、天文学など、それぞれ違う分野に特化していて興味深いです。
行ってみたい図書館ばかり!
一般常識として「国立国会図書館の蔵書数は凄い」ということは以前から分かっていたつもりでしたが、こうして改めて国立国会図書館の概要を読むと、その蔵書数の異次元っぷりに衝撃を受けました!
さすが、あらゆる図書を収集・保存し、未来へ伝え続ける聖域…。
桁が違う…。
わたしは特にこの本の『第3章 コミュニケーションが生まれる図書館』を気に入りました。
残念ながらこの第3章はごくわずかなページしか割かれていないのですが、図書館の利用者が本と出会うだけでなく、利用者同士がお互いに本について話したりする中で人と人が出会う取り組みが紹介されているのが素敵です。
各図書館の蔵書数、利用条件、貸出の可否なども掲載されています。
図書館そのものがロマンを感じさせる美しい建築物であったり、各図書館が児童書、演劇台本、映画シナリオ、雑誌、その土地にゆかりのある作家の作品、洋書、写真と映像、展覧会カタログ、漫画、広告、天文学など、それぞれ違う分野に特化していて興味深いです。
行ってみたい図書館ばかり!
一般常識として「国立国会図書館の蔵書数は凄い」ということは以前から分かっていたつもりでしたが、こうして改めて国立国会図書館の概要を読むと、その蔵書数の異次元っぷりに衝撃を受けました!
さすが、あらゆる図書を収集・保存し、未来へ伝え続ける聖域…。
桁が違う…。
わたしは特にこの本の『第3章 コミュニケーションが生まれる図書館』を気に入りました。
残念ながらこの第3章はごくわずかなページしか割かれていないのですが、図書館の利用者が本と出会うだけでなく、利用者同士がお互いに本について話したりする中で人と人が出会う取り組みが紹介されているのが素敵です。
この本のタイトルには「医療・介護スタッフ必修」とありますが、いつどこで誰が自分の目の前で倒れるかは分からないので、一般常識として多くの人におすすめしたい本です。
窒息、過換気症候群、頭部外傷、急性心筋梗塞、骨折、出血、火傷、アナフィラキシーショック、熱中症など、様々な状況に応じた対処法が載っています。
いざという時は気が動転してオロオロしてしまいがちだけれど、とっさの処置が出来るか出来ないかで、誰かの生死やその後の後遺症の程度にも影響しますから、しっかり頭に入れておきたいです。
まずは、「救急のABCD」を頭に入れておきたいです。
Aは気道確保(エアウェイ)、Bは呼吸(ブリージング。人工呼吸)、Cは循環(サーキュレーション。心臓マッサージや止血)、Dは電気的除細動(デフィブリレーション。よく目にするAEDはAutomated External Defibrillatorの略)。
わたしは身近な人たちが頭部外傷で亡くなったり頚椎損傷で障害を負ったりしていますので、特にP36〜37に載っている対処法をしっかり頭に叩き込み、いざという時はバイタルサインの確認や頚椎の保護をして救急車を呼びたいです。
熱中症について、「熱中症になると、筋肉の細胞が壊れてコーヒー色をした尿(ミオグロビン尿)が出ることがあります。ミオグロビンが尿細管に詰まると腎臓がダメージを受けます。肝臓などほかの重要臓器も障害を受ける危険性があります。症状が進むと、集中治療を行わざるをえません」(P78から抜粋)と書かれていて、改めて熱中症の恐ろしさにゾッとしました。
熱中症にならないための対策を徹底したいです。
この本の最後のページには、「救急処置がうまくいったときには達成感が得られます。しかし、うまくいかなかったとき、自責の念にかられます。時には悪い記憶がよみがえるのかもしれません。また、傷病者のその後の経過がわからないとイライラもたまります」(P102から抜粋)と救急救命にあたる人への心のケアや、二次災害・ケガ・感染から自分を守ることの重要性についても触れられています。
こう言ったら不謹慎なのかもしれませんが、救える命もあれば救えない命もあるというのが現実。
誰かを救おうとして結果的に救えなかったとしても、自分を責めないで欲しいです。
そういうのは見殺しにしたのとは違いますから。
窒息、過換気症候群、頭部外傷、急性心筋梗塞、骨折、出血、火傷、アナフィラキシーショック、熱中症など、様々な状況に応じた対処法が載っています。
いざという時は気が動転してオロオロしてしまいがちだけれど、とっさの処置が出来るか出来ないかで、誰かの生死やその後の後遺症の程度にも影響しますから、しっかり頭に入れておきたいです。
まずは、「救急のABCD」を頭に入れておきたいです。
Aは気道確保(エアウェイ)、Bは呼吸(ブリージング。人工呼吸)、Cは循環(サーキュレーション。心臓マッサージや止血)、Dは電気的除細動(デフィブリレーション。よく目にするAEDはAutomated External Defibrillatorの略)。
わたしは身近な人たちが頭部外傷で亡くなったり頚椎損傷で障害を負ったりしていますので、特にP36〜37に載っている対処法をしっかり頭に叩き込み、いざという時はバイタルサインの確認や頚椎の保護をして救急車を呼びたいです。
熱中症について、「熱中症になると、筋肉の細胞が壊れてコーヒー色をした尿(ミオグロビン尿)が出ることがあります。ミオグロビンが尿細管に詰まると腎臓がダメージを受けます。肝臓などほかの重要臓器も障害を受ける危険性があります。症状が進むと、集中治療を行わざるをえません」(P78から抜粋)と書かれていて、改めて熱中症の恐ろしさにゾッとしました。
熱中症にならないための対策を徹底したいです。
この本の最後のページには、「救急処置がうまくいったときには達成感が得られます。しかし、うまくいかなかったとき、自責の念にかられます。時には悪い記憶がよみがえるのかもしれません。また、傷病者のその後の経過がわからないとイライラもたまります」(P102から抜粋)と救急救命にあたる人への心のケアや、二次災害・ケガ・感染から自分を守ることの重要性についても触れられています。
こう言ったら不謹慎なのかもしれませんが、救える命もあれば救えない命もあるというのが現実。
誰かを救おうとして結果的に救えなかったとしても、自分を責めないで欲しいです。
そういうのは見殺しにしたのとは違いますから。
著…池上彰『いま、君たちに一番伝えたいこと』
2018年8月13日 おすすめの本一覧
「歴史は偶然の積み重ねでできあがっているわけではありません。過去を手がかりに現代を読み解くことによって、すこし先を見通すことができるかもしれません。だからこそ、いまにつながる現代史を知ることが重要なのです。「歴史は決して暗記科目ではありません」。私はいつも学生たちに、こう話しかけています」(P62から抜粋)
池上さんがこう書いている通り、ものごとは全て繋がっています。
たとえば、冷戦、イラク戦争、アラブの春、イスラム国。
これらはみんな繋がっています。
東西冷戦が始まり、アメリカ陣営とソ連陣営に世界が二分され、それが終わると民族紛争と宗教対立が混沌化。
異教徒がイスラム教の聖地に駐屯したことなどに怒ったウサマ・ビンラディンがアルカイダを組織して米同時多発テロを引き起こし、その報復でアメリカがアフガニスタンとイラクを攻撃。
「イスラム国」の前身組織が組織され、民主化要求運動「アラブの春」が盛り上がってシリアが内戦状態に陥ると、「イスラム国」の前身組織がシリア内戦に介入。
全ては繋がっています。
そして報復は報復を生む。
池上さんはドイツのワイツゼッカー元大統領の、
「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる」
(P256から抜粋)
という言葉でこの本を締めくくっています。
報復に報復を繰り返す、そんな負の連鎖を断ち切るためにも、なぜそんな出来事が起きたのか、という歴史を学ばなければなりません。
「エルトゥールル号からの恩返し」のように、良い行いがまた良い行いとなって返ってくる幸福なラリーを受け継いでいくために。
1890年に日本を訪問した軍艦エルトゥールル号が帰国の途中、和歌山県串本町沖で台風のため沈没。
残念ながら587人が死亡しましたが、地元の人々が総出で救助を行い、69人を助けることが出来ました。
地元の人々が死亡者たちを丁重に葬り、生存者を日本の軍艦がトルコに送り届けたそうです。
その約100年後の1985年に、イラクからイランへの空爆が始まり、イラン在住の日本人が脱出出来なくて困り果てていた時、トルコの航空機がイランに飛び、日本人をトルコまで脱出させてくれたそうです。
「このときトルコは、「エルトゥールル号の恩義は忘れていません。その恩返しです」と言ったものです」
(P42から抜粋)
だそうです。
か、かっこいい…!!
100年越しの恩返し…!!
100年前のことを後世の人が覚えている、というのは歴史教育の賜物。
その後も日本とトルコはお互いに地震災害の時などに助け合っています。
血で血を洗う負の歴史を繰り返すのではなく、負の歴史から目を背けず教訓として後世の人々へ伝えながら、お互いに助け合うという歴史を受け継いでいきたいです。
池上さんがこう書いている通り、ものごとは全て繋がっています。
たとえば、冷戦、イラク戦争、アラブの春、イスラム国。
これらはみんな繋がっています。
東西冷戦が始まり、アメリカ陣営とソ連陣営に世界が二分され、それが終わると民族紛争と宗教対立が混沌化。
異教徒がイスラム教の聖地に駐屯したことなどに怒ったウサマ・ビンラディンがアルカイダを組織して米同時多発テロを引き起こし、その報復でアメリカがアフガニスタンとイラクを攻撃。
「イスラム国」の前身組織が組織され、民主化要求運動「アラブの春」が盛り上がってシリアが内戦状態に陥ると、「イスラム国」の前身組織がシリア内戦に介入。
全ては繋がっています。
そして報復は報復を生む。
池上さんはドイツのワイツゼッカー元大統領の、
「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる」
(P256から抜粋)
という言葉でこの本を締めくくっています。
報復に報復を繰り返す、そんな負の連鎖を断ち切るためにも、なぜそんな出来事が起きたのか、という歴史を学ばなければなりません。
「エルトゥールル号からの恩返し」のように、良い行いがまた良い行いとなって返ってくる幸福なラリーを受け継いでいくために。
1890年に日本を訪問した軍艦エルトゥールル号が帰国の途中、和歌山県串本町沖で台風のため沈没。
残念ながら587人が死亡しましたが、地元の人々が総出で救助を行い、69人を助けることが出来ました。
地元の人々が死亡者たちを丁重に葬り、生存者を日本の軍艦がトルコに送り届けたそうです。
その約100年後の1985年に、イラクからイランへの空爆が始まり、イラン在住の日本人が脱出出来なくて困り果てていた時、トルコの航空機がイランに飛び、日本人をトルコまで脱出させてくれたそうです。
「このときトルコは、「エルトゥールル号の恩義は忘れていません。その恩返しです」と言ったものです」
(P42から抜粋)
だそうです。
か、かっこいい…!!
100年越しの恩返し…!!
100年前のことを後世の人が覚えている、というのは歴史教育の賜物。
その後も日本とトルコはお互いに地震災害の時などに助け合っています。
血で血を洗う負の歴史を繰り返すのではなく、負の歴史から目を背けず教訓として後世の人々へ伝えながら、お互いに助け合うという歴史を受け継いでいきたいです。
たんぱく質、炭水化物、脂質、ミネラル、ビタミン。
この5大栄養素のどれかが不足すると、せっかく背を伸ばすための栄養をとっても、栄養は生命維持に費やされてしまうそうです。
この本には、5大栄養素をバランス良く取れる一週間分のレシピが載っているので、早速今日からの献立作りの参考になります。
写真に写っている飲み物やデザートも含めて全部美味しそうなので、子どもだけでなく大人用の献立作りにも役立ちます。
ポイントは、6品目とって様々な食材をバランス良く取り入れることらしいので、わたしもお弁当を作る際に食材の種類を多めに用意するようにしたいと思います。
もしも成長期のうちにこの本と出会えていたらわたしの身長(150cmありません)は今より少しはマシだったかも…と思うと残念でなりません。
わたしが成長期だった頃は、両親が共働きで2人とも帰りが遅い&祖母も母も料理が苦手で嫁姑問題で対立し二世帯同居で生活は別々&両親がよく離婚話でもめていてお互いの愚痴を子どもにぶつけてくる、という感じで、そんな家庭環境なのでこの本に出てくるような豊富なメニューの食事は食べられませんでした。
たまに近所のおばあさんがお菓子をくれる時は良かったけれど、それ以外の時は自分で冷凍庫で氷を作って氷を食べて空腹を紛らわせていました。
季節を問わず製氷皿2枚分以上をほぼ毎日食べていましたが、今思うとストレスや鉄分不足などによる栄養不足が原因の氷食症に陥っていたのだと思います。
身長は遺伝の問題もあるけれど、身長が低くて得することは何も無く、身長制限があるせいで就きたい職業に挑戦すら出来なかったり、スポーツが不利だったり、他人から馬鹿にされたりと、困ることだらけなので、未来を担う子どもたちには出来る限り体格に恵まれるよう育っていって欲しいです。
この5大栄養素のどれかが不足すると、せっかく背を伸ばすための栄養をとっても、栄養は生命維持に費やされてしまうそうです。
この本には、5大栄養素をバランス良く取れる一週間分のレシピが載っているので、早速今日からの献立作りの参考になります。
写真に写っている飲み物やデザートも含めて全部美味しそうなので、子どもだけでなく大人用の献立作りにも役立ちます。
ポイントは、6品目とって様々な食材をバランス良く取り入れることらしいので、わたしもお弁当を作る際に食材の種類を多めに用意するようにしたいと思います。
もしも成長期のうちにこの本と出会えていたらわたしの身長(150cmありません)は今より少しはマシだったかも…と思うと残念でなりません。
わたしが成長期だった頃は、両親が共働きで2人とも帰りが遅い&祖母も母も料理が苦手で嫁姑問題で対立し二世帯同居で生活は別々&両親がよく離婚話でもめていてお互いの愚痴を子どもにぶつけてくる、という感じで、そんな家庭環境なのでこの本に出てくるような豊富なメニューの食事は食べられませんでした。
たまに近所のおばあさんがお菓子をくれる時は良かったけれど、それ以外の時は自分で冷凍庫で氷を作って氷を食べて空腹を紛らわせていました。
季節を問わず製氷皿2枚分以上をほぼ毎日食べていましたが、今思うとストレスや鉄分不足などによる栄養不足が原因の氷食症に陥っていたのだと思います。
身長は遺伝の問題もあるけれど、身長が低くて得することは何も無く、身長制限があるせいで就きたい職業に挑戦すら出来なかったり、スポーツが不利だったり、他人から馬鹿にされたりと、困ることだらけなので、未来を担う子どもたちには出来る限り体格に恵まれるよう育っていって欲しいです。
著…鹿島田忠志『あなたの不調がスパッと消える! 快腸SPAT』
2018年8月5日 おすすめの本一覧
病気を治すのは医者ではなく患者自身。
腸には全身の免疫細胞の7割が集中しているため、自然治癒力を強化するためには、腸が重要なカギとなる。
という視点で書かれた本。
腸が「第二の脳」と呼ばれる理由や、腸内細菌の働き、腸に由来する不調や病気、骨格のゆがみを判定・矯正して腸を健康にする方法が紹介されています。
骨盤だけでなく、胸椎まわりや、頚椎まわりの歪みのチェック方法も載っているので、自分の歪みをチェックすることが可能です。
P126掲載の「気道ストレッチ」をやると鼻や喉の通りが良くなり、呼吸が楽になるそうなので、少なくとも毎日1回以上はやるよう習慣化したいと思います。
「ただ横になるだけでも肝臓の血流は7割増しになる」(P133から抜粋)
という言葉や、
「1時間に1度は目を閉じて、自分の身体をスキャンしてください」
(P138から抜粋)
という言葉を読み、
意識して自分の身体を労わろう!と気づかされました。
腸には全身の免疫細胞の7割が集中しているため、自然治癒力を強化するためには、腸が重要なカギとなる。
という視点で書かれた本。
腸が「第二の脳」と呼ばれる理由や、腸内細菌の働き、腸に由来する不調や病気、骨格のゆがみを判定・矯正して腸を健康にする方法が紹介されています。
骨盤だけでなく、胸椎まわりや、頚椎まわりの歪みのチェック方法も載っているので、自分の歪みをチェックすることが可能です。
P126掲載の「気道ストレッチ」をやると鼻や喉の通りが良くなり、呼吸が楽になるそうなので、少なくとも毎日1回以上はやるよう習慣化したいと思います。
「ただ横になるだけでも肝臓の血流は7割増しになる」(P133から抜粋)
という言葉や、
「1時間に1度は目を閉じて、自分の身体をスキャンしてください」
(P138から抜粋)
という言葉を読み、
意識して自分の身体を労わろう!と気づかされました。
「日本人は「安心」という言葉が大好きです。でも、安心は「大丈夫だ」と思うことで生まれる心理でしかありません。「事実」ではなく「気持ち」なんです。ミサイルが飛び交うような危険な環境に置かれていても、「大丈夫。平気平気」と思っていれば、それは安心なのです。ネットトラブルだって同じ。子どもが危険にさらされているのに、親がそれを知らなければ、どこまでも安心していられます。でも、それではお子さんを守れないですよね」
(P69から抜粋)
という文は、友人たちにシェアしたくなるくらい説得力があります。
子どもにスマホを持たせなければいい、パソコンを触らせなければいい、と短絡的に考えても何も解決しません。
まずは親自身がネットトラブルについて理解を深めることが必要。
この本では、
スマホで撮る画像の位置情報サービスやLINEの友だち追加許可のオン・オフの方法、悪質なサイトにアクセスしないためのフィルタリングの重要性、勝手に他人を撮って勝手にネットに載せる肖像権・パブリシティ権の侵害や、他人のプライバシー情報を流出させるリスク(DV被害者が避難先で写ってしまい、DV加害者に居場所がバレてしまうこともある!)、そういった世間から叩かれる行為をしたことで個人を特定されてネット上で炎上し一生を棒に振るかもしれないリスク、親のクレジットカード情報を入力して子どもが勝手にネット上で買い物をすると不正アクセス禁止法違反となること、選挙権のない年齢の人が立候補者のツイートをリツイートすると公職選挙法違反になること、
などについて触れられています。
怒りを制御する「アンガーマネジメント」の手法を使い、ネットに何かをアップする前に6秒間考える、という「6秒ルール」も紹介されていて、とても良いアイディアだと思いますので、わたしも6秒ルールを取り入れていきます。
また、夏になると、友人たちが我が子の水浴び写真などをSNSに載せているのを目にしますが、あれも裸の程度次第では児童ポルノ製造の罪に問われますよね…。
本人たちにとっては可愛い我が子の姿でも、変態がニヤニヤしながら舐めるように見ているかもしれません。
子どもだけでなく、大人も気をつけないといけないですよね。
以前カフェで「彼氏がエロい写真送ってって言ってくる〜。絶対他の人には見せないからって〜」などとと年若いお嬢さんたちが話しているのが耳に入ってきて、わたしはコーヒーを噴きそうになったことがあります。
そういう画像を送れという軽薄な男が本当に他の人に見せない誠実さを1ミリでも持っているかというと、持ってるわけないんだからお止めなさい!!
お嬢さんたちに断言しましょう、その男はその画像を100%友達みんなでシェアする! 下手したらネットにアップするよ!!と。
シェアするまでが画像の醍醐味ですから。
敢えてここに事件名まで書きませんが、交際相手のパソコンがウイルスに感染したことで女性の裸の写真がネット上に出回ったり、女性から別れ話を告げられて逆上した男が女性の裸の画像や動画をネット上にばらまいた後その女性を殺した事件など、ロクなことにはならない実例が世の中には沢山あります。
ネット上に画像がばらまかれたら、面白がった人たちにあちこちへ拡散されてしまいますよ。
お嬢さんたち、あなたを大切にしてくれる人と付き合ってください。
まともな記憶力と誠実さがある男性なら、わざわざ画像や動画に撮らなくたってあなたのことをちゃんと覚えているはずです。
あなたが断っても、「〇〇ちゃんと会えなくて寂しい時に見たいんだよ〜」としつこく頼まれたら、「じゃあもっと寂しくしてあげる。もう会えないわ」と振ってやりましょう!
(P69から抜粋)
という文は、友人たちにシェアしたくなるくらい説得力があります。
子どもにスマホを持たせなければいい、パソコンを触らせなければいい、と短絡的に考えても何も解決しません。
まずは親自身がネットトラブルについて理解を深めることが必要。
この本では、
スマホで撮る画像の位置情報サービスやLINEの友だち追加許可のオン・オフの方法、悪質なサイトにアクセスしないためのフィルタリングの重要性、勝手に他人を撮って勝手にネットに載せる肖像権・パブリシティ権の侵害や、他人のプライバシー情報を流出させるリスク(DV被害者が避難先で写ってしまい、DV加害者に居場所がバレてしまうこともある!)、そういった世間から叩かれる行為をしたことで個人を特定されてネット上で炎上し一生を棒に振るかもしれないリスク、親のクレジットカード情報を入力して子どもが勝手にネット上で買い物をすると不正アクセス禁止法違反となること、選挙権のない年齢の人が立候補者のツイートをリツイートすると公職選挙法違反になること、
などについて触れられています。
怒りを制御する「アンガーマネジメント」の手法を使い、ネットに何かをアップする前に6秒間考える、という「6秒ルール」も紹介されていて、とても良いアイディアだと思いますので、わたしも6秒ルールを取り入れていきます。
また、夏になると、友人たちが我が子の水浴び写真などをSNSに載せているのを目にしますが、あれも裸の程度次第では児童ポルノ製造の罪に問われますよね…。
本人たちにとっては可愛い我が子の姿でも、変態がニヤニヤしながら舐めるように見ているかもしれません。
子どもだけでなく、大人も気をつけないといけないですよね。
以前カフェで「彼氏がエロい写真送ってって言ってくる〜。絶対他の人には見せないからって〜」などとと年若いお嬢さんたちが話しているのが耳に入ってきて、わたしはコーヒーを噴きそうになったことがあります。
そういう画像を送れという軽薄な男が本当に他の人に見せない誠実さを1ミリでも持っているかというと、持ってるわけないんだからお止めなさい!!
お嬢さんたちに断言しましょう、その男はその画像を100%友達みんなでシェアする! 下手したらネットにアップするよ!!と。
シェアするまでが画像の醍醐味ですから。
敢えてここに事件名まで書きませんが、交際相手のパソコンがウイルスに感染したことで女性の裸の写真がネット上に出回ったり、女性から別れ話を告げられて逆上した男が女性の裸の画像や動画をネット上にばらまいた後その女性を殺した事件など、ロクなことにはならない実例が世の中には沢山あります。
ネット上に画像がばらまかれたら、面白がった人たちにあちこちへ拡散されてしまいますよ。
お嬢さんたち、あなたを大切にしてくれる人と付き合ってください。
まともな記憶力と誠実さがある男性なら、わざわざ画像や動画に撮らなくたってあなたのことをちゃんと覚えているはずです。
あなたが断っても、「〇〇ちゃんと会えなくて寂しい時に見たいんだよ〜」としつこく頼まれたら、「じゃあもっと寂しくしてあげる。もう会えないわ」と振ってやりましょう!
わたしの母はいわゆる「アダルトチルドレン」に該当する人です。
母は60歳をとっくに超えた今でも両親との関係性に苦しんでいます。
愛して欲しかった両親はとっくに亡くなっているのに。
そして母もまた、自分の親にされたようにわたしと接してしまうことがしばしば。
そんな母の苦しみを理解したい、と思ってわたしはこの本を読みました。
アダルトチルドレン、インナーマザーなどの概念が分かりやすく書かれています。
この本のタイトルには「長女」とありますが、長女に限った話ではないと思います。
機能不全家族(いわゆる毒親)によって苦しんでいる人は沢山います。
この本には、「こうするべき」が強すぎる…という記述があり、まさにその通りだと思いました。
自分が、もしくは他人が「どうしたいのか」を考えようとすると混乱してしまうんですよね…。
ましてや「自分らしさ」が何なのかなんて想像もつかない…。
本人も周りも相当苦しいでしょう。
この本のP178〜P180で紹介されている「三点確保」を心がけながら(三点で支えていれば、どこか一ヶ所の手や足がすべったとしても、ほかの二点で体を支え、安全を確保できる…という登山やロッククライミングではなじみのある言葉だそうです)、一対一で共依存し合うのではなく、いくつもの人間関係を築いていきたいです。
わたしは溺れている母にしがみつかれて一緒に沈んでいくのではなく、先にどうにか自分が岸辺に上がって母に浮き輪を投げたい。
母の親代わりにはなってあげられないから、自立した大人の一人として母を見守っていきたい。
と思ってしまうわたしなのですが、P162に「「やっぱり母とはわかりあえない」でもいい」と書かれているのを見て心が楽になりました。
母は60歳をとっくに超えた今でも両親との関係性に苦しんでいます。
愛して欲しかった両親はとっくに亡くなっているのに。
そして母もまた、自分の親にされたようにわたしと接してしまうことがしばしば。
そんな母の苦しみを理解したい、と思ってわたしはこの本を読みました。
アダルトチルドレン、インナーマザーなどの概念が分かりやすく書かれています。
この本のタイトルには「長女」とありますが、長女に限った話ではないと思います。
機能不全家族(いわゆる毒親)によって苦しんでいる人は沢山います。
この本には、「こうするべき」が強すぎる…という記述があり、まさにその通りだと思いました。
自分が、もしくは他人が「どうしたいのか」を考えようとすると混乱してしまうんですよね…。
ましてや「自分らしさ」が何なのかなんて想像もつかない…。
本人も周りも相当苦しいでしょう。
この本のP178〜P180で紹介されている「三点確保」を心がけながら(三点で支えていれば、どこか一ヶ所の手や足がすべったとしても、ほかの二点で体を支え、安全を確保できる…という登山やロッククライミングではなじみのある言葉だそうです)、一対一で共依存し合うのではなく、いくつもの人間関係を築いていきたいです。
わたしは溺れている母にしがみつかれて一緒に沈んでいくのではなく、先にどうにか自分が岸辺に上がって母に浮き輪を投げたい。
母の親代わりにはなってあげられないから、自立した大人の一人として母を見守っていきたい。
と思ってしまうわたしなのですが、P162に「「やっぱり母とはわかりあえない」でもいい」と書かれているのを見て心が楽になりました。
「ロボット図鑑AR」アプリを使ってこの本の特定のページにスマホをかざすと、ロボットがリアルに動き出す、とこの本のはじめに書かれていたので、早速アプリをダウンロードしてみました。
アプリで好きなロボットを作り、ARを使ってこの本のページの上をロボットに歩かせたりポーズを取らせたり、ドローンを飛ばしたりといったことが出来るので、子どもだけでなく大人も楽しめます。
本の内容も、子どもの頃に空想した未来が近づいている!とワクワクさせる内容ばかり。
エクソ・バイオニクス社の「eLEGS」は筋力の衰えた人や体の不自由な人の助けになるそうですし、ロッキード・マーティン社の「HULC」は兵士や作業員に重いものを持ち上げる力を与えるそうなので災害・事故現場における救助活動にも使えそうな気がします。
タッチ・バイオニクス社の「i-limb」は一本一本の指をばらばらに動かしたり、物を掴む時の力の入れ具合と握り方も調整出来るそうなので、様々な理由で手の機能が低下した方の希望の光になりそう!
アプリで好きなロボットを作り、ARを使ってこの本のページの上をロボットに歩かせたりポーズを取らせたり、ドローンを飛ばしたりといったことが出来るので、子どもだけでなく大人も楽しめます。
本の内容も、子どもの頃に空想した未来が近づいている!とワクワクさせる内容ばかり。
エクソ・バイオニクス社の「eLEGS」は筋力の衰えた人や体の不自由な人の助けになるそうですし、ロッキード・マーティン社の「HULC」は兵士や作業員に重いものを持ち上げる力を与えるそうなので災害・事故現場における救助活動にも使えそうな気がします。
タッチ・バイオニクス社の「i-limb」は一本一本の指をばらばらに動かしたり、物を掴む時の力の入れ具合と握り方も調整出来るそうなので、様々な理由で手の機能が低下した方の希望の光になりそう!
NHKスペシャル取材班『高校生ワーキングプア「見えない貧困」の真実』
2018年6月12日 おすすめの本一覧
「子どもは、家庭という閉ざされた空間の中で人知れず追い詰められていく。たとえるなら、「川の岩陰で溺れた状態」だ。(中略)本当に困った子どもは、自ら名乗り出ることはできない。自力で這い上がれないまま、岩陰で溺れているからだ。子どもに向けた相談窓口を開いて、困ったらここへ相談してくださいという取り組みを見かけるが、それでは、川の岸辺に屋台を開いて溺れている子どもに向かって困ったらここまでおいで、と言っているようなものだ」
(P151〜152から抜粋)
という記述を読んで、仕事で生活困窮世帯の相談窓口を担当するわたし自身の仕事ぶりを反省させられました。
自分は受け身になっていないか。
ただ上っ面だけを見て事務的な対応だけしていないか。
子どもに限らず、溺れている人を発見できるよう様々な「川」を何度も巡回し、溺れている人をただ発見するだけではなく実際に救命が出来るよう浮き輪などの道具や救命に必要な知識も沢山持ちたいし、協力し合えるライフセーバー仲間も増やしたいです。
(P151〜152から抜粋)
という記述を読んで、仕事で生活困窮世帯の相談窓口を担当するわたし自身の仕事ぶりを反省させられました。
自分は受け身になっていないか。
ただ上っ面だけを見て事務的な対応だけしていないか。
子どもに限らず、溺れている人を発見できるよう様々な「川」を何度も巡回し、溺れている人をただ発見するだけではなく実際に救命が出来るよう浮き輪などの道具や救命に必要な知識も沢山持ちたいし、協力し合えるライフセーバー仲間も増やしたいです。
きくちいま『おとなのときめきふだん着物』
2018年5月29日 おすすめの本一覧
半幅帯や作り帯などを活用しながら普段着として着物を楽しもうという本。
単衣をメインに、基本アイテム(たとえば着物4枚、帯4本、帯揚げ3枚、帯締め3本、などの組み合わせ)を使った着回しのアイデアが参考になります。
焼肉にも着物で行きたいので、匂い対策のためにも洗える着物が基本!という著者の考え方にわたしは圧倒されました。
わたしは着物でカフェへ行くことはあっても焼肉は未体験です。
たとえ汚れ防止用にナプキンや割烹着を着たとしても焼肉のタレが飛びそうでわたしは勇気が出ません!
著者はすごい。
また、この本には、着物初心者を食い物にして数十万〜数百万で着物や小物を売りつける着付け教室や呉服屋のエピソードや、P104〜105などに頼れるお店の探し方についてのアドバイスも載っているので、着物に憧れているけれどまず何からしたら良いか分からない方におすすめ。
また、着物には直接関係ないですが、
「わたしにとって足のネイルは、地に足をつけるためのいわば文鎮です。足袋で見えなくなるけどね」
(P17から抜粋)
という著者の言葉に共感しました。
お洒落は活力。
単衣をメインに、基本アイテム(たとえば着物4枚、帯4本、帯揚げ3枚、帯締め3本、などの組み合わせ)を使った着回しのアイデアが参考になります。
焼肉にも着物で行きたいので、匂い対策のためにも洗える着物が基本!という著者の考え方にわたしは圧倒されました。
わたしは着物でカフェへ行くことはあっても焼肉は未体験です。
たとえ汚れ防止用にナプキンや割烹着を着たとしても焼肉のタレが飛びそうでわたしは勇気が出ません!
著者はすごい。
また、この本には、着物初心者を食い物にして数十万〜数百万で着物や小物を売りつける着付け教室や呉服屋のエピソードや、P104〜105などに頼れるお店の探し方についてのアドバイスも載っているので、着物に憧れているけれどまず何からしたら良いか分からない方におすすめ。
また、着物には直接関係ないですが、
「わたしにとって足のネイルは、地に足をつけるためのいわば文鎮です。足袋で見えなくなるけどね」
(P17から抜粋)
という著者の言葉に共感しました。
お洒落は活力。
「体にいいと思って食べるのではなく自分がおいしいと思って食べる。頭で食べるのではなく、体で食べる。センサーは自分の舌です。みんなそれを持っているはずなのに、判断を人に預けたり、ブランドに頼ってしまうから感性が鈍る」
(P9から抜粋)
という言葉にハッとさせられました。
おいしいという素直な気持ちを大事にして、「いただきます」と「ごちそうさま」を言いたいですね。
そうしたら心も体もだんだん元気になる気がする。
この本には色んなレシピが載っていて、中でもわたしはP16掲載の「豆乳マヨネーズ」を見た瞬間お腹がぐ〜っと鳴りました。
なたね油または太白ごま油、豆乳、米酢、海塩、てんさい糖、マスタードをブレンダーで攪拌して作るそうです。
サラダにかけたい!
他にもこの本には、運動をする、睡眠をとる、など当たり前のようで意外とちゃんと出来ていないことについて書かれています。
自分で自分を大切に扱ってあげないといけないですね…。
(P9から抜粋)
という言葉にハッとさせられました。
おいしいという素直な気持ちを大事にして、「いただきます」と「ごちそうさま」を言いたいですね。
そうしたら心も体もだんだん元気になる気がする。
この本には色んなレシピが載っていて、中でもわたしはP16掲載の「豆乳マヨネーズ」を見た瞬間お腹がぐ〜っと鳴りました。
なたね油または太白ごま油、豆乳、米酢、海塩、てんさい糖、マスタードをブレンダーで攪拌して作るそうです。
サラダにかけたい!
他にもこの本には、運動をする、睡眠をとる、など当たり前のようで意外とちゃんと出来ていないことについて書かれています。
自分で自分を大切に扱ってあげないといけないですね…。
新品の家具などに、使い込まれたかのような味わいを出しつつも、汚い印象にはならないエイジング加工を施すための本。
シャビーシック、レトロ調、アンティーク調、この3つのテイストが好きな方におすすめ。
ペイントした後に敢えて剥がしたり、ひび割れを作ったり、時の経過と共に錆びたり色褪せた感じを演出する手順の一つ一つが、下準備の仕方も含めてカラー写真付きで紹介されています。
人間の中には妙にアンチエイジングに固執して美容整形をし過ぎる人もいるけれど、家具はエイジングした物の方が落ち着くから不思議です。
人間も歳相応の方が自然で素敵なんですけどね。
歳を重ねるということは、歳の分だけ、懸命に生き抜いてきた証でもありますから。
いわばアンティーク。
シャビーシック、レトロ調、アンティーク調、この3つのテイストが好きな方におすすめ。
ペイントした後に敢えて剥がしたり、ひび割れを作ったり、時の経過と共に錆びたり色褪せた感じを演出する手順の一つ一つが、下準備の仕方も含めてカラー写真付きで紹介されています。
人間の中には妙にアンチエイジングに固執して美容整形をし過ぎる人もいるけれど、家具はエイジングした物の方が落ち着くから不思議です。
人間も歳相応の方が自然で素敵なんですけどね。
歳を重ねるということは、歳の分だけ、懸命に生き抜いてきた証でもありますから。
いわばアンティーク。
「エアコンはどうやって快適な空気をつくっているの?」
「電子レンジはどうやって食べ物を温めているの?」
「バーコードやQRコードのしくみはどうなっているの?」
「飛行機はなぜ空を飛べるの?」
など、なんとなく分かっているつもりでも、誰かに今すぐ正確に説明できるかと言うと自信のないことについて教えてくれる本。
なお、先ほど挙げた例の答えは以下の通り。
エアコンは液体が気体になるときに熱を奪い、気体が液体になるときに熱を放出する現象を利用している。
電子レンジは食べ物の中に含まれる水にマイクロ波を当て、水の分子のプラスとマイナスの電気を反応させることによって水の温度を上昇させ、水のまわりにも熱を波及させることで食べ物を温めている。
バーコードはひとつの数字を表すために白色と黒色の線(モジュール)7本と13桁のJANコードを組み合わせていて、従来のバーコードではせいぜい20桁程度の情報量しか扱えなかったのに対してQRコードはそのバーコードを進化させ1つのコードで数字のみなら最大7089文字を実装可能。
飛行機は推力(前に進む力)、重力(下に引っ張る力)、揚力(浮く力)、抵抗力のバランスによって空を飛んでいる。
こうして改めて考えてみると、現代人は便利な生活を当たり前のように享受しているけれど、そもそもご先祖様たちが色々な科学の仕組みに気づいてそれを応用してくれたからこそ今があるんですよね。
ありがたや。
「電子レンジはどうやって食べ物を温めているの?」
「バーコードやQRコードのしくみはどうなっているの?」
「飛行機はなぜ空を飛べるの?」
など、なんとなく分かっているつもりでも、誰かに今すぐ正確に説明できるかと言うと自信のないことについて教えてくれる本。
なお、先ほど挙げた例の答えは以下の通り。
エアコンは液体が気体になるときに熱を奪い、気体が液体になるときに熱を放出する現象を利用している。
電子レンジは食べ物の中に含まれる水にマイクロ波を当て、水の分子のプラスとマイナスの電気を反応させることによって水の温度を上昇させ、水のまわりにも熱を波及させることで食べ物を温めている。
バーコードはひとつの数字を表すために白色と黒色の線(モジュール)7本と13桁のJANコードを組み合わせていて、従来のバーコードではせいぜい20桁程度の情報量しか扱えなかったのに対してQRコードはそのバーコードを進化させ1つのコードで数字のみなら最大7089文字を実装可能。
飛行機は推力(前に進む力)、重力(下に引っ張る力)、揚力(浮く力)、抵抗力のバランスによって空を飛んでいる。
こうして改めて考えてみると、現代人は便利な生活を当たり前のように享受しているけれど、そもそもご先祖様たちが色々な科学の仕組みに気づいてそれを応用してくれたからこそ今があるんですよね。
ありがたや。