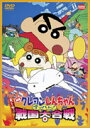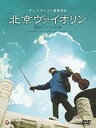ジュゼッペ・トルナトーレ監督 『マレーナ』
2009年4月17日 映画 コメント (4)
こんな方におすすめ:色っぽい美女を見たい方
こんな方にはおすすめしません:非情な展開が嫌な方
女性は女性に対してどこまでも残酷になれる生き物だ・・・、とわたしはこの映画を見ながら改めて感じました。
この映画の冒頭には、虫眼鏡を使って太陽光で蟻を焼き殺す少年たちが登場します。けれど相手の痛みを思いやれないのは大人も同じ。
マレーナは夫と父を戦争によって失いました。町の人々はこれまでずっと彼女を異質な者として見るばかりだったので、彼女が孤独な身となってからも、彼女の心に寄り添ってくれる人は誰もいませんでした。それでも戦争は彼女の気持ちことなどお構いなしにまだまだ続きます。食糧もお金も頼れる人もない戦時中を女一人で生きていくために、マレーナがその美しさを活用して娼婦という道を選択したからといって誰が責められましょうか。
けれど女性たちは群衆の前で彼女の髪を引っ張り、メッタ打ちにし、お腹を蹴り、彼女が口元や膝から血を流し始めてもおかまいなしに暴力をふるい続け、男性も見ている前で彼女の胸を露出させ、泣き叫んで抵抗しようとする彼女を抑えつけながら彼女の髪をほとんど坊主頭の短さに切り・・・、「この町から出て行け!」と叫ぶのでした。
それを男性たちも止めません。
この映画の主人公である少年すらも止めません。
容赦ない制裁を受けたために立ち上がることも容易にはかなわず、ガクガク震え、嗚咽しながらも裸の胸を隠そうとする彼女に、誰も服を着せてあげないし傷も手当てしてくれません。
ただ見ているだけ。
・・・この映画って、「少年が年上の美女に恋をして、その恋心を打ち明けることも出来ずただ彼女を見守り続けた映画」とロマンティックに評されることも多いのですが、少年はただ見ていただけではありませんか!
ただ見ていただけ。
少年は彼女が町から追われた後、戦地から生きて帰ってきた彼女の夫に「みんな彼女を悪く言うけれど、僕は真実を知っている。彼女はあなた一人を愛していた」と教えてくれたけれど・・・。
彼女が悲鳴をあげている間、少年はただ見ていただけではありませんか。
その時少年自身も、彼女をその沈黙と視線によって追い詰める人々のうちの一人になっていたではありませんか。
少年の視線に他の人のような冷たさがないと理解する余裕など、その時の彼女には無かったことでしょう。
そういうこともあってこの映画は見ていると辛くなる映画です。
けれど、彼女は美しい。
集団リンチを受けた町に戻ってくるという彼女の度胸も称賛に値します。
けれど、彼女の心にまで深い深い傷を負わせた女性たちは、町へ戻ってきた彼女の服装が地味になったこと、目尻にシワが出来たこと、彼女が太ったことを見て笑みを浮かべました。そして女性たちは、彼女が女性たちに「こんにちは」と挨拶したその瞬間、満足そうに安堵したように微笑んだのでした。
・・・その微笑みにゾッとします。
女性たちは、「彼女が自分たちと同じ町の女になった」と思ったのでしょうか? それとも「彼女は自分たちが暴力をふるったことを許した」と思ったのでしょうか? ・・・許せるはずなんて無いのに。
けれど女性たちが微笑まなかったら彼女は再び町を追われることになったかもしれないから、女性たちを非難するわけにもいきません・・・。
・・・う~ん・・・。
・・・。
・・・嫌です、やっぱり。
非難したいです!
そして、実際に彼女のような運命を辿った女性たちのために祈りたいです。
イエス・キリストがかつて娼婦へ言ったとされる言葉を思い出しながら・・・。
「もう、それでいい。
わたしはあなたの悲しみを知っている」。
こんな方にはおすすめしません:非情な展開が嫌な方
女性は女性に対してどこまでも残酷になれる生き物だ・・・、とわたしはこの映画を見ながら改めて感じました。
この映画の冒頭には、虫眼鏡を使って太陽光で蟻を焼き殺す少年たちが登場します。けれど相手の痛みを思いやれないのは大人も同じ。
マレーナは夫と父を戦争によって失いました。町の人々はこれまでずっと彼女を異質な者として見るばかりだったので、彼女が孤独な身となってからも、彼女の心に寄り添ってくれる人は誰もいませんでした。それでも戦争は彼女の気持ちことなどお構いなしにまだまだ続きます。食糧もお金も頼れる人もない戦時中を女一人で生きていくために、マレーナがその美しさを活用して娼婦という道を選択したからといって誰が責められましょうか。
けれど女性たちは群衆の前で彼女の髪を引っ張り、メッタ打ちにし、お腹を蹴り、彼女が口元や膝から血を流し始めてもおかまいなしに暴力をふるい続け、男性も見ている前で彼女の胸を露出させ、泣き叫んで抵抗しようとする彼女を抑えつけながら彼女の髪をほとんど坊主頭の短さに切り・・・、「この町から出て行け!」と叫ぶのでした。
それを男性たちも止めません。
この映画の主人公である少年すらも止めません。
容赦ない制裁を受けたために立ち上がることも容易にはかなわず、ガクガク震え、嗚咽しながらも裸の胸を隠そうとする彼女に、誰も服を着せてあげないし傷も手当てしてくれません。
ただ見ているだけ。
・・・この映画って、「少年が年上の美女に恋をして、その恋心を打ち明けることも出来ずただ彼女を見守り続けた映画」とロマンティックに評されることも多いのですが、少年はただ見ていただけではありませんか!
ただ見ていただけ。
少年は彼女が町から追われた後、戦地から生きて帰ってきた彼女の夫に「みんな彼女を悪く言うけれど、僕は真実を知っている。彼女はあなた一人を愛していた」と教えてくれたけれど・・・。
彼女が悲鳴をあげている間、少年はただ見ていただけではありませんか。
その時少年自身も、彼女をその沈黙と視線によって追い詰める人々のうちの一人になっていたではありませんか。
少年の視線に他の人のような冷たさがないと理解する余裕など、その時の彼女には無かったことでしょう。
そういうこともあってこの映画は見ていると辛くなる映画です。
けれど、彼女は美しい。
集団リンチを受けた町に戻ってくるという彼女の度胸も称賛に値します。
けれど、彼女の心にまで深い深い傷を負わせた女性たちは、町へ戻ってきた彼女の服装が地味になったこと、目尻にシワが出来たこと、彼女が太ったことを見て笑みを浮かべました。そして女性たちは、彼女が女性たちに「こんにちは」と挨拶したその瞬間、満足そうに安堵したように微笑んだのでした。
・・・その微笑みにゾッとします。
女性たちは、「彼女が自分たちと同じ町の女になった」と思ったのでしょうか? それとも「彼女は自分たちが暴力をふるったことを許した」と思ったのでしょうか? ・・・許せるはずなんて無いのに。
けれど女性たちが微笑まなかったら彼女は再び町を追われることになったかもしれないから、女性たちを非難するわけにもいきません・・・。
・・・う~ん・・・。
・・・。
・・・嫌です、やっぱり。
非難したいです!
そして、実際に彼女のような運命を辿った女性たちのために祈りたいです。
イエス・キリストがかつて娼婦へ言ったとされる言葉を思い出しながら・・・。
「もう、それでいい。
わたしはあなたの悲しみを知っている」。
ソフィア・コッポラ監督 『マリー・アントワネット』
2009年2月8日 映画
わたしはこの映画に感謝しています。
ルイ16世を好きになれたから。
いい人そうではあるけれどいい男ではない。
それが今までのわたしのルイ16世に対するイメージ。
いい人そうではあるけれどいい男ではない、それはこの映画の中でも同じ。
パッと見、冴えないです。(俳優さんごめんなさい)
ルイ16世と初めて会った時、マリーは落胆の表情を浮かべているように見えます。
ルイ16世は結婚初夜も含めそれ以降もずっと、マリーに手を出しませんでした。
当然マリーは妊娠できません。
マリーはただでさえ故国オーストリアの敵国フランスに独りぼっちであり、王太子妃の義務として子を産まなければならない重責があるというのに、ルイ16世がその気にならないのですからどうしようもありません。
人々はマリーのことを「不妊症」と噂します。そもそも一度の結びつきさえないというのに。
その噂はマリーの耳にも入りました。もしかしたらマリーは、自分には女としての魅力が無いのではないか・・・だからこんなことになってしまったのではないか・・・と考えたこともあるかもしれません。当時における14、15歳の花嫁にとってとても辛い想像です。お付きの者の「子を産めない王妃は婚姻を解消されることもある」という言葉も、母からの「あなたの新しい家庭での本質的問題はあなたが夫の性的情熱を刺激できずにいることです。あなたほど魅力に溢れる女性にとってあるまじき事態です」という手紙も、マリーを追い詰めました。マリーははけぐちを求めて買い物や夜会に没頭。
それでもルイ16世は毎晩マリーとベッドの中で眠るだけ・・・。
と、ここまでは他の映像作品でも描かれます。しかしこの映画はルイ16世を好きにさせてくれます。
この映画の中で、マリーと仲良さそうではあるのにマリーに手を出そうとすらしないルイ16世は、なぜかベッドの中に錠前を持ち込み、錠前をジッと見つめているのです。ルイ16世の趣味は狩りと錠前作り。いくら趣味だからって、なぜベッドの中に錠前を持ち込むの? 答えは後々明らかになります。
この映画の中で、ルイ16世は「素晴らしいものに対して拍手をするのは当たり前」というマリーの素直さに惚れたように見えます。ルイ16世は自分がマリーに課してしまった悲しみを取り除きたいと決心し、ついにマリーの上に乗ります。わたしはこのシーンを見て拍手しました!(←自宅で見たので・・・) マリーの上にはルイ16世。ルイ16世の下には笑顔のマリー。「やった! もうすぐご懐妊の場面が見られるぞ~っ」と・・・思い・・・きや・・・アレ? ルイ16世はマリーの上からおりてしまいました!! ルイ16世はマリーに謝りました。
それから大分経ってから、ようやくマリーの兄ヨーゼフ2世が登場。もっと早く登場してくださいましお兄様、と思ったのはわたしですがマリーも思ったかもしれません。ヨーゼフ2世の助言により、ルイ16世の誰にも言えなかった悩みは軽やかに解決。ルイ16世はゲイではありませんでした、真性・・・だったのです(何なのかわからない人はネットか親に聞きましょう)。マリーの上に一度乗った時は、成し遂げようと決意していたものの激痛に耐えられなかったのかもしれませんね。ルイ16世はこの悩みについて何度か医師に相談したようですが、医師としてはやんごとなき御方であらせられるルイ16世が真性・・・だとは診断し辛かったのでしょう。当時のフランスでは今のように真性・・・の手術は確立されていなかったようですし。この映画では描かれませんが、文献によるとヨーゼフ2世が手術という手があると教えたらしいです。
その後・・・。ベッドへ向かうルイ16世の足取りがいつもと違うようです。背中がまっすぐ。勝負に挑む感じです。お! なんか男らしくベッドに入りましたよ。再び、マリーの上にはルイ16世。ルイ16世の下には笑顔のマリー。「頑張れ~!」わたしはテレビの画面前に寄って声援を送りました。嗚呼、映画のベッドシーンを応援するなんて生まれて初めてです。ルイ16世はマリーにチュッ、チュッ、チュッとキス。マリーも幸せそう。テレビの画面を見つめるわたしはニヤニヤしました。嗚呼、ルイ16世も悩んでいたんだ、マリーとずっとこうしたかったんだ、と思うと・・・おや? おかしいな。映画のベッドシーンを見て涙ぐむなど前代未聞っ。
マリーは懐妊。良かったね良かったね・・・! 出産の際、出産を見守る人が部屋の中に大勢いることもあって、マリーは酸欠で気を失いそうになりました。素早く部屋の窓を開けたのはルイ16世。他の誰も窓を開けようとしなかったというのに、王自ら。窓を開けた後、ルイ16世はマリーの手を両手で優しく握り、マリーの手にキスをしました。「嗚呼、いい人そうだけどいい男じゃないなんて言って悪かったよ。あんたいい男だよ!」とわたしはこのシーンをジ~ンとしながら見ました。
子どもが生まれてからはマリーの浪費も治まり、夫婦は仲睦ましくなりました。マリーとフェルゼンが秘めた恋をしたとはいえ、今までと比べて大きな進歩です。ルイ16世は、マリーがプチトリアンで披露する下手なお芝居にも、王自らいち早く立ち上がって拍手。これでめでたしめでたし・・・となれば良かったのですがフランス革命が起こるんですよね・・・。(><)
わたしの乏しい文章力では上手く書けなかったのですが、わたしはこの映画を見てルイ16世を好きになりました。体での結びつきは遅かったし、心での結びつきもマリーにとってはわかりにくいものだったけれど、ルイ16世のマリーへの優しさが随所に表れていて。
この映画のコンセプトは「マリー・アントワネットを身近に感じて欲しい」だと思うのですが、ルイ16世についても身近に感じることが出来たと思います。子どもが出来ずに悩んでいるカップルは今もたくさんいますしね。
――――――――――――――――――――――――――――――
<余談>
ランバル公妃役は、『ミネハハ 秘密の森の少女たち』(以前わたしが書いたレビューはこちら→http://20756.diarynote.jp/200805241312230000/)でヒダラ役をやったメアリー・ナイさんなんですね。
彼女はあの映画の中で、いくらそういう役だとしても悲惨な目に遭っていたので、正直わたしは心配していました。映画を嫌いになりはしないだろうか、と。
けれどミネハハの後『マリー・アントワネット』にも出演なさっていることを知り、安心しました。ランバル公妃はとかく孤独になりがちなマリーを優しく支えてくれる役ですよね。ぴったりだと思いました。今後も応援していきたいです。
ルイ16世を好きになれたから。
いい人そうではあるけれどいい男ではない。
それが今までのわたしのルイ16世に対するイメージ。
いい人そうではあるけれどいい男ではない、それはこの映画の中でも同じ。
パッと見、冴えないです。(俳優さんごめんなさい)
ルイ16世と初めて会った時、マリーは落胆の表情を浮かべているように見えます。
ルイ16世は結婚初夜も含めそれ以降もずっと、マリーに手を出しませんでした。
当然マリーは妊娠できません。
マリーはただでさえ故国オーストリアの敵国フランスに独りぼっちであり、王太子妃の義務として子を産まなければならない重責があるというのに、ルイ16世がその気にならないのですからどうしようもありません。
人々はマリーのことを「不妊症」と噂します。そもそも一度の結びつきさえないというのに。
その噂はマリーの耳にも入りました。もしかしたらマリーは、自分には女としての魅力が無いのではないか・・・だからこんなことになってしまったのではないか・・・と考えたこともあるかもしれません。当時における14、15歳の花嫁にとってとても辛い想像です。お付きの者の「子を産めない王妃は婚姻を解消されることもある」という言葉も、母からの「あなたの新しい家庭での本質的問題はあなたが夫の性的情熱を刺激できずにいることです。あなたほど魅力に溢れる女性にとってあるまじき事態です」という手紙も、マリーを追い詰めました。マリーははけぐちを求めて買い物や夜会に没頭。
それでもルイ16世は毎晩マリーとベッドの中で眠るだけ・・・。
と、ここまでは他の映像作品でも描かれます。しかしこの映画はルイ16世を好きにさせてくれます。
この映画の中で、マリーと仲良さそうではあるのにマリーに手を出そうとすらしないルイ16世は、なぜかベッドの中に錠前を持ち込み、錠前をジッと見つめているのです。ルイ16世の趣味は狩りと錠前作り。いくら趣味だからって、なぜベッドの中に錠前を持ち込むの? 答えは後々明らかになります。
この映画の中で、ルイ16世は「素晴らしいものに対して拍手をするのは当たり前」というマリーの素直さに惚れたように見えます。ルイ16世は自分がマリーに課してしまった悲しみを取り除きたいと決心し、ついにマリーの上に乗ります。わたしはこのシーンを見て拍手しました!(←自宅で見たので・・・) マリーの上にはルイ16世。ルイ16世の下には笑顔のマリー。「やった! もうすぐご懐妊の場面が見られるぞ~っ」と・・・思い・・・きや・・・アレ? ルイ16世はマリーの上からおりてしまいました!! ルイ16世はマリーに謝りました。
それから大分経ってから、ようやくマリーの兄ヨーゼフ2世が登場。もっと早く登場してくださいましお兄様、と思ったのはわたしですがマリーも思ったかもしれません。ヨーゼフ2世の助言により、ルイ16世の誰にも言えなかった悩みは軽やかに解決。ルイ16世はゲイではありませんでした、真性・・・だったのです(何なのかわからない人はネットか親に聞きましょう)。マリーの上に一度乗った時は、成し遂げようと決意していたものの激痛に耐えられなかったのかもしれませんね。ルイ16世はこの悩みについて何度か医師に相談したようですが、医師としてはやんごとなき御方であらせられるルイ16世が真性・・・だとは診断し辛かったのでしょう。当時のフランスでは今のように真性・・・の手術は確立されていなかったようですし。この映画では描かれませんが、文献によるとヨーゼフ2世が手術という手があると教えたらしいです。
その後・・・。ベッドへ向かうルイ16世の足取りがいつもと違うようです。背中がまっすぐ。勝負に挑む感じです。お! なんか男らしくベッドに入りましたよ。再び、マリーの上にはルイ16世。ルイ16世の下には笑顔のマリー。「頑張れ~!」わたしはテレビの画面前に寄って声援を送りました。嗚呼、映画のベッドシーンを応援するなんて生まれて初めてです。ルイ16世はマリーにチュッ、チュッ、チュッとキス。マリーも幸せそう。テレビの画面を見つめるわたしはニヤニヤしました。嗚呼、ルイ16世も悩んでいたんだ、マリーとずっとこうしたかったんだ、と思うと・・・おや? おかしいな。映画のベッドシーンを見て涙ぐむなど前代未聞っ。
マリーは懐妊。良かったね良かったね・・・! 出産の際、出産を見守る人が部屋の中に大勢いることもあって、マリーは酸欠で気を失いそうになりました。素早く部屋の窓を開けたのはルイ16世。他の誰も窓を開けようとしなかったというのに、王自ら。窓を開けた後、ルイ16世はマリーの手を両手で優しく握り、マリーの手にキスをしました。「嗚呼、いい人そうだけどいい男じゃないなんて言って悪かったよ。あんたいい男だよ!」とわたしはこのシーンをジ~ンとしながら見ました。
子どもが生まれてからはマリーの浪費も治まり、夫婦は仲睦ましくなりました。マリーとフェルゼンが秘めた恋をしたとはいえ、今までと比べて大きな進歩です。ルイ16世は、マリーがプチトリアンで披露する下手なお芝居にも、王自らいち早く立ち上がって拍手。これでめでたしめでたし・・・となれば良かったのですがフランス革命が起こるんですよね・・・。(><)
わたしの乏しい文章力では上手く書けなかったのですが、わたしはこの映画を見てルイ16世を好きになりました。体での結びつきは遅かったし、心での結びつきもマリーにとってはわかりにくいものだったけれど、ルイ16世のマリーへの優しさが随所に表れていて。
この映画のコンセプトは「マリー・アントワネットを身近に感じて欲しい」だと思うのですが、ルイ16世についても身近に感じることが出来たと思います。子どもが出来ずに悩んでいるカップルは今もたくさんいますしね。
――――――――――――――――――――――――――――――
<余談>
ランバル公妃役は、『ミネハハ 秘密の森の少女たち』(以前わたしが書いたレビューはこちら→http://20756.diarynote.jp/200805241312230000/)でヒダラ役をやったメアリー・ナイさんなんですね。
彼女はあの映画の中で、いくらそういう役だとしても悲惨な目に遭っていたので、正直わたしは心配していました。映画を嫌いになりはしないだろうか、と。
けれどミネハハの後『マリー・アントワネット』にも出演なさっていることを知り、安心しました。ランバル公妃はとかく孤独になりがちなマリーを優しく支えてくれる役ですよね。ぴったりだと思いました。今後も応援していきたいです。
矢口史靖監督 『ハッピー・フライト』
2008年12月4日 映画 『ハッピー・フライト』(公式HP→http://www.happyflight.jp/index.html)、映画館で見て参りました。
予想以上に面白かったです。
わたしは明日実際にANAに乗るのですが、乗るのが楽しみになりました。
また映画館で見たい作品です。
わたしはまだ1度しか見ていないのですが、わたしが思うにこの映画は、
<こういう人におすすめ>
きびきび働いている人を見るのが好き。
その仕事ならではの楽しみを知るのが好き。
気楽に笑えて、たまにドキドキさせてくれるものが好き。
<こういう人にはおすすめ出来ないかも>
主人公の視点でのみ物語が進行しないと集中出来ない。
仕事で足を引っ張っているのにその自覚がない新人を許せない。
飛行機が揺れるのが怖い。そもそも乗るのが怖い。
<こういう映画だろうな・・・という感想>
ANAによるANAのためのお仕事宣伝映画。
この映画によってANAは、「台風が発生したり、飛行機に鳥がぶつかるなど、色んなトラブルが起こる可能性がある。多くの部署がある中で、幾つかヒューマンエラーが起きることだってある。しかしどんな場合でも、各部署が連携して補い合い、安全に運行しますよ」と言いたいのだと思います。
わたしはだからこそ、ANAが言いたいことを踏まえた上で娯楽として楽しめる映画を作れる監督として、矢口監督が起用されたのだと思います。
もしも飛行中にトラブルが発生するシーンをひどく緊迫したものに描いてしまう監督を起用してしまったら、この映画を見た人が「飛行機に乗りたくない」と思ってしまう可能性が高いですから。それでは意味がありません。各部署が愚痴を言いつつも信頼し合ってトラブルを解決する様子を、あくまでも気楽に見せてくれなくては。
その辺、矢口監督は上手いですね。
「各部署がこういう仕事をしているから安全に飛行機は飛びます」ということを伝えるため、各部署で働く人たちをどんどん登場させ、その人たちにコミカルさを与えることにより、乗客として飛行機に乗る際じっくり向き合うことのないスタッフたちに親近感を抱かせることにも成功していると思います。
ただしわたしは、綾瀬はるかさんが演じるキャビンアテンダントさんの悪気のないドジっぷりは他から浮きすぎかな、と感じます。他がしっかり仕事をしている分、1人くらいはドジな人がいないと娯楽として成立しないのかもしれませんが。わたしは正直言って「国内線にだってあんなキャビンアテンダントさんはいないだろうに、国際線にいるの?」と思い、せっかく映画に引き込まれていた思考が現実に引き戻されてしまいました。
<以下、徒然なるままに感想を書きます>
●笹野さんが演じるカツラがバレバレな乗客が、座席に置いてある非常時のマニュアルを見て、自分そっくりのイラストが描かれているのを見て「ウッ」となっているのが面白いです。わたしも自分そっくり、或いは知人そっくりのイラストが無いか見てみます。
●わたしは田畑さんの演じているグランドホステスさんに最も親近感を抱きました。わたしはもともと田畑さんが好きですし。あのグランドホステスさんはその後、あのお客さんと恋に発展したのでしょうか?
●映画のタイトルに「ハッピー」が付くのはおかしいのでは? 乗客にとってはアン・ハッピー・フライトでしょうに。
●吹石さんの美しさに惚れぼれ。
●岸部さん演じるオペレーションセンターのおじさん(?)、かっこいいですね。普段は冴えないおじさん、でもピンチになると・・・冴え渡る!
●菅原さんの豹変ぶりが凄い。役者さんって凄いなと感じました。
●たった数秒のシーンに竹中さんが出演するとは・・・!
予想以上に面白かったです。
わたしは明日実際にANAに乗るのですが、乗るのが楽しみになりました。
また映画館で見たい作品です。
わたしはまだ1度しか見ていないのですが、わたしが思うにこの映画は、
<こういう人におすすめ>
きびきび働いている人を見るのが好き。
その仕事ならではの楽しみを知るのが好き。
気楽に笑えて、たまにドキドキさせてくれるものが好き。
<こういう人にはおすすめ出来ないかも>
主人公の視点でのみ物語が進行しないと集中出来ない。
仕事で足を引っ張っているのにその自覚がない新人を許せない。
飛行機が揺れるのが怖い。そもそも乗るのが怖い。
<こういう映画だろうな・・・という感想>
ANAによるANAのためのお仕事宣伝映画。
この映画によってANAは、「台風が発生したり、飛行機に鳥がぶつかるなど、色んなトラブルが起こる可能性がある。多くの部署がある中で、幾つかヒューマンエラーが起きることだってある。しかしどんな場合でも、各部署が連携して補い合い、安全に運行しますよ」と言いたいのだと思います。
わたしはだからこそ、ANAが言いたいことを踏まえた上で娯楽として楽しめる映画を作れる監督として、矢口監督が起用されたのだと思います。
もしも飛行中にトラブルが発生するシーンをひどく緊迫したものに描いてしまう監督を起用してしまったら、この映画を見た人が「飛行機に乗りたくない」と思ってしまう可能性が高いですから。それでは意味がありません。各部署が愚痴を言いつつも信頼し合ってトラブルを解決する様子を、あくまでも気楽に見せてくれなくては。
その辺、矢口監督は上手いですね。
「各部署がこういう仕事をしているから安全に飛行機は飛びます」ということを伝えるため、各部署で働く人たちをどんどん登場させ、その人たちにコミカルさを与えることにより、乗客として飛行機に乗る際じっくり向き合うことのないスタッフたちに親近感を抱かせることにも成功していると思います。
ただしわたしは、綾瀬はるかさんが演じるキャビンアテンダントさんの悪気のないドジっぷりは他から浮きすぎかな、と感じます。他がしっかり仕事をしている分、1人くらいはドジな人がいないと娯楽として成立しないのかもしれませんが。わたしは正直言って「国内線にだってあんなキャビンアテンダントさんはいないだろうに、国際線にいるの?」と思い、せっかく映画に引き込まれていた思考が現実に引き戻されてしまいました。
<以下、徒然なるままに感想を書きます>
●笹野さんが演じるカツラがバレバレな乗客が、座席に置いてある非常時のマニュアルを見て、自分そっくりのイラストが描かれているのを見て「ウッ」となっているのが面白いです。わたしも自分そっくり、或いは知人そっくりのイラストが無いか見てみます。
●わたしは田畑さんの演じているグランドホステスさんに最も親近感を抱きました。わたしはもともと田畑さんが好きですし。あのグランドホステスさんはその後、あのお客さんと恋に発展したのでしょうか?
●映画のタイトルに「ハッピー」が付くのはおかしいのでは? 乗客にとってはアン・ハッピー・フライトでしょうに。
●吹石さんの美しさに惚れぼれ。
●岸部さん演じるオペレーションセンターのおじさん(?)、かっこいいですね。普段は冴えないおじさん、でもピンチになると・・・冴え渡る!
●菅原さんの豹変ぶりが凄い。役者さんって凄いなと感じました。
●たった数秒のシーンに竹中さんが出演するとは・・・!
テリー・ギリアム監督 『ブラザーズ・グリム』
2008年10月19日 映画 コメント (2)原恵一監督 『映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ! 戦国大合戦』
2008年10月16日 映画
廉姫はしんのすけに問いました。
「そなたたちの世界の男女はどのように恋をする」
しんのすけは廉姫に答えました。
「21世紀ではお互いに好きになればいいんだよ」
・・・しんのすけもいつか、たとえ時代が21世紀になろうとも、お互いに好き合っている男女が必ずしも結ばれるわけではないことを知るのでしょうか。
そんな想いを、しんのすけには知らないで欲しい。
・・・この映画を見てそう思った大人は少なくないことでしょう。
身分の違いという障害が少なくなった分、少しは21世紀の方がましなのかもしれませんが、恋の苦しさが変わるはずもない。
廉姫は呟きました。
「それにしても不思議。北と南で生まれた二人が、江戸と出逢い夫婦となって・・・。春日のわたしの、一番好きな場所に住んでいるなんて。だからこそ、あなたたち家族はそんなにも仲睦まじく幸せなのだと思いたい。だとしたら、わたしは嬉しい。本当に」
その場所を一番好きな理由。
だからこそ、という言葉の意味。
・・・又兵衛は知っていたのに。
「そなたたちの世界の男女はどのように恋をする」
しんのすけは廉姫に答えました。
「21世紀ではお互いに好きになればいいんだよ」
・・・しんのすけもいつか、たとえ時代が21世紀になろうとも、お互いに好き合っている男女が必ずしも結ばれるわけではないことを知るのでしょうか。
そんな想いを、しんのすけには知らないで欲しい。
・・・この映画を見てそう思った大人は少なくないことでしょう。
身分の違いという障害が少なくなった分、少しは21世紀の方がましなのかもしれませんが、恋の苦しさが変わるはずもない。
廉姫は呟きました。
「それにしても不思議。北と南で生まれた二人が、江戸と出逢い夫婦となって・・・。春日のわたしの、一番好きな場所に住んでいるなんて。だからこそ、あなたたち家族はそんなにも仲睦まじく幸せなのだと思いたい。だとしたら、わたしは嬉しい。本当に」
その場所を一番好きな理由。
だからこそ、という言葉の意味。
・・・又兵衛は知っていたのに。
監督・・・ボビー・ファレリー&ピーター・ファレリー 『愛しのローズマリー』
2008年9月28日 映画
催眠術にかかりたくなる映画。
特に「自分だって自分の外見に自信がなくて苦しんでいるのに、交際相手を外見で選ぼうとしてしまう・・・」と悩んでいる方に見ていただきたい映画です。
以下はあらすじ。
「若くてキレイでスタイル抜群のねえちゃんとしか付き合うな」という父の遺言のせいで、主人公ハルは女性の外見にしか惹かれません。
彼はお世辞にも格好いい男性とはいえません。しかし彼は外見の良い女性にだけアプローチし、振られまくります。好みの女性としてミシェル・ファイファーなどの名前を列挙することからも理想の高さがわかります。彼は、外見が悪いけれど内面の良い女性には見向きもしません。彼はこれまでそんな人生を送ってきたし、これからも送る気満々。
偶然彼とエレベーターに乗り合わせたセラピストは、彼に催眠術をかけました。
女性の内面しか見えなくなる催眠術を。
内面の醜い女性は醜く、内面の美しい女性は美しく見えるようになるのです。
この催眠術にかかった彼は素晴らしい女性ローズマリーと出逢います。彼女は眩いばかりに美しく、優しく、知的で、ユーモアたっぷり。2人は付き合い始めました。交際は順調。
しかし催眠術は解けてしまいました。
この映画の素晴らしいところは、この後の展開。
彼は催眠術が解けてしまったことによって、ローズマリーの本当の体格を知ります。目にワセリン(?)を塗っていたので顔は見えませんでしたが、体格はバッチリ見えました。凄まじい巨漢でした。
けれど彼はそこで彼女を諦めたりはしませんでした。
彼にとって彼女は既にかけがえのない存在になっていたからです。
彼はまず、あのセラピストに同じ催眠術をもう一度かけてもらおうと試みました。しかしあのセラピストは忙しい為、居所さえ掴めません。そうこうしているうちに彼は、彼女が平和部隊に入隊してキリバスへ発つことを知ります。
もう催眠術をかけてもらう時間などない。
彼は彼女の本当の顔と直面することを恐れながらも、彼女に会いに行きます。
まだこの映画を見ていない方のために、結末は書かないでおきます。
ただ、これだけは書かせてください。わたしがこの映画の中で最も素晴らしいと感じたのは、彼も彼女も彼ららしい姿のままで生きていくということです。
特に「自分だって自分の外見に自信がなくて苦しんでいるのに、交際相手を外見で選ぼうとしてしまう・・・」と悩んでいる方に見ていただきたい映画です。
以下はあらすじ。
「若くてキレイでスタイル抜群のねえちゃんとしか付き合うな」という父の遺言のせいで、主人公ハルは女性の外見にしか惹かれません。
彼はお世辞にも格好いい男性とはいえません。しかし彼は外見の良い女性にだけアプローチし、振られまくります。好みの女性としてミシェル・ファイファーなどの名前を列挙することからも理想の高さがわかります。彼は、外見が悪いけれど内面の良い女性には見向きもしません。彼はこれまでそんな人生を送ってきたし、これからも送る気満々。
偶然彼とエレベーターに乗り合わせたセラピストは、彼に催眠術をかけました。
女性の内面しか見えなくなる催眠術を。
内面の醜い女性は醜く、内面の美しい女性は美しく見えるようになるのです。
この催眠術にかかった彼は素晴らしい女性ローズマリーと出逢います。彼女は眩いばかりに美しく、優しく、知的で、ユーモアたっぷり。2人は付き合い始めました。交際は順調。
しかし催眠術は解けてしまいました。
この映画の素晴らしいところは、この後の展開。
彼は催眠術が解けてしまったことによって、ローズマリーの本当の体格を知ります。目にワセリン(?)を塗っていたので顔は見えませんでしたが、体格はバッチリ見えました。凄まじい巨漢でした。
けれど彼はそこで彼女を諦めたりはしませんでした。
彼にとって彼女は既にかけがえのない存在になっていたからです。
彼はまず、あのセラピストに同じ催眠術をもう一度かけてもらおうと試みました。しかしあのセラピストは忙しい為、居所さえ掴めません。そうこうしているうちに彼は、彼女が平和部隊に入隊してキリバスへ発つことを知ります。
もう催眠術をかけてもらう時間などない。
彼は彼女の本当の顔と直面することを恐れながらも、彼女に会いに行きます。
まだこの映画を見ていない方のために、結末は書かないでおきます。
ただ、これだけは書かせてください。わたしがこの映画の中で最も素晴らしいと感じたのは、彼も彼女も彼ららしい姿のままで生きていくということです。
中島哲也監督 『嫌われ松子の一生』
2008年8月12日 映画
龍洋一は「神様」がいなくなった場所で新約聖書を読み続けるのでしょうか。
「神様」のいない世界が、自分にとって意味のないものであっても。
「神様」を死に至らしめた自分が、自分にとって殴りつけても構わない存在であっても。
ここは「神様」がもう一度世界を愛そうとした場所だから、
この世界のこの場所に居たい。
・・・龍洋一はそう思って生きていってくれるでしょうか。
「神様」のいない世界が、自分にとって意味のないものであっても。
「神様」を死に至らしめた自分が、自分にとって殴りつけても構わない存在であっても。
ここは「神様」がもう一度世界を愛そうとした場所だから、
この世界のこの場所に居たい。
・・・龍洋一はそう思って生きていってくれるでしょうか。
押井守監督 『スカイ・クロラ』
2008年8月6日 映画
画像は『カウントダウン・オブ・「スカイ・クロラ」』より。
*注*
わたしは原作を読んだことがありません。
以下は映画を見て、わたしがわたしなりにキルドレを解釈した文です。
正しいとは限りません。
ネタバレ注意。
キルドレは突然変異によって生まれた「戦争で死なない限り死なない人間」ではない・・・、わたしにはそう思えました。
彼らはその死の理由が戦争であっても戦争でなくても死ぬ。けれどそれは、完全なる死ではない。
体を再利用されている。
人為的な輪廻転生。
この世界は、そういう技術を持った世界。
キルドレは、戦争というショーを全人類に魅せる為に作り出された、全人類が所有する奴隷のようなもの。
だからキルドレは人間扱いしてもらえない。
生きる自由も死ぬ自由もないから。
人々はキルドレの戦いを見て、「自分たちには生きる自由も死ぬ自由もある」と優越感に浸る。
キルドレは、戦争をするため子どもの頃から戦闘機に乗せられる。
戦争であるからには、いつ敵に殺されてもおかしくない。
子どもの頃から日常的に戦っているから、全員が大人になるまでに戦死してしまう。
だから、キルドレは「永遠に大人にならない子ども」と呼ばれる。
復活したキルドレは新たな名を与えられ、以前居た基地にやって来る。
本人は最初からその名を持っていたつもりだし、新しく配属されてきたつもりだ。
基地の人間もそのことを理解しているし、そのキルドレが以前の記憶を持たないとわかっているので、基地の人間はそのキルドレを新しい配属者として扱う。
けれど。死んでしまえば脳の中の記憶は消失するとはいえ、記憶を覚えているのは脳だけではない。体にも記憶というものは染み付いている。だから、キルドレは以前していた行動を繰り返す。
例えば、マッチを折ってから捨てる癖。
例えば、新聞を几張面に折りたたむ癖。
そして、同じ人間を愛す。
愛する人もやがては死んで違う人間になり、自分もまた違う人間になっていく。
それでもまた愛し合う。
そんな繰り返しの日々を変えたいと願う。
「生きる自由、死ぬ自由、愛する自由を望む自分」でいる自由が欲しい。
「空で戦っていない時も生きていることを実感できる自分」になりたい。
だからキルドレは「決して勝てない敵」に挑む。
挑んで、たとえ散ろうとも、また挑み続ける。
空の上で。
−−−−−−−−−
興味のある方は是非劇場でご覧になってはいかがでしょうか。
テーマからいっても、御自身が1日でも若いうちに見た方が良いです。
寂しくも美しいオルゴールの音色だけでも、聴きに行く価値あり。レクイエムでありながらも子守唄でもある、そんな音色は稀少です。是非あの音色に体を包まれてみてください。
わたしは上記(「−」の区切りの上)を恋愛メインで書いていますが、実際は戦争の是非も問いかけてくる映画です。
*注*
わたしは原作を読んだことがありません。
以下は映画を見て、わたしがわたしなりにキルドレを解釈した文です。
正しいとは限りません。
ネタバレ注意。
キルドレは突然変異によって生まれた「戦争で死なない限り死なない人間」ではない・・・、わたしにはそう思えました。
彼らはその死の理由が戦争であっても戦争でなくても死ぬ。けれどそれは、完全なる死ではない。
体を再利用されている。
人為的な輪廻転生。
この世界は、そういう技術を持った世界。
キルドレは、戦争というショーを全人類に魅せる為に作り出された、全人類が所有する奴隷のようなもの。
だからキルドレは人間扱いしてもらえない。
生きる自由も死ぬ自由もないから。
人々はキルドレの戦いを見て、「自分たちには生きる自由も死ぬ自由もある」と優越感に浸る。
キルドレは、戦争をするため子どもの頃から戦闘機に乗せられる。
戦争であるからには、いつ敵に殺されてもおかしくない。
子どもの頃から日常的に戦っているから、全員が大人になるまでに戦死してしまう。
だから、キルドレは「永遠に大人にならない子ども」と呼ばれる。
復活したキルドレは新たな名を与えられ、以前居た基地にやって来る。
本人は最初からその名を持っていたつもりだし、新しく配属されてきたつもりだ。
基地の人間もそのことを理解しているし、そのキルドレが以前の記憶を持たないとわかっているので、基地の人間はそのキルドレを新しい配属者として扱う。
けれど。死んでしまえば脳の中の記憶は消失するとはいえ、記憶を覚えているのは脳だけではない。体にも記憶というものは染み付いている。だから、キルドレは以前していた行動を繰り返す。
例えば、マッチを折ってから捨てる癖。
例えば、新聞を几張面に折りたたむ癖。
そして、同じ人間を愛す。
愛する人もやがては死んで違う人間になり、自分もまた違う人間になっていく。
それでもまた愛し合う。
そんな繰り返しの日々を変えたいと願う。
「生きる自由、死ぬ自由、愛する自由を望む自分」でいる自由が欲しい。
「空で戦っていない時も生きていることを実感できる自分」になりたい。
だからキルドレは「決して勝てない敵」に挑む。
挑んで、たとえ散ろうとも、また挑み続ける。
空の上で。
−−−−−−−−−
興味のある方は是非劇場でご覧になってはいかがでしょうか。
テーマからいっても、御自身が1日でも若いうちに見た方が良いです。
寂しくも美しいオルゴールの音色だけでも、聴きに行く価値あり。レクイエムでありながらも子守唄でもある、そんな音色は稀少です。是非あの音色に体を包まれてみてください。
わたしは上記(「−」の区切りの上)を恋愛メインで書いていますが、実際は戦争の是非も問いかけてくる映画です。
ジェフ・シェイファー監督 『ユーロ・トリップ』
2008年7月4日 映画
*注*
実年齢18歳以上、精神年齢20歳以上の方にしかおすすめ出来ない映画です。
Scotty doesn’t know♪ Scotty doesn’t know♪ Scotty doesn’t kno〜w〜♪
マット・デイモンが歌うこの曲が鼻歌に出るようになったら、あなたも「お馬鹿映画好き」の仲間入り! あれ? 嬉しくない?(^皿^)
マット・デイモンは主人公スコッティーから彼女を奪って「スッコティーは知らねえ 毎週末俺が彼女と車で(以下略) 教会に行くと言って(以下略) 奴の誕生日に(以下略)」と歌うのです。その歌をスコッティーが聴いてしまったので歌詞を「Skotty does know」に変えるべきなのですが、変えたら余計悲惨さがアップするのでやめておきましょう。マット・デイモンがやたら楽しそうなのが何よりです。今ではもう周りが止めてしまうので、こんなB級お馬鹿映画には出られないでしょう。一生の記念ですね♪(^皿^)b
何たってこの『ユーロ・トリップ』は青春お馬鹿映画の傑作です。
健全な青少年としてのエロネタ、ゲイネタ、フーリガンネタのみならず、ドイツの口髭が生えてて右腕上げてるあの人のネタや、教皇が亡くなったことを知らせる鐘を鳴らしちゃったりと不謹慎の極みなのに、うまいこと爽やかに仕上がっている傑作なのです。
<あらすじ>
主人公たちは高校を卒業したばかりの若者4人。4人のうち3人がノーマルな男性。1人はノーマルな女性。
彼らはメル友に会うためアメリカからベルリンを目指して旅立ちました。
しかしなかなかベルリンまで辿り着きません!
しかしくれぐれも実年齢18歳以上、精神年齢20歳以上じゃないと見ちゃダメですよー。これに該当する方も、家族や恋人と一緒に見ないようにお気をつけください♪
実年齢18歳以上、精神年齢20歳以上の方にしかおすすめ出来ない映画です。
Scotty doesn’t know♪ Scotty doesn’t know♪ Scotty doesn’t kno〜w〜♪
マット・デイモンが歌うこの曲が鼻歌に出るようになったら、あなたも「お馬鹿映画好き」の仲間入り! あれ? 嬉しくない?(^皿^)
マット・デイモンは主人公スコッティーから彼女を奪って「スッコティーは知らねえ 毎週末俺が彼女と車で(以下略) 教会に行くと言って(以下略) 奴の誕生日に(以下略)」と歌うのです。その歌をスコッティーが聴いてしまったので歌詞を「Skotty does know」に変えるべきなのですが、変えたら余計悲惨さがアップするのでやめておきましょう。マット・デイモンがやたら楽しそうなのが何よりです。今ではもう周りが止めてしまうので、こんなB級お馬鹿映画には出られないでしょう。一生の記念ですね♪(^皿^)b
何たってこの『ユーロ・トリップ』は青春お馬鹿映画の傑作です。
健全な青少年としてのエロネタ、ゲイネタ、フーリガンネタのみならず、ドイツの口髭が生えてて右腕上げてるあの人のネタや、教皇が亡くなったことを知らせる鐘を鳴らしちゃったりと不謹慎の極みなのに、うまいこと爽やかに仕上がっている傑作なのです。
<あらすじ>
主人公たちは高校を卒業したばかりの若者4人。4人のうち3人がノーマルな男性。1人はノーマルな女性。
彼らはメル友に会うためアメリカからベルリンを目指して旅立ちました。
しかしなかなかベルリンまで辿り着きません!
<彼らの寄り道の数々を、大人の事情で端折りつつ御紹介しましょう>
1. 経由のため、まずロンドンに着く。うっかりフーリガン専用バーに入る。命惜しさにフーリガンと仲良くなってしまい、試合が行われるパリまで拉致される。
2. せっかくパリに来たからルーヴル美術館へ。美術館前でロボットダンス(?)をしている大道芸人と出会う。主人公もふざけて対抗。ロボットダンスで通行人からお金をゲット! 「ここは俺のシマだ」と大道芸人が怒ったのでロボットファイトをする。勝つ。
3. 列車の中でロボット大道芸人と再会! ロボット大道芸人はゲイだった。主人公のうち男性は触 ら れ る。
4. ヨーロッパ1のヌーディストビーチへ♪ わくわくしながら行ってみた。けれど女性なんていやしない。いるのは女性目的にやってきた全裸の男性たちのみ。主人公たちのうち1人は女性がおり、この女性が水着姿で現れたのでビーチにいた男性たちが寄って来た。・・・想像してください、ゾンビが食欲じゃない欲に特化してしまったバイオハザードを! 主人公たちは無事逃げ切りました。
5. 高校を卒業したんだもん、オトナのお店へGo♪ ヨーロッパ美女に囲まれて幸せ〜と思いきや。うっかり女王様と下僕のお店に入ってしまった! ・・・翌朝、痛い思いをしながら旅行する羽目に。
6. ヒッチハイクに失敗。スロバキア共和国へ。アブサンを飲んでぶっ飛んで、近親(キスしかしてないけど以下略)をやらかしてしまう。
7. やっとメル友の家へ辿り着いた! だがメル友は旅に出てしまっていた。主人公たちはメル友を追いかけてバチカンへ。
8. 教皇が死んだことを知らせる鐘を鳴らした。新しい教皇が決まったことを知らせる白い煙をあげた。主人公はここでメル友を発見! 慌てる主人公は司教帽(?)を被り、杖(?)を持ち、金色のカーテンが体に巻いた状態で群衆の前に出てしまった。群衆は「新しい教皇だ!」と勘違い。歓声があがる。世界規模でTV中継をされる。とりあえず手を振って歓声に応えてみる。(‘ ▽‘)ノ
9.... 結末は御自分でどうぞ♪
しかしくれぐれも実年齢18歳以上、精神年齢20歳以上じゃないと見ちゃダメですよー。これに該当する方も、家族や恋人と一緒に見ないようにお気をつけください♪
黒澤明監督 『八月の狂詩曲(ラプソディー)』
2008年6月28日 映画
舞台は昭和が平成へと変わった頃。
季節は原爆が落ちたのと同じ、夏。
孫たちは夏休みをばあちゃんの家で過ごしました。じいちゃんは原爆を長崎に落とされて死亡。ばあちゃんはじいちゃんを探しに長崎へ行った際被爆しています。
孫たちは原爆のことを知ってアメリカ人を嫌いになりかけました。
ばあちゃんは孫たちに言いました。「みんな戦争のせいたい。戦争が悪かとやけん。戦争で日本人もたくさん死んだけどアメリカ人もたくさん死んだ」と。
実際に戦争を経験したばあちゃんがそう言ったので、孫たちは少し冷静になれました。
孫たちはアメリカ人の機嫌を窺う日本人に対しても嫌悪を露わにします。孫たちよりばあちゃんの方が余程この嫌悪を強く感じていたことでしょう。この映画では、ばあちゃんがアメリカに帰化した兄のことを思い出せない、ということでこの嫌悪が描かれています。ばあちゃんは10人以上いた兄弟の名前を黒板に書いていき、その兄以外の全ての兄弟の名前を書くことができたのに、なぜかその兄の名前にはピンとこなかったのです。その兄の上と下の兄弟のことは思い出せる上、真ん中に誰かいたということも覚えているのに。
この理由については直接的に描かれませんでしたが・・・わたしは以下のように考えます。ばあちゃんは当時兄を「裏切り者」と強く思った。戦時中は鬼畜米英と叫びながら戦後はアメリカかぶれしていく者たちと同じだと思った(別の映画ですがわたしは『火垂るの墓』の最後あたりでこれを強く感じました。レコードを聴き洋服を着る日本人に対して「嫌だなあ」と思いました)。兄を初めからいなかったと思いこもうとした。普通の物忘れとは違い「思い出したい」と思わないから、全く思い出せない。・・・と。
こういう戦争の傷もあるんですね・・・。
頭では「戦争が悪いのであって人が悪いのではない」と思っていても・・・。
季節は原爆が落ちたのと同じ、夏。
孫たちは夏休みをばあちゃんの家で過ごしました。じいちゃんは原爆を長崎に落とされて死亡。ばあちゃんはじいちゃんを探しに長崎へ行った際被爆しています。
孫たちは原爆のことを知ってアメリカ人を嫌いになりかけました。
ばあちゃんは孫たちに言いました。「みんな戦争のせいたい。戦争が悪かとやけん。戦争で日本人もたくさん死んだけどアメリカ人もたくさん死んだ」と。
実際に戦争を経験したばあちゃんがそう言ったので、孫たちは少し冷静になれました。
孫たちはアメリカ人の機嫌を窺う日本人に対しても嫌悪を露わにします。孫たちよりばあちゃんの方が余程この嫌悪を強く感じていたことでしょう。この映画では、ばあちゃんがアメリカに帰化した兄のことを思い出せない、ということでこの嫌悪が描かれています。ばあちゃんは10人以上いた兄弟の名前を黒板に書いていき、その兄以外の全ての兄弟の名前を書くことができたのに、なぜかその兄の名前にはピンとこなかったのです。その兄の上と下の兄弟のことは思い出せる上、真ん中に誰かいたということも覚えているのに。
この理由については直接的に描かれませんでしたが・・・わたしは以下のように考えます。ばあちゃんは当時兄を「裏切り者」と強く思った。戦時中は鬼畜米英と叫びながら戦後はアメリカかぶれしていく者たちと同じだと思った(別の映画ですがわたしは『火垂るの墓』の最後あたりでこれを強く感じました。レコードを聴き洋服を着る日本人に対して「嫌だなあ」と思いました)。兄を初めからいなかったと思いこもうとした。普通の物忘れとは違い「思い出したい」と思わないから、全く思い出せない。・・・と。
こういう戦争の傷もあるんですね・・・。
頭では「戦争が悪いのであって人が悪いのではない」と思っていても・・・。
芝山努監督 『映画 ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』
2008年6月18日 映画
この映画に登場する「種まく人」はわたしが理想とする神の姿にかなり近いです。
「種まく人」は生きものを懲らしめることも、救うこともありません。
「種まく人」はただ、生きものが生きられる環境を創るだけ。
「種まく人」は環境が出来上がるまでの間は、その土地を守ります。
「種まく人」は環境が出来上がった後は、そこに留まることなく去り、また新たな土地に命を生み出していきます。
「種まく人」が去ったということは、そこに生きる生きものに全てが委ねられたということ。戦争をしようが、環境破壊をしようが、絶滅しようとも・・・全てが委ねられているのです。
けれど「種まく人」は生きものを身捨てているわけではありません。見守っています。この生きものには生きる資格がない、とかこの世界はもう駄目だ、などと悲観せず、その世界がどうなるか見守っているのです。手を出したりしません。
それがわたしの理想にかなり近いのです。
わたしは大人になった今でも時々「どうして神様は助けてくれないの?」と不満を感じることがあります。
けれど、自分にとっての救いは誰かにとっての苦しみになるかも知れません。それを考えると、「神様がいたかどうかもわからない」世界に生まれてきて良かったと思えるのです。
何が起こったとしても神様のせいにせず、自分で解決策を考えられるから。
多分、神様がいちいち助けてくれていたら、いつまで経っても成長できません。
神様がいたかどうかもわからない世界にいることによって、神様に自分で考えるチャンスを与えてもらっている気がします。
ただ、わたしはこの考えを他人に押し付けるつもりはありません。
犯罪に巻き込まれたり、病気になったり、被災した人などは神様に救いを求めて当たり前。
人それぞれ理想の神の姿は違って当たり前。
わたしは他の人がどんな神を理想とするのか知りたいので、今後は宗教の勉強もしようかなと思います。(人間に罰を与えたり御褒美をくれる「神様」は信用できませんけどね・・・)
「種まく人」は生きものを懲らしめることも、救うこともありません。
「種まく人」はただ、生きものが生きられる環境を創るだけ。
「種まく人」は環境が出来上がるまでの間は、その土地を守ります。
「種まく人」は環境が出来上がった後は、そこに留まることなく去り、また新たな土地に命を生み出していきます。
「種まく人」が去ったということは、そこに生きる生きものに全てが委ねられたということ。戦争をしようが、環境破壊をしようが、絶滅しようとも・・・全てが委ねられているのです。
けれど「種まく人」は生きものを身捨てているわけではありません。見守っています。この生きものには生きる資格がない、とかこの世界はもう駄目だ、などと悲観せず、その世界がどうなるか見守っているのです。手を出したりしません。
それがわたしの理想にかなり近いのです。
わたしは大人になった今でも時々「どうして神様は助けてくれないの?」と不満を感じることがあります。
けれど、自分にとっての救いは誰かにとっての苦しみになるかも知れません。それを考えると、「神様がいたかどうかもわからない」世界に生まれてきて良かったと思えるのです。
何が起こったとしても神様のせいにせず、自分で解決策を考えられるから。
多分、神様がいちいち助けてくれていたら、いつまで経っても成長できません。
神様がいたかどうかもわからない世界にいることによって、神様に自分で考えるチャンスを与えてもらっている気がします。
ただ、わたしはこの考えを他人に押し付けるつもりはありません。
犯罪に巻き込まれたり、病気になったり、被災した人などは神様に救いを求めて当たり前。
人それぞれ理想の神の姿は違って当たり前。
わたしは他の人がどんな神を理想とするのか知りたいので、今後は宗教の勉強もしようかなと思います。(人間に罰を与えたり御褒美をくれる「神様」は信用できませんけどね・・・)
アンドリュー・カリー監督 『ゾンビーノ』
2008年6月9日 映画
ゾンビに萌えることができる映画。
60年代の香り漂うブラックコメディ。
以下はネタバレを含むあらすじです。
この映画の世界では、首を切断されない限り、人間はゾンビになってしまいます。ゾンビは人間の肉を食べようとします。そこで人間は、ゾンビの食欲を抑える特別な首輪を開発。首輪をつけられたゾンビは大人しくなる上、ある程度は知能を有しているため、人間はゾンビを召使いとして使役するようになりました。ゾンビは何も食べないし眠らないし、何より賃金を要求しません。労働基準法の適用なんてありません。
しかし首輪は時々故障を起こしてしまいます。そのため人間は子どもの頃から、首輪が壊れたゾンビを殺せるよう射撃の授業を受けます。子どもたちは「脳ミソを吹っ飛ばせ♪」と歌いながら、的の頭を集中的に撃ちまくります。
新聞配達員もゾンビ。牛乳配達員もゾンビ。葬式スタッフもゾンビ。学校の用務員もゾンビ。公園の管理人も・・・やっぱりゾンビ。一般家庭にも、一家に1人はゾンビ。子どもたちはゾンビに縄をつけて、遊び相手として連れ歩きます。
ティミーという小学生男子の家にも男性ゾンビが1人います。ティミーはいじめられっ子。男性ゾンビがいじめっ子からティミーを守ってくれたので、ティミーと男性ゾンビは仲良しになり、ティミーは男性ゾンビに「ファイド」という名前をつけました。ファイドって犬につける名前らしいのですが・・・仲良きことは美しきかな。ファイドは雷を怖がったり、ジュースを飲む真似をしたりと感情が豊かなゾンビです。
しかし近所に住むおばあさんがファイドの首輪を壊してしまったので、ファイドはおばあさんを食べちゃいました! 人を食べたゾンビは殺されてしまいます・・・。
・・・ティミーは冷静な判断をしました。まず、おばあさんの死体を放置。ファイドについた返り血を手早く洗い流し、夜になってからスコップを持って現場に戻りました。けれど戻ってみると、おばあさんはゾンビになっていました。そこでティミーはスコップで、ゾンビ化したおばあさんの頭部を殴りまくり、首を切断することに成功。ティミーは「花が好きだったよね」と言いつつ、ゾンビ化したおばあさんの体を公園の花壇に埋めました。・・・何ちゅう小学生?
おばあさんが壊したファイドの指輪は、近所に住む変人のシアポリスさんが修理してくれました。本当は、一般人が勝手に首輪を修理するのはいけないことなのですが。シアポリスさんは、若くして亡くなった美人ゾンビ・タミーと2人暮らし。シアポリスさんは色々と変人要素を兼ね備えているのですが、何よりタミーの首輪の機能を解除した状態でタミーとムニャムニャ・・・(以下略)するのが趣味。タミーに食べられかけて首についたという歯形がご自慢の模様。
返り血は洗い流したし、ゾンビ化したおばあさんは埋めたし、首輪も直って万々歳。
・・・と思いきや。ティミーはミスをしました。実は、ゾンビ化したおばあさんはティミーと出会う前に人を襲っていたのです。襲われた人は死亡してゾンビになりました。そして人の肉を食べ、食べられた人もまたゾンビに! 本来は地獄絵図のはずですが、なんだか面白い光景で、笑いを誘います。ネズミ算式に被害者が増え、ついに警察は、ファイドがおばあさんを食べたことが事の発端であると突き止めました。
ファイドは連れて行かれてしまいました・・・。けれどファイドはゾンビの中でも優秀なゾンビだったので殺されず、工場で働かされているとのこと。
ティミーはシアポリスさんとタミーと共に、ファイド救出に向かいました。しかしシアポリスさんは無茶をしました。故意にゾンビに人を襲わせて大混乱が起こった隙に救出、という無茶な作戦を実行したのです。多くの犠牲者が出ました。犠牲者の中には、ティミーのパパや、ティミーのガールフレンドのパパも含まれていました・・・。亡くなってしまったのです。が、ティミーはファイドが父親代わりになって喜んでいるようですし、ティミーのガールフレンドも元は父親だったゾンビに首輪をつけて「今の方が優しいしイケてるわ」と喜んでいる模様。
めでたしめでたし♪
・・・すごい映画だ。
60年代の香り漂うブラックコメディ。
以下はネタバレを含むあらすじです。
この映画の世界では、首を切断されない限り、人間はゾンビになってしまいます。ゾンビは人間の肉を食べようとします。そこで人間は、ゾンビの食欲を抑える特別な首輪を開発。首輪をつけられたゾンビは大人しくなる上、ある程度は知能を有しているため、人間はゾンビを召使いとして使役するようになりました。ゾンビは何も食べないし眠らないし、何より賃金を要求しません。労働基準法の適用なんてありません。
しかし首輪は時々故障を起こしてしまいます。そのため人間は子どもの頃から、首輪が壊れたゾンビを殺せるよう射撃の授業を受けます。子どもたちは「脳ミソを吹っ飛ばせ♪」と歌いながら、的の頭を集中的に撃ちまくります。
新聞配達員もゾンビ。牛乳配達員もゾンビ。葬式スタッフもゾンビ。学校の用務員もゾンビ。公園の管理人も・・・やっぱりゾンビ。一般家庭にも、一家に1人はゾンビ。子どもたちはゾンビに縄をつけて、遊び相手として連れ歩きます。
ティミーという小学生男子の家にも男性ゾンビが1人います。ティミーはいじめられっ子。男性ゾンビがいじめっ子からティミーを守ってくれたので、ティミーと男性ゾンビは仲良しになり、ティミーは男性ゾンビに「ファイド」という名前をつけました。ファイドって犬につける名前らしいのですが・・・仲良きことは美しきかな。ファイドは雷を怖がったり、ジュースを飲む真似をしたりと感情が豊かなゾンビです。
しかし近所に住むおばあさんがファイドの首輪を壊してしまったので、ファイドはおばあさんを食べちゃいました! 人を食べたゾンビは殺されてしまいます・・・。
・・・ティミーは冷静な判断をしました。まず、おばあさんの死体を放置。ファイドについた返り血を手早く洗い流し、夜になってからスコップを持って現場に戻りました。けれど戻ってみると、おばあさんはゾンビになっていました。そこでティミーはスコップで、ゾンビ化したおばあさんの頭部を殴りまくり、首を切断することに成功。ティミーは「花が好きだったよね」と言いつつ、ゾンビ化したおばあさんの体を公園の花壇に埋めました。・・・何ちゅう小学生?
おばあさんが壊したファイドの指輪は、近所に住む変人のシアポリスさんが修理してくれました。本当は、一般人が勝手に首輪を修理するのはいけないことなのですが。シアポリスさんは、若くして亡くなった美人ゾンビ・タミーと2人暮らし。シアポリスさんは色々と変人要素を兼ね備えているのですが、何よりタミーの首輪の機能を解除した状態でタミーとムニャムニャ・・・(以下略)するのが趣味。タミーに食べられかけて首についたという歯形がご自慢の模様。
返り血は洗い流したし、ゾンビ化したおばあさんは埋めたし、首輪も直って万々歳。
・・・と思いきや。ティミーはミスをしました。実は、ゾンビ化したおばあさんはティミーと出会う前に人を襲っていたのです。襲われた人は死亡してゾンビになりました。そして人の肉を食べ、食べられた人もまたゾンビに! 本来は地獄絵図のはずですが、なんだか面白い光景で、笑いを誘います。ネズミ算式に被害者が増え、ついに警察は、ファイドがおばあさんを食べたことが事の発端であると突き止めました。
ファイドは連れて行かれてしまいました・・・。けれどファイドはゾンビの中でも優秀なゾンビだったので殺されず、工場で働かされているとのこと。
ティミーはシアポリスさんとタミーと共に、ファイド救出に向かいました。しかしシアポリスさんは無茶をしました。故意にゾンビに人を襲わせて大混乱が起こった隙に救出、という無茶な作戦を実行したのです。多くの犠牲者が出ました。犠牲者の中には、ティミーのパパや、ティミーのガールフレンドのパパも含まれていました・・・。亡くなってしまったのです。が、ティミーはファイドが父親代わりになって喜んでいるようですし、ティミーのガールフレンドも元は父親だったゾンビに首輪をつけて「今の方が優しいしイケてるわ」と喜んでいる模様。
めでたしめでたし♪
・・・すごい映画だ。
アレハンドロ・アメナーバル監督 『海を飛ぶ夢』
2008年6月5日 映画
ラモン・サンペドロは実在した人物。
首を折ったことが原因で頭から下の感覚を失い、動かすことも出来なくなった男性。
彼は事故から約30年間ずっとベッドの上で生きてきました。
今、ラモンは実在「した」人物。
彼は死を望み、友人が手を貸したのです。
この映画は尊厳死を肯定もしなければ否定もしません。
この映画は観客がラモンを応援したくなるように、しかし時には尊厳死に反対する側を応援したくなるように作ってあります。
誰も悪くないから。
ラモンは愛されていなかったわけではありません。愛していなかったわけでもありません。だからこそ彼は約30年間待ったのです。「何故僕は死にたいんだ」と苦しみ続けたのです。
けれど、今の体では愛する人に触れられません。愛する人が触れてくれたとしても、今の体は感じることが出来ません。だから彼は魂を体から自由にして、魂となって愛する人を感じたかった。大好きな海に、車椅子などに縛られず、自由に行きたかった。
それが彼にとっての「生きる」ということ。
だから彼の友人は彼が生きられるように、尊厳死を合法化するため裁判に協力しました。けれど努力は報われず、裁判所は彼が尊厳死することを許してはくれませんでした。最終手段として友人は、コップの水に青酸カリを混ぜ、ストローをさし、ラモンの傍に置くという方法によって彼が死ぬのを手助けしました。
彼と友人の行動を責められる人はいるのでしょうか。
責める人はいたでしょう。特に宗教関係者が。この映画にも神父が登場します。神父もラモンと同じく四肢麻痺なのですが、神父は尊厳死に反対する立場。神父は自分の考えをラモンやラモンの家族に押し付けようとします。そのせいでラモンの家族は心に一生忘れられない傷を負いました。
・・・この神父が正しいのか正しくないのかはわたしにもわかりませんが、一つハッキリしていることがあります、わたしはこの神父が嫌いです。けれどこの映画には、神父の登場シーンも含めたどのシーンも飛ばさずに何度もリピートさせる力があります。それは多分神父に悪意があるのではなく心底「尊厳死はいけない」と思って言っているからであり、ラモンの家族も友人も彼を応援しつつも(ただしラモンの兄は応援しない立場)気持ちが揺らいでいるからであり、ラモンの魂が海の上を飛んでいくシーンが美しいからではないかと思います。
首を折ったことが原因で頭から下の感覚を失い、動かすことも出来なくなった男性。
彼は事故から約30年間ずっとベッドの上で生きてきました。
今、ラモンは実在「した」人物。
彼は死を望み、友人が手を貸したのです。
この映画は尊厳死を肯定もしなければ否定もしません。
この映画は観客がラモンを応援したくなるように、しかし時には尊厳死に反対する側を応援したくなるように作ってあります。
誰も悪くないから。
ラモンは愛されていなかったわけではありません。愛していなかったわけでもありません。だからこそ彼は約30年間待ったのです。「何故僕は死にたいんだ」と苦しみ続けたのです。
けれど、今の体では愛する人に触れられません。愛する人が触れてくれたとしても、今の体は感じることが出来ません。だから彼は魂を体から自由にして、魂となって愛する人を感じたかった。大好きな海に、車椅子などに縛られず、自由に行きたかった。
それが彼にとっての「生きる」ということ。
だから彼の友人は彼が生きられるように、尊厳死を合法化するため裁判に協力しました。けれど努力は報われず、裁判所は彼が尊厳死することを許してはくれませんでした。最終手段として友人は、コップの水に青酸カリを混ぜ、ストローをさし、ラモンの傍に置くという方法によって彼が死ぬのを手助けしました。
彼と友人の行動を責められる人はいるのでしょうか。
責める人はいたでしょう。特に宗教関係者が。この映画にも神父が登場します。神父もラモンと同じく四肢麻痺なのですが、神父は尊厳死に反対する立場。神父は自分の考えをラモンやラモンの家族に押し付けようとします。そのせいでラモンの家族は心に一生忘れられない傷を負いました。
・・・この神父が正しいのか正しくないのかはわたしにもわかりませんが、一つハッキリしていることがあります、わたしはこの神父が嫌いです。けれどこの映画には、神父の登場シーンも含めたどのシーンも飛ばさずに何度もリピートさせる力があります。それは多分神父に悪意があるのではなく心底「尊厳死はいけない」と思って言っているからであり、ラモンの家族も友人も彼を応援しつつも(ただしラモンの兄は応援しない立場)気持ちが揺らいでいるからであり、ラモンの魂が海の上を飛んでいくシーンが美しいからではないかと思います。
出演・・・ルグリ 他 『エトワール デラックス版』
2008年6月4日 映画
「バレエを“生きている”の。愛しているでは弱すぎる」
第一舞踊手マリ=アニエス=ジロが言ったこの言葉が『エトワール』を象徴しています。
『エトワール』はパリ・オペラ座のダンサーたちを撮ったドキュメンタリー映画です。通し稽古、舞台裏、レッスン風景、ダンサーや振付家へのインタビューなどを見ることが出来ます。
ベジャールは言いました、「芸術に解説は不要」と。だからわたしも『エトワール』の解説はしません。バレエに限らず踊りが好きな方は是非見てください。
第一舞踊手マリ=アニエス=ジロが言ったこの言葉が『エトワール』を象徴しています。
『エトワール』はパリ・オペラ座のダンサーたちを撮ったドキュメンタリー映画です。通し稽古、舞台裏、レッスン風景、ダンサーや振付家へのインタビューなどを見ることが出来ます。
ベジャールは言いました、「芸術に解説は不要」と。だからわたしも『エトワール』の解説はしません。バレエに限らず踊りが好きな方は是非見てください。
李相日監督 『フラガール』
2008年6月2日 映画
南海キャンディーズのしずちゃん扮する熊野小百合の父が亡くなったシーンで。
「ああ、あのお父さん死んじゃったんだ・・・!」とわたしの目から涙が溢れました。
普段は、登場人物の父が亡くなった、ぐらいでは決して泣きません。
けれど小百合の父の場合は違いました。
小百合の父は町の炭鉱夫。この町では、炭鉱を閉鎖してハワイアンセンターを作ろうという計画が、炭鉱夫たちとその家族の気持ちを置き去りにして進行しています。町の会社は、オイル主流の時代になる前に炭鉱を閉鎖したい。炭鉱夫たちとその家族たちは、100年も続いた炭鉱を閉鎖して欲しくない。男は炭鉱でお国のために命をかけて働くのが当たり前、女はそれを支えるのが当たり前・・・、みんなその考えのもと生きてきたからです。みんな炭鉱以外の場所で働くという選択肢を無くそうとします。そのためこの町ではハワイ事業に協力すると「裏切り者」と言われます。それでも小百合の父は「会社のお役に立ててもらえればと思って」娘を連れて来るのです。
熊野小百合は初登場シーンで、父に連れられてフラダンスの練習場にやって来ます。小百合はでっかいです。父の身長を頭1つ超えて、でっかいです。体格も立派です。練習場に居た数名の人間は、小百合の姿に唖然とします。けれど小百合は内気な様子で、挨拶も出来ません。視線はさまようばかり。小百合は何故か練習場にお盆を持って来ています。緊張している時って何かを触ったり握ったりしたくなりますよね。小百合にとって握れる身近なものはお盆だったのでしょう。更に小百合の着物からいって家事手伝いをしていることが考えられます。この町の女性は選炭場で働く人も多いし、もしかしたら町の旅館で仲居をやっているのかもしれませんが、どうもこの様子だと家の外で働いているようには見えません。家の外で働くには、挨拶をする、笑顔を作る、などの対人スキルが必要です。けれど小百合は、練習場にいる数名の人間に一言も声をかけることが出来ない。お盆をギューッと握りしめていることからいっても、人見知りであることは間違いありません。父はそんな小百合のことを「男手ひとつで育てたもんで、見てくれはちっと男みたいだげんど。小っちぇえ頃から踊りが好きで好きで・・・な」と紹介します。それでようやく小百合は笑顔を浮かべます。父はどうすれば小百合が笑うか知っているのです。
この短い紹介の中に色んなフォローが含まれています。多分、小百合の父はこう言いたいのではないでしょうか。小百合がこう育ったのは小百合のせいではありません。男みたいなのではなく、少し男みたいに見えるだけ。見てくれがこうなだけであって、心の中は小百合という名にぴったりの娘です。小百合は嫌々練習場に来たのではなく、踊りが好きだから来たのですよ。けれど初々しい性格なので一人で来れず、そのため自分が付き添って来たのですよ。・・・と。小百合が笑ったのは、父の言いたいことを理解したからではないでしょうか。
小百合の父は、「娘がいつもお世話になって・・・」と練習場に挨拶に来ることもありました。上手く踊れずに外を走らされる娘と一緒に走ることもありました。「小百合頑張れ!」と言いながら。
練習を積み重ねた結果、小百合はフラダンスを踊れるようになりました。けれどダンサーとして舞台に上がり始めた頃の小百合は、舞台で笑顔を浮かべられないし、楽屋では壁に向かって何かブツブツ話すし、舞台そでまで出ておきながら逃げようとするし、終いには舞台中央で座りこんだ後舞台から走って逃げる始末。
そんな状態だったのが変わります。小百合は舞台で笑いながら踊れるようになったのです。いつの頃からか、小百合は舞台に上げる前に手鏡を見て微笑むようになりました。自分で買った手鏡かもしれないし、母の形見の手鏡かもしれません。けれどわたしには、小百合の父が「笑顔で踊れるように」と買ってくれた手鏡であるように思えました。
舞台に上がる前に、小百合は父の身に起こったことを知らされます。炭鉱で落盤事故が起き、父がその犠牲になったというニュースが飛び込んできたのです。小百合は手鏡を離さず、手鏡を見ながら無理やり笑顔を作ろうとします。父が死んだかどうかはわからない。もしかしたら今から急いで駆け付ければ、小百合は父の死に目にあえるかもしれない。他のダンサーたちは舞台を中止して帰ろうとしました。けれどただ一人、当の小百合が言いました。「躍ります」と。「父ちゃんもきっとそう言ってくれっと思うから・・・」と。
舞台は予定通り終了。小百合を含むダンサーたちは町に帰ってから、小百合の父が最期まで小百合の名を呼びながら息を引き取ったと知りました。小百合は町の人に「親不幸者!」と詰られ、泣きながら、父の亡骸に会うため歩きだします。
わたしには、小百合がどちらを選択したとしても親不幸になったし親孝行になったような気がします。
多分親になった人間は、死ぬ時に子どもや孫に会いたいものではないでしょうか。普段子どもに立派になって欲しいと思ってはいても、死ぬ時は会いたい。だから小百合が舞台を取りやめにしてでも父に会いに駆け付ければ、父は喜んだはず。けれどこれまでの父の行動を考えると、父は心のどこかでガッカリしたかもしれません。勿論喜びの方が勝るでしょうが・・・。
でも、これって凄いことだと思いませんか。
どちらを選択したとしても親不幸になるし親孝行になる、という親子関係を築けるなんて。
「ああ、あのお父さん死んじゃったんだ・・・!」とわたしの目から涙が溢れました。
普段は、登場人物の父が亡くなった、ぐらいでは決して泣きません。
けれど小百合の父の場合は違いました。
小百合の父は町の炭鉱夫。この町では、炭鉱を閉鎖してハワイアンセンターを作ろうという計画が、炭鉱夫たちとその家族の気持ちを置き去りにして進行しています。町の会社は、オイル主流の時代になる前に炭鉱を閉鎖したい。炭鉱夫たちとその家族たちは、100年も続いた炭鉱を閉鎖して欲しくない。男は炭鉱でお国のために命をかけて働くのが当たり前、女はそれを支えるのが当たり前・・・、みんなその考えのもと生きてきたからです。みんな炭鉱以外の場所で働くという選択肢を無くそうとします。そのためこの町ではハワイ事業に協力すると「裏切り者」と言われます。それでも小百合の父は「会社のお役に立ててもらえればと思って」娘を連れて来るのです。
熊野小百合は初登場シーンで、父に連れられてフラダンスの練習場にやって来ます。小百合はでっかいです。父の身長を頭1つ超えて、でっかいです。体格も立派です。練習場に居た数名の人間は、小百合の姿に唖然とします。けれど小百合は内気な様子で、挨拶も出来ません。視線はさまようばかり。小百合は何故か練習場にお盆を持って来ています。緊張している時って何かを触ったり握ったりしたくなりますよね。小百合にとって握れる身近なものはお盆だったのでしょう。更に小百合の着物からいって家事手伝いをしていることが考えられます。この町の女性は選炭場で働く人も多いし、もしかしたら町の旅館で仲居をやっているのかもしれませんが、どうもこの様子だと家の外で働いているようには見えません。家の外で働くには、挨拶をする、笑顔を作る、などの対人スキルが必要です。けれど小百合は、練習場にいる数名の人間に一言も声をかけることが出来ない。お盆をギューッと握りしめていることからいっても、人見知りであることは間違いありません。父はそんな小百合のことを「男手ひとつで育てたもんで、見てくれはちっと男みたいだげんど。小っちぇえ頃から踊りが好きで好きで・・・な」と紹介します。それでようやく小百合は笑顔を浮かべます。父はどうすれば小百合が笑うか知っているのです。
この短い紹介の中に色んなフォローが含まれています。多分、小百合の父はこう言いたいのではないでしょうか。小百合がこう育ったのは小百合のせいではありません。男みたいなのではなく、少し男みたいに見えるだけ。見てくれがこうなだけであって、心の中は小百合という名にぴったりの娘です。小百合は嫌々練習場に来たのではなく、踊りが好きだから来たのですよ。けれど初々しい性格なので一人で来れず、そのため自分が付き添って来たのですよ。・・・と。小百合が笑ったのは、父の言いたいことを理解したからではないでしょうか。
小百合の父は、「娘がいつもお世話になって・・・」と練習場に挨拶に来ることもありました。上手く踊れずに外を走らされる娘と一緒に走ることもありました。「小百合頑張れ!」と言いながら。
練習を積み重ねた結果、小百合はフラダンスを踊れるようになりました。けれどダンサーとして舞台に上がり始めた頃の小百合は、舞台で笑顔を浮かべられないし、楽屋では壁に向かって何かブツブツ話すし、舞台そでまで出ておきながら逃げようとするし、終いには舞台中央で座りこんだ後舞台から走って逃げる始末。
そんな状態だったのが変わります。小百合は舞台で笑いながら踊れるようになったのです。いつの頃からか、小百合は舞台に上げる前に手鏡を見て微笑むようになりました。自分で買った手鏡かもしれないし、母の形見の手鏡かもしれません。けれどわたしには、小百合の父が「笑顔で踊れるように」と買ってくれた手鏡であるように思えました。
舞台に上がる前に、小百合は父の身に起こったことを知らされます。炭鉱で落盤事故が起き、父がその犠牲になったというニュースが飛び込んできたのです。小百合は手鏡を離さず、手鏡を見ながら無理やり笑顔を作ろうとします。父が死んだかどうかはわからない。もしかしたら今から急いで駆け付ければ、小百合は父の死に目にあえるかもしれない。他のダンサーたちは舞台を中止して帰ろうとしました。けれどただ一人、当の小百合が言いました。「躍ります」と。「父ちゃんもきっとそう言ってくれっと思うから・・・」と。
舞台は予定通り終了。小百合を含むダンサーたちは町に帰ってから、小百合の父が最期まで小百合の名を呼びながら息を引き取ったと知りました。小百合は町の人に「親不幸者!」と詰られ、泣きながら、父の亡骸に会うため歩きだします。
わたしには、小百合がどちらを選択したとしても親不幸になったし親孝行になったような気がします。
多分親になった人間は、死ぬ時に子どもや孫に会いたいものではないでしょうか。普段子どもに立派になって欲しいと思ってはいても、死ぬ時は会いたい。だから小百合が舞台を取りやめにしてでも父に会いに駆け付ければ、父は喜んだはず。けれどこれまでの父の行動を考えると、父は心のどこかでガッカリしたかもしれません。勿論喜びの方が勝るでしょうが・・・。
でも、これって凄いことだと思いませんか。
どちらを選択したとしても親不幸になるし親孝行になる、という親子関係を築けるなんて。
キム・ヨンファ監督 『カンナさん大成功です!』
2008年5月30日 映画
タイトルは原作を意識して「カンナさん」だけれど、劇中のヒロイン名は「ハンナさん」。
ハンナさんの気持ちの移り変わり・・・というより「気持ちが増えていく」感じが伝わる映画です。
ハンナさんは巨体で野暮ったく、けれど優しい心と可憐な声を持っている女性でした。ある日ハンナさんは、好きな人がハンナさんの容姿を馬鹿にしているということを知りました。ハンナさんは自殺をしようと思いましたが・・・思いとどまり、代わりに全身整形に踏み切りました。大がかりな手術のため、死ぬ危険性もありましたがハンナさんは無事生還。巨体で野暮ったかったハンナさんは、全身整形と運動のおかげで、透明感のあるスレンダー美人に!
ここで「彼に復讐してやろう」とか「彼よりもっといい男と付き合ってやろう」と思わないのがハンナさん。
ハンナさんは、ジェニーと名乗って(たぶんハンナさんがジェニー人形を好きだから)彼に近づきました。そしてジェニーとして彼と仕事をするようになるのです。仕事をする中で、彼がハンナさんを彼なりに大切に思っていたことが判明します。彼が容姿の美しさのみで人を称賛しないこともわかりました。ハンナさんは自分がハンナであることを彼に告白しようと思いました。が、告白はできませんでした。理由は色々ありますが、一番大きな理由は、整形手術をした女性とは恋人になりたくないと彼が言ったからです。そのためハンナさんはジェニーとして彼と会い続けることになります。
ハンナさんはやっぱり彼のことが好きなのです。
けれどその感情は、ハンナさんがハンナさんでしかなかった頃彼に抱いた気持ちと同じものではない・・・とわたしは思います。
初めの頃、ハンナさんにとって彼は絶対的な存在でした。人に馬鹿にされる人生を送ってきたハンナさんに対して、彼は傷つけるようなことをしなかったのです。それが一度壊れて、ハンナさんは彼と決別しようとしました。でもハンナさんは偶然、彼を街で見かけてしまいました。ハンナさんは彼から目を離すことが出来ませんでした。それでハンナさんは、たとえ馬鹿にされようとも彼を好きだという自分が居ることを自覚します。それでジェニーとして近づいて、ハンナさんでしかなかった頃は知らなかった彼の一面にまた魅かれて・・・。
この映画を見ていて、ハンナさんのドキドキが伝わってきました。戸惑いも。自己嫌悪も。
ラストシーンではハンナさんの彼に対する新たな気持ちがまた増えている感じがします。彼の機嫌を取ることが無くなっている。彼となら対等になれるという気持ちが増えたのかもしれません。
また何度でも見たい映画です。
ハンナさんの気持ちの移り変わり・・・というより「気持ちが増えていく」感じが伝わる映画です。
ハンナさんは巨体で野暮ったく、けれど優しい心と可憐な声を持っている女性でした。ある日ハンナさんは、好きな人がハンナさんの容姿を馬鹿にしているということを知りました。ハンナさんは自殺をしようと思いましたが・・・思いとどまり、代わりに全身整形に踏み切りました。大がかりな手術のため、死ぬ危険性もありましたがハンナさんは無事生還。巨体で野暮ったかったハンナさんは、全身整形と運動のおかげで、透明感のあるスレンダー美人に!
ここで「彼に復讐してやろう」とか「彼よりもっといい男と付き合ってやろう」と思わないのがハンナさん。
ハンナさんは、ジェニーと名乗って(たぶんハンナさんがジェニー人形を好きだから)彼に近づきました。そしてジェニーとして彼と仕事をするようになるのです。仕事をする中で、彼がハンナさんを彼なりに大切に思っていたことが判明します。彼が容姿の美しさのみで人を称賛しないこともわかりました。ハンナさんは自分がハンナであることを彼に告白しようと思いました。が、告白はできませんでした。理由は色々ありますが、一番大きな理由は、整形手術をした女性とは恋人になりたくないと彼が言ったからです。そのためハンナさんはジェニーとして彼と会い続けることになります。
ハンナさんはやっぱり彼のことが好きなのです。
けれどその感情は、ハンナさんがハンナさんでしかなかった頃彼に抱いた気持ちと同じものではない・・・とわたしは思います。
初めの頃、ハンナさんにとって彼は絶対的な存在でした。人に馬鹿にされる人生を送ってきたハンナさんに対して、彼は傷つけるようなことをしなかったのです。それが一度壊れて、ハンナさんは彼と決別しようとしました。でもハンナさんは偶然、彼を街で見かけてしまいました。ハンナさんは彼から目を離すことが出来ませんでした。それでハンナさんは、たとえ馬鹿にされようとも彼を好きだという自分が居ることを自覚します。それでジェニーとして近づいて、ハンナさんでしかなかった頃は知らなかった彼の一面にまた魅かれて・・・。
この映画を見ていて、ハンナさんのドキドキが伝わってきました。戸惑いも。自己嫌悪も。
ラストシーンではハンナさんの彼に対する新たな気持ちがまた増えている感じがします。彼の機嫌を取ることが無くなっている。彼となら対等になれるという気持ちが増えたのかもしれません。
また何度でも見たい映画です。
ジョン・アーヴィン監督 『ミネハハ 秘密の森の少女たち』
2008年5月24日 映画
まず始めに、R指定にすべき映画であることを申し上げます。
バレエと少女と女学校が出てくる幻想的な映画だ、と誤解して見ると・・・痛い思いをします。
*注*
以下のレビューは完全ネタバレしております。
残酷な描写も含みますので苦手な方は読まないことをおすすめします。
オープニングがこの映画の残酷さを物語ります。
何者かの足がバレエを踊っています。指の先から血が滲み、床を汚しトゥ・シューズの先が真っ赤に染まっても、その何者かは音楽に合わせて軽やかに踊り続けるのです。
少女たちの運命はまるでこの足のよう。
どこからか連れて来られた少女たちは、女性しかいない学校の中で成長します。この学校は、1人の公爵によって全面的に援助されています。
この学校は生徒も女性、教師も校長も女性、召使いも女性です。少女たちは自分がどこから来たのか、誰から生まれたのか知りません。
少女たちは「ここはただの全寮制の女学校」であると思いこみ、学校の敷地内にしか外出できないことにも疑問を持たず、バレエに勤しんでいました。
ある日ヴェラという好奇心の強い少女が隠し部屋を見つけるまでは。
ヴェラは隠し部屋を見つけた翌日、学校から脱走したので行方不明、ということにされました。
実際は隠し部屋から出られなくなったヴェラを校長が意図的にそのまま見捨てて、死ぬまで閉じ込めていたのです。
死んでしまったヴェラは学校の敷地内に埋められました。
ヴェラの死体が埋められるところを目撃してしまったメルジーニは、学校から逃げ出そうとしました。
けれど学校の番犬に見つかり、追いかけられ、メルジーニは悲鳴を上げながら必死に逃げました。
メルジーニは表門までたどり着いたところで番犬に追いつかれてしまい、足を噛みちぎられました。
校長は秘密を知ってしまったメルジーニにモルヒネを過剰投与し、殺してしまいました。
ブランカはバレエの主役。
ブランカは教師の1人と恋人同士でした。
ブランカは、自分の恋人ヒダラをバレエの主役にしたいと願うイレーネによって、教師と寝ているところを校長に密告されてしまいました。
ブランカは錯乱状態になってしまい、校長はブランカをどこかへ連れて行ってしまいました。
イレーネは自分の行動によって友人を1人失いましたが、恋人であるヒダラをバレエの主役にすることに成功。
けれどイレーネは自分が間違っていたことに気づきます。
主役としてバレエを踊るヒダラに、公爵が一輪の薔薇を投げたのです。
たったそれだけでイレーネは全て理解しました。
公爵が何のためにこの学校を全面的に援助しているのか。
バレエの主役になることが何を意味するのか。
…イレーネは首を吊りました。
ヒダラはイレーネの死体を見てしまいました。
ヒダラはなぜイレーネが自殺したのかその時はわからなかったようですが、それでもこのバレエが原因であることは気づいたようです。
ヒダラは踊っている途中で舞台に火を放ちました。
ヒダラは燃える舞台の上に立ち続けましたが、公爵によって救い出されてしまい・・・、公爵の館らしきところへ連れて行かれ、ヒダラは公爵に強姦されました。
公爵はそのために巨額を投じ、少女ばかりの学校を作り、バレエをさせていたのです。
自分好みの、自分のための少女を育て、好きにするために。
この学校で育った少女たちは絶対に学校から出られません。
校長も教師も召使も、もともとはこの学校の生徒。
校長、教師、召使、バレエの主役、これらの道を歩まなかった元生徒たちは、・・・恐らく殺されたか自殺したか。
死体はきっと学校の敷地のどこかに埋まっていることでしょう。
ヒダラは強姦された後、公爵の館らしきところから逃げ出しました。
けれど辿り着いた先は元の学校・・・!
公爵は広大な敷地を持ち、少女たちを徹底的に隔絶しているのです。
ヒダラが悲鳴を上げたところで映画は終了します。
―――――
わたしはヒダラが強姦されるラストシーンを見て「二度とこの映画を見たくない」と思ったのですが、この映画を嫌いにはなれません。
少女たちの衣装の可愛らしさ、音楽の美しさ、時に映し出される森の神秘性に魅せられてしまいました。
オープニングのトゥシューズについているものは血ではなく赤い松脂かもしれません。
わたしは見てすぐに血を連想したのですが・・・。
実際のところはどうなのでしょうか?
バレエと少女と女学校が出てくる幻想的な映画だ、と誤解して見ると・・・痛い思いをします。
*注*
以下のレビューは完全ネタバレしております。
残酷な描写も含みますので苦手な方は読まないことをおすすめします。
オープニングがこの映画の残酷さを物語ります。
何者かの足がバレエを踊っています。指の先から血が滲み、床を汚しトゥ・シューズの先が真っ赤に染まっても、その何者かは音楽に合わせて軽やかに踊り続けるのです。
少女たちの運命はまるでこの足のよう。
どこからか連れて来られた少女たちは、女性しかいない学校の中で成長します。この学校は、1人の公爵によって全面的に援助されています。
この学校は生徒も女性、教師も校長も女性、召使いも女性です。少女たちは自分がどこから来たのか、誰から生まれたのか知りません。
少女たちは「ここはただの全寮制の女学校」であると思いこみ、学校の敷地内にしか外出できないことにも疑問を持たず、バレエに勤しんでいました。
ある日ヴェラという好奇心の強い少女が隠し部屋を見つけるまでは。
ヴェラは隠し部屋を見つけた翌日、学校から脱走したので行方不明、ということにされました。
実際は隠し部屋から出られなくなったヴェラを校長が意図的にそのまま見捨てて、死ぬまで閉じ込めていたのです。
死んでしまったヴェラは学校の敷地内に埋められました。
ヴェラの死体が埋められるところを目撃してしまったメルジーニは、学校から逃げ出そうとしました。
けれど学校の番犬に見つかり、追いかけられ、メルジーニは悲鳴を上げながら必死に逃げました。
メルジーニは表門までたどり着いたところで番犬に追いつかれてしまい、足を噛みちぎられました。
校長は秘密を知ってしまったメルジーニにモルヒネを過剰投与し、殺してしまいました。
ブランカはバレエの主役。
ブランカは教師の1人と恋人同士でした。
ブランカは、自分の恋人ヒダラをバレエの主役にしたいと願うイレーネによって、教師と寝ているところを校長に密告されてしまいました。
ブランカは錯乱状態になってしまい、校長はブランカをどこかへ連れて行ってしまいました。
イレーネは自分の行動によって友人を1人失いましたが、恋人であるヒダラをバレエの主役にすることに成功。
けれどイレーネは自分が間違っていたことに気づきます。
主役としてバレエを踊るヒダラに、公爵が一輪の薔薇を投げたのです。
たったそれだけでイレーネは全て理解しました。
公爵が何のためにこの学校を全面的に援助しているのか。
バレエの主役になることが何を意味するのか。
…イレーネは首を吊りました。
ヒダラはイレーネの死体を見てしまいました。
ヒダラはなぜイレーネが自殺したのかその時はわからなかったようですが、それでもこのバレエが原因であることは気づいたようです。
ヒダラは踊っている途中で舞台に火を放ちました。
ヒダラは燃える舞台の上に立ち続けましたが、公爵によって救い出されてしまい・・・、公爵の館らしきところへ連れて行かれ、ヒダラは公爵に強姦されました。
公爵はそのために巨額を投じ、少女ばかりの学校を作り、バレエをさせていたのです。
自分好みの、自分のための少女を育て、好きにするために。
この学校で育った少女たちは絶対に学校から出られません。
校長も教師も召使も、もともとはこの学校の生徒。
校長、教師、召使、バレエの主役、これらの道を歩まなかった元生徒たちは、・・・恐らく殺されたか自殺したか。
死体はきっと学校の敷地のどこかに埋まっていることでしょう。
ヒダラは強姦された後、公爵の館らしきところから逃げ出しました。
けれど辿り着いた先は元の学校・・・!
公爵は広大な敷地を持ち、少女たちを徹底的に隔絶しているのです。
ヒダラが悲鳴を上げたところで映画は終了します。
―――――
わたしはヒダラが強姦されるラストシーンを見て「二度とこの映画を見たくない」と思ったのですが、この映画を嫌いにはなれません。
少女たちの衣装の可愛らしさ、音楽の美しさ、時に映し出される森の神秘性に魅せられてしまいました。
オープニングのトゥシューズについているものは血ではなく赤い松脂かもしれません。
わたしは見てすぐに血を連想したのですが・・・。
実際のところはどうなのでしょうか?
犬童 一心監督 『ジョゼと虎と魚たち』
2008年5月21日 映画
ジョゼは人魚姫の物語を知っているでしょうか。
わたしはジョゼと恒夫(つねお)くんに人魚姫の物語を重ね合わせました。この映画を見終わって、わたしは「もしも人魚姫が歩くことの出来る脚を持たず、代わりに声を持っていたとしても、王子様とは結ばれなかったかもしれない・・・」と思いました。
ジョゼは日本人です。ジョゼは歩けません。ジョゼは20歳前後くらいの女性ですが、乳母車に乗って外へ出ます。ジョゼはおばあさんと二人暮らしです。ジョゼはおばあさんに「こわれもの」と呼ばれます。ジョゼはおばあさんに、近所の人に見つからないようにしろと言われます。ジョゼは乳母車で散歩する時以外はずっと家にいます。ジョゼは学校へ行ったことがありません。ジョゼはおばあさんがゴミ置き場から拾ってきてくれる本を読んで勉強しています。ジョゼの戸籍上の名前はくみ子です。でもジョゼは自分の名前はジョゼだと言います。ジョゼはフランソワーズ・サガンの本に登場するジョゼという女性の恋物語が好きなようです。ジョゼは恒夫くんに出逢いました。恒夫くんはジョゼを、くみ子ではなくジョゼと呼んでくれます。ジョゼと恒夫くんは恋人になりました。ジョゼは恒夫くんに背負われて外へ出るようになりました。ジョゼと恒夫くんは婚約するかもしれないところまでいきました。けれどいつしか別れてしまいました。
理由はいろいろ。
若い恒夫くんにとってジョゼの存在が重たくなったのかもしれません。ある日、恒夫くんは両親にジョゼを紹介するため、ジョゼを助手席に乗せ、長距離ドライブをしました。運転後ジョゼを背負いながら、恒夫くんはジョゼに「ねえ、車椅子買おうよ」と言いました。けれどジョゼは「いやや」と言いました。ジョゼは恒夫くんと離れたくなかったのでしょう。けれど長距離運転で疲れている恒夫くんには、ジョゼの体重以上の重さが感じられたかもしれません。恒夫くんはその重さを感じる自分を嫌悪したのかもしれません。
そんな恒夫くんの気持ちを、ジョゼは敏感に感じ取ったようです。ジョゼは別れを予感していたのでしょう、海底を模したラブホテルのベッドの上で、眠っている恒夫くんにこう呟きました。「いつかあんたがおらんようんなったら、迷子の貝殻みたいに、(わたしは)ひとりぼっちで海の底をころころころころ転がり続けることになるんやろう。・・・でもまあ、それもまた良しや」と。そしてジョゼはあっさりと恒夫くんと別れました。
ジョゼの身の引き方はまるで、「王子様に生きていてほしい」と言って泡になっていった人魚姫のようです。恒夫くんは前の彼女とよりを戻したのか、ラストシーンでは前の彼女と並んで歩いています。
けれどジョゼはジョゼ。ジョゼは人魚姫ではありません。恒夫くんも恒夫くん。恒夫くんは王子様とは違います。
ラストシーンで、恒夫くんはジョゼを思い出して泣き出します。ジョゼは恒夫くんと離れて、寂しそうな、でもどこか満ち足りたような表情をしています。
わたしは恒夫くんの涙とジョゼの表情に、初めて『人魚姫』を読んだ時のどうしようもない気持ちを軽くしてもらえた気がしました。
わたしはジョゼと恒夫(つねお)くんに人魚姫の物語を重ね合わせました。この映画を見終わって、わたしは「もしも人魚姫が歩くことの出来る脚を持たず、代わりに声を持っていたとしても、王子様とは結ばれなかったかもしれない・・・」と思いました。
ジョゼは日本人です。ジョゼは歩けません。ジョゼは20歳前後くらいの女性ですが、乳母車に乗って外へ出ます。ジョゼはおばあさんと二人暮らしです。ジョゼはおばあさんに「こわれもの」と呼ばれます。ジョゼはおばあさんに、近所の人に見つからないようにしろと言われます。ジョゼは乳母車で散歩する時以外はずっと家にいます。ジョゼは学校へ行ったことがありません。ジョゼはおばあさんがゴミ置き場から拾ってきてくれる本を読んで勉強しています。ジョゼの戸籍上の名前はくみ子です。でもジョゼは自分の名前はジョゼだと言います。ジョゼはフランソワーズ・サガンの本に登場するジョゼという女性の恋物語が好きなようです。ジョゼは恒夫くんに出逢いました。恒夫くんはジョゼを、くみ子ではなくジョゼと呼んでくれます。ジョゼと恒夫くんは恋人になりました。ジョゼは恒夫くんに背負われて外へ出るようになりました。ジョゼと恒夫くんは婚約するかもしれないところまでいきました。けれどいつしか別れてしまいました。
理由はいろいろ。
若い恒夫くんにとってジョゼの存在が重たくなったのかもしれません。ある日、恒夫くんは両親にジョゼを紹介するため、ジョゼを助手席に乗せ、長距離ドライブをしました。運転後ジョゼを背負いながら、恒夫くんはジョゼに「ねえ、車椅子買おうよ」と言いました。けれどジョゼは「いやや」と言いました。ジョゼは恒夫くんと離れたくなかったのでしょう。けれど長距離運転で疲れている恒夫くんには、ジョゼの体重以上の重さが感じられたかもしれません。恒夫くんはその重さを感じる自分を嫌悪したのかもしれません。
そんな恒夫くんの気持ちを、ジョゼは敏感に感じ取ったようです。ジョゼは別れを予感していたのでしょう、海底を模したラブホテルのベッドの上で、眠っている恒夫くんにこう呟きました。「いつかあんたがおらんようんなったら、迷子の貝殻みたいに、(わたしは)ひとりぼっちで海の底をころころころころ転がり続けることになるんやろう。・・・でもまあ、それもまた良しや」と。そしてジョゼはあっさりと恒夫くんと別れました。
ジョゼの身の引き方はまるで、「王子様に生きていてほしい」と言って泡になっていった人魚姫のようです。恒夫くんは前の彼女とよりを戻したのか、ラストシーンでは前の彼女と並んで歩いています。
けれどジョゼはジョゼ。ジョゼは人魚姫ではありません。恒夫くんも恒夫くん。恒夫くんは王子様とは違います。
ラストシーンで、恒夫くんはジョゼを思い出して泣き出します。ジョゼは恒夫くんと離れて、寂しそうな、でもどこか満ち足りたような表情をしています。
わたしは恒夫くんの涙とジョゼの表情に、初めて『人魚姫』を読んだ時のどうしようもない気持ちを軽くしてもらえた気がしました。
チェン・カイコー監督 『北京ヴァイオリン』
2008年5月17日 映画
ヴァイオリンの天才少年・チュンが父親の真実を知り、ヴァイオリンを弾く意味を変える瞬間が見事な映画です。
これまでは母を求めて。
今は父を求めて。
自分の想いを伝えるために。
チュンはそれまで誰かに気持ちを伝える方法として、言葉で表現する、贈り物をして表現する、感情を顔に表して表現する、などを使っていました。
しかしラストシーンでは、ヴァイオリンを演奏をするという方法に全ての想いを注ぎ込んでいます。
チュンのその演奏を祝福する人たちがチュンの周りにたくさんいる、というラストシーンも素敵。
これまでは母を求めて。
今は父を求めて。
自分の想いを伝えるために。
チュンはそれまで誰かに気持ちを伝える方法として、言葉で表現する、贈り物をして表現する、感情を顔に表して表現する、などを使っていました。
しかしラストシーンでは、ヴァイオリンを演奏をするという方法に全ての想いを注ぎ込んでいます。
チュンのその演奏を祝福する人たちがチュンの周りにたくさんいる、というラストシーンも素敵。
田中光敏監督 『化粧師 kewaishi』
2008年5月1日 映画
一度めは音付きで、二度めは音無しで見つめていただきたい映画です。
小三馬さんがどんな眼をしているのか想像するために。
そして、そんな眼をしている男性を好きになった女性の気持ちを想像するために。
*注* 以下はネタバレありの考察です。
沢山のものをジッと見つめている小三馬さんを、純江も見つめていました。
なぜ彼はあんなに無口なのか。なぜ人に誤解されても平気でいられるのか。なぜあんな綺麗な化粧ができるのか・・・。
純江は彼に恋をしたから、誰よりも彼を見つめることができました。
見つめていたから、彼の秘密に気づきました。
純江はその秘密を誰にも言いませんでした。言わなくたって皆幸せに生活していけるし、彼が困ることになるかもしれないし、今のままで自分は彼と一緒にいられるから・・・(この辺の心理描写は詳しく描かれていないのですが、純江にはこんな想いがあったのではないでしょうか)。
けれど純江は一人娘。純江は、婿を取って家を継がなければならない、と自分でもわかっていました。わかっていたから彼に気持ちを告げず、ニコニコ笑っていました。
面と向き合っていなければ、自分の声は彼にはわからない。そう知っていたから、純江は彼がこぐ自転車の後ろに乗りながら泣きました。「小三馬さんのそばにいたいのに」と泣きました。
すぐに純江の婿は見つかり・・・、お嫁入りが決まりました。純江は彼に化粧を頼みました。綺麗な化粧が出来上がり、純江はまた涙を流しました。
涙を流した後で。純江は彼が警官に暴力を奮われているのを目にします。彼が後ろから警官に呼び止められ、その呼び止めを無視して逃げたから暴力を奮った、とのことでした。
「小三馬さんは逃げたんじゃない!」
彼に恋をして、彼を見つめていたから、純江はそう言うことができました。
彼と結ばれることはできなかったけれど。
彼を救うことができました。
人をよく見つめている彼のことですから、きっと彼は純江の気持ちに気づいていたことでしょう。
純江が自転車の後ろで泣いた時だって、彼はバックミラー越しに彼女の表情を見つめていたのです。きっと気づいていたはず。
けれど彼には見えてしまっていたのでしょう。彼に気持ちを告げない純江の気持ちも、自分を嫌う純江の両親の気持ちも、娘に婿がくるのが嬉しいという純江の両親の気持ちも、何もかも見えてしまっていたのかもしれません。
だから彼は自分が純江をどう思うか言わなかったのでしょう。
わたしは、彼は純江を好きだったのではないかと思います。なぜなら、彼の化粧は人を別人にするものではなく、本来のその人の姿に戻すような化粧だからです。
彼は彼女を綺麗に化粧しました。
それは彼が純江の綺麗さを知っていたということでしょう。
彼に化粧された純江が涙を流したのも、彼のその気持ちが伝わったからではないでしょうか。そうであって欲しいです。せめて・・・。
―――――――
<備考>
●小三馬を演じたのは椎名桔平さん。目で語る椎名さんの色気は必見です。わたしはドキドキしっぱなしでした。
●雰囲気ぶち壊しの余談で恐縮ですが・・・。
純江を演じたのは菅野 美穂さん。純江の両親を演じたのは田中 邦衛さんと柴田理恵さんです。・・・この両親から菅野さんが生まれるわけないべ! あれか、隔世遺伝か!
・・・と思わずツッコミを入れてしまいました、すみません。柴田さんが美人なのは存じ上げております。
小三馬さんがどんな眼をしているのか想像するために。
そして、そんな眼をしている男性を好きになった女性の気持ちを想像するために。
*注* 以下はネタバレありの考察です。
沢山のものをジッと見つめている小三馬さんを、純江も見つめていました。
なぜ彼はあんなに無口なのか。なぜ人に誤解されても平気でいられるのか。なぜあんな綺麗な化粧ができるのか・・・。
純江は彼に恋をしたから、誰よりも彼を見つめることができました。
見つめていたから、彼の秘密に気づきました。
純江はその秘密を誰にも言いませんでした。言わなくたって皆幸せに生活していけるし、彼が困ることになるかもしれないし、今のままで自分は彼と一緒にいられるから・・・(この辺の心理描写は詳しく描かれていないのですが、純江にはこんな想いがあったのではないでしょうか)。
けれど純江は一人娘。純江は、婿を取って家を継がなければならない、と自分でもわかっていました。わかっていたから彼に気持ちを告げず、ニコニコ笑っていました。
面と向き合っていなければ、自分の声は彼にはわからない。そう知っていたから、純江は彼がこぐ自転車の後ろに乗りながら泣きました。「小三馬さんのそばにいたいのに」と泣きました。
すぐに純江の婿は見つかり・・・、お嫁入りが決まりました。純江は彼に化粧を頼みました。綺麗な化粧が出来上がり、純江はまた涙を流しました。
涙を流した後で。純江は彼が警官に暴力を奮われているのを目にします。彼が後ろから警官に呼び止められ、その呼び止めを無視して逃げたから暴力を奮った、とのことでした。
「小三馬さんは逃げたんじゃない!」
彼に恋をして、彼を見つめていたから、純江はそう言うことができました。
彼と結ばれることはできなかったけれど。
彼を救うことができました。
人をよく見つめている彼のことですから、きっと彼は純江の気持ちに気づいていたことでしょう。
純江が自転車の後ろで泣いた時だって、彼はバックミラー越しに彼女の表情を見つめていたのです。きっと気づいていたはず。
けれど彼には見えてしまっていたのでしょう。彼に気持ちを告げない純江の気持ちも、自分を嫌う純江の両親の気持ちも、娘に婿がくるのが嬉しいという純江の両親の気持ちも、何もかも見えてしまっていたのかもしれません。
だから彼は自分が純江をどう思うか言わなかったのでしょう。
わたしは、彼は純江を好きだったのではないかと思います。なぜなら、彼の化粧は人を別人にするものではなく、本来のその人の姿に戻すような化粧だからです。
彼は彼女を綺麗に化粧しました。
それは彼が純江の綺麗さを知っていたということでしょう。
彼に化粧された純江が涙を流したのも、彼のその気持ちが伝わったからではないでしょうか。そうであって欲しいです。せめて・・・。
―――――――
<備考>
●小三馬を演じたのは椎名桔平さん。目で語る椎名さんの色気は必見です。わたしはドキドキしっぱなしでした。
●雰囲気ぶち壊しの余談で恐縮ですが・・・。
純江を演じたのは菅野 美穂さん。純江の両親を演じたのは田中 邦衛さんと柴田理恵さんです。・・・この両親から菅野さんが生まれるわけないべ! あれか、隔世遺伝か!
・・・と思わずツッコミを入れてしまいました、すみません。柴田さんが美人なのは存じ上げております。